連載●池明観日記─第32回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
》シークフリートのアメリカ論《
成人になったアメリカといおうか。André Siegfriedのフランス語の著書を英訳した“America Comes of Age”(1927年)という本を読みおえた。アメリカがヨーロッパの移民を受け入れながら成長してきた過程を詳しくたどることができた。アメリカを成り立たせた複雑な民族と宗教的背景の相異が詳細に記されていた。南部のプロテスタント勢力がカトリック勢力を排斥してきた過程もよく知ることができた。それで1963年にケネディ大統領は暗殺されねばならなかったのか。その背後には1866年に始まったクー・クラックス・クラン(ku klux klan)のような極右宗教勢力があったといわれた。そのような状況の中でアメリカは今日まで成長してきたといえるであろう。シークフリートは人種問題に対してもつぎのように記したのであった。

”No matter which way we turn in the North or South,These, seems to be no solution. The colour problem is an abyss into which we can look only with terror.”
「北部であろうと南部であろうとどこに目を向けても、解決の道はないように見える。白黒の問題はわれわれがただ恐怖を持ってのぞき込むべき深渕である」
しかしアメリカはいま黒人大統領を出現させたことで政治的峠を越えているというべきではなかろうか。ここでわれわれはアメリカがリードする今日はイギリスが支配していたかつての世界とは質的に異なると考えるべきではなかろうか。今問題がないというのではない。多くの問題があっても越えて行けるだろうと思うのだ。そしてこれはアメリカが当面している問題であるだけではなく、世界が当面している問題といわねばなるまい。このような問題においてもアメリカは先頭に立って苦しんでいる。人種問題においても、経済問題においても、世界統合のことをはじめ世界政治の問題においても、アメリカはそのすべてを担っている。シークフリートはこのようなすべての問題において、1920年代、即ち、第一次世界大戦後、第二次大戦前夜のアメリカをたどってみたといえるであろう。ソ連なき後、今まで3世紀に及ぶヨーロッパの世界支配の歴史ののち、第一次、第二次世界大戦を経て今日はアメリカが支配する時代であるといえるのではなかろうか。シークフリートはそれをかつてのイギリス支配と関連づけてアングロサクソンの世界支配としてとらえようとしたのだが、私はそれとは異なる世界秩序であるという観点からながめている。
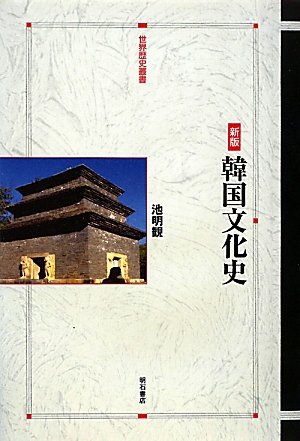
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
何よりも私は歴史の進歩という観点に立ちたいと思っている。アメリカのドルの経済と軍事力が支配する時代であり、人類が共滅することも可能であるという核武器の下で平和と交流を掲げざるをえなくなった今日の歴史ではないか。この現在の世界をシークフリートの議論と照らしてどのように考えることができるであろうか。彼が論及した「黄禍」(Yellow Peril)と「大量生産」(mass production)について少しだけ取り上げてみたい。
その当時、日本は中国と同じように言及されることを耐え難く思っていた。シークフリートは中国の三千年の歴史を取り上げた。しかし彼は白人と黄色人種との対決という構図に徹底的に固執する人であった。そのような立場でアメリカとイギリスが手をたずさえて進むアングロサクソンの世界を展望し、世界史をつぎのように描いた。
”The Americans will become sooner or later the guiding force in the Anglo-Saxon family, but the day when they will be the leaders of the whole white race is much further off.”
「アメリカ人は遅かれ早かれアングロサクソン族の指導力となるであろう。しかし彼らが全白人種の指導者となる日はずうっと後になるであろう」
こういいながら彼は黄色人種を排撃していた1920年代のアメリカを支持したのであるが、そのような政策はそのまま現代史において維持できるものではなかった。彼はアメリカの大量生産の文明に対して疑問を投げつけながらこの本をつぎのようなことばで締めくくったのであった。
”From this unusual aspect we perceive certain traits that are common to psychology of both Europe and the Orient. So the discussion broadens until it becomes a dialogue, as it were, between Ford and Ghandi.”
「この並はずれた局面においてわれわれはヨーロッパと東洋双方の心理に共通する特徴を認めるようになる。そこでわれわれの論議はいわばフォードとガンディとの間の対話というものに拡大してゆくようになる」
著者は東洋人がアメリカに移民してくることに対するアメリカの警戒心に同意しながらもフォードとガンディの対話という考えを述べざるをえなかった。彼は大量生産が投げかける人間個性の無視と文明の大衆化と浅薄化を警戒しながらこのような最後のことばを放った。しかし今日のアメリカ社会は今日の文明のなかでもっとも余裕を持っているといわねばならないのではないか。その点でアメリカはガンジーの精神性と対話しうる可能性をどこよりも多く示しているといえるかもしれない。アメリカの大量生産は世界の産業の基準というべきかもしれないが、それにもかかわらすアメリカの企業が世界のどの国の企業よりも従業員に対して余裕を与えているという事実はどのように評価しなければならないのだろうか。そしてフォードによって代表されていたアメリカの自動車産業または世界的企業が斜陽化し、1920年代の黄禍の対象であった日本のトヨタがアメリカにおいても自動車産業の象徴になりえたということをどのように考えねばならないのだろうか。モンロー主義のアメリカはどこに行ってしまったのか。多くのことを省略して一言で表現するとすれば、シークフリートが『成人になったアメリカ』において展望しながら憂えたのとは異なる世界とアメリカが、彼の時代から100年近い歴史が流れてしまった今日、われわれの目の前に現われているといわねばならないのではなかろうか。われわれの予想した世界とは異なる世界が現われているとすれば、歴史はなんと深い意味を含んでいるといえようか。歴史は常にわれわれに展望を与えるものであるが、それはわれわれの展望を超えてわれわれにやってくるものである。それはわれわれが造り、予想するものを超えてやってくるものだ。
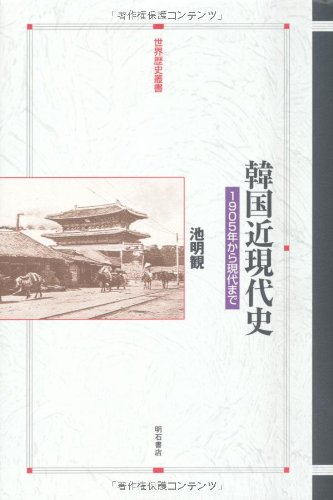
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
私は、私のこの著作をE.H.カーの名著『歴史とは何か』(1961年)になぞらえて『現代史とは何か』としようかと考えている。この本は体系的に現代史とは何かという問いに答えようとするものではない。韓国という風土の中でとりあげることであり、そこで私自身が経験してきた歴史に対して私が何度も何度も問うてきた過程を示すものである。それは盲人の一面的な解答を拒否した寓話が提起した象の姿のようなものなのかもしれないが、今日の世界史の中で南北に分断されたまま意味なき陣痛を続けていると見られる韓国の現代史について私は問い続けてきたのである。1960年韓国の4・19の年にアメリカの歴史の中ではアイルランド系カトリックの信者であるケネディ大統領を生み出し、アメリカのリベラルは歓喜した。しかし1963年に迫ってきたテキサスにおける彼の死、そしてその後を追って彼の弟、ロバート・ケネディの死。これをまさに予告でもするかのようにシークフリートはアメリカの歴史の中ではアイルランド系であるカトリック系移民はせいぜいアメリカの地方選挙までにとどまっていなければならないといった。そして「教会」とはつぎのような運命を担っているものであると彼がいった時、私は一人のプロテスタントとして驚かざるをえなかった。
”The Church stands for conservative influences in every country in the world, for the family against moral anarchy, for order against license, and for property against revolution.”
「教会は世界どの国においても保守的影響を代表する。道徳的無秩序に対しては家族を、放任に対しては秩序を、革命に対しては所有を代表する」
これは特に南米のカトリックを念頭においたことばではなかろうか。私は韓国民主化闘争の時に私が経験したことを思い出さざるをえなかった。民主化運動がつぎつぎと失敗した挫折感の中で国内の人びとが「先統一・後民主」を主張しようとした時、私は日本にいて必ず「先民主・後統一」を主張しなければならないと国内の民主化運動グループに伝えようとした。統一を優先と主張したら何よりもアカ攻撃にさらされるだろうと思ったからであった。しかしそのために後日統一優先へと走っていた民主化運動グループから私は白眼視されたことを回想せざるをえない。その頃はキリスト教勢力は大体において民主化運動の前面からは後退していたといえようか。急進主義または強硬派の台頭によって運動が分裂したといおうか。これも韓国現代政治史の重要な一駒であった。
このような思い出にふけているうちに突然一つの考えに捉われた。朴槿恵(パク・クネ)勢力というのは朴正熙(パク・チョンヒ)の残党が吐き出すことのできる最後の焔ではなかろうかという考えである。そのようにして古い勢力は消えていくのではなかろうか。つぎの世代は軍事支配をほとんど記憶もしていないであろうか。歴史とは、時間とはこのように冷酷なものであり、ある意味では空しいものであるとすらいわねばなるまい。(2014年5月29日)
≫『北回帰線』を読んで≪
ヘンリー・ミラーの『北回帰線』(原作1934年、新潮社刊1969年)を読み終えた。ミラーは1891年のうまれであり、この作品は彼の初期作品であって、その頃彼はすでに40歳を過ぎていたであろう。彼は絶望のあまり死を考えていたが、パリへと向かった。北回帰線、そこは人間の目を離れた無秩序の地であるように見えるが、結局それは彼が逃避すべき地帯であった。この本を読み続けるためには私はかなりの忍耐心を持たねばならなかった。奇抜な表現や修飾を検討するとすれば、だいぶ努力をしなければならなかったが、適当に読み過ごしたといえよう。人生哲学をくり広げているような難渋な文章が続くかと思うと、巻末においてフランスの女性を捨ててアメリカにひそかに帰って行くフィルモアを描いた文章は、ほとんどほかの作家たちの文章と変わらない特別な飛躍のないごく常識的な文章であった。この作品にはそのような文章ととても変わった修飾が続く文章とが混ざりあっているといえよう。そのように二つの種類の文章が場所を異にして固まっているように見えた。
多くの売春婦との関係が続く程度だという思いから私はこの小説を読み終える必要があるだろうかと考えたが、終わりまでがまんして読み終えるとミラーの他の作品も読みたいという気持ちになった。この作品に対して私が文学的に何かいえることはない。1934年といえば第二次大戦の前夜、アメリカにおいてもアメリカ脱出を希望する世代があった頃ではなかろうか。二箇所だけ引用して考えてみたい。ミラーはフランスと比較してアメリカをつぎのように描いた。
「海の向うでは、人々は、いつの日か合衆国の大統領になることしか考えない。潜在的にはあらゆる人間が大統領の器なのである。ここではちがう。ここではあらゆる人間が潜在的にはゼロなのだ。もし何ものかになれば、それは偶然のことにぞくする。奇蹟である。生れ故郷の村を出るなどというチャンスは千に一つしかない」
私にはどうしてか韓国においては大統領とは誰もなりうるのだという「錯覚」が長く続いてきたように思われる。韓国は両班と常人という区別があったにしても日本に比べれば厳格な階級制度はなかった社会であったといえるのではなかろうか。このような考えが私の頭から離れない。そのような韓国の社会において解放、6・25の朝鮮戦争、南北分断などと伝統的な社会がほとんどくずれてしまったことを考えざるをえない。そこでなんでもない存在であるというべき者が自分を大統領と呼ぶようにと強要してきた。反日の愛国者の時代は過ぎ去ってかつての親日派でさえ大統領の座をしめるようになってきたではないか。大統領にカリスマが全く伴わない今日のような時代をわれわれはどのように生きて行くのかと考えざるをえなくなる。
フィルモアはフランスの女性から逃げ出すのであるが、アメリカの「ピューリタン面をした奴ら」を憎悪しながらも、それほど熱狂していたフランスに対してつぎのような非難を口にするようになる。
「彼らは残酷で強欲だ。はじめのうちはすばらしく見える。それというのも、自由感を味わうからだね。しばらくするといや気がさしてくる。心の底では、いっさいが死んでいるのだ。何の感情もなければ、同情もなく、友情もない。奴らは骨の髄まで利己的なのだ」
この小説の終わりにはアメリカへの回帰というきざしが現れる。これはアメリカ人にのみある心情ではなく誰にも見られる心情であるといえるが、特に現代アメリカ人においてはどこに行ってもそのような「郷愁」がついて廻るようである。現代史とアメリカ人または「米国観」は追求してみたい課題である。
やがて解放69周年、日本統治時代の倍にもなる年月が、解放と南北分断から流れたことになるのではないか。南北がこれからますます遠くなるのではなくもっと近くなる関係にならねばなるまい。歴史には永久の諦念などありえないのではなかろうか。(2014年6月28日)
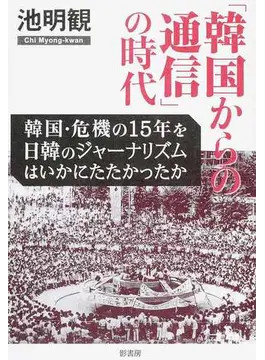
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
日本の早稲田大学大学院のYからEメイルが来た。韓国における軍事政権の時代に展開された民主化運動を南アフリカのネルソン・マンデラ、ミャンマーのアウンサン・スー・チーそして中国の魯迅とともに研究してみたいというのであった。それで私は政治家個人に対する研究よりは彼らの闘争戦線とでもいおうか、そのような集団または国民の闘争を比較しながら研究した方がよかろうといいながらアーノルド・トインビーとクレイン・ブリントンの研究を例としてあげた。
トインビーの場合は彼が1776年のアメリカの独立運動が地球を何回か廻りながら近代革命を引き起こしたことを問題にしたことをあげ、クレイン・ブリントンの場合は『革命の解剖』においてアメリカの独立革命、フランス革命、ロシア革命を比較しながら論じたことをあげた。クレイン・ブリントン以後、20世紀後半から21世紀の初めにかけて起こった世界革命を比較して論じてくれれば、いかに有難いことであろうかといった。その時代にスペインやギリシャの革命もあったが、大体において非ヨーロッパの革命をわれわれは研究してみるのがよかろうといった。
そして私はアメリカの独立運動が民主主義を指南し、その後アメリカの政治がそこから動揺しなかったことを重要視せざるをえなかった。フランス革命はナポレオン戦争を呼び起こしたようにいかに動揺したことか。現代になってようやくフランス革命は安定の道にたどりついたといおうか。アメリカの革命は保守と進歩の間を往復したといえるけれども民主主義という道からはずれることがなかった。韓国の民主主義も今まであまりはっきりした道を歩んできたとはいえないといえるかもしれないけれども、今や専制に逆戻りすることはないといえるであろう。1960年の4・19民主革命は軍事政権という反動をよび起こしたが。
このような観点からすれば、近代国家としてのアメリカの先進性を問題にすることができよう。それは失敗したことのない民主主義の道であった。それでアメリカは民主主義国家のモデルとなっているといえよう。そのような意味でも現代史はアメリカを中心に動いているといえるであろう。もちろん世界史としての現代史そのものがアメリカを中心に動いているという現実である。ソ連がスローガンとして叫んだ平等社会というのは実際において恐しい力でもって強要された不自然な、非歴史的な不平等社会、いわば人間の恣意によって強要された人工的な社会ではなかったか。
歴史は終局的には自然の流れに戻るものだ。今日における多数の名における独占ともいうべき民主主義の不自然さは克服されねばならない。合理的な、善意の合意のみが民主主義ではなかろうか。アメリカは1960年代の急進的といえる民権運動は拒否したのだが、大統領オバマに至る政治の道を許容したがために民主社会であることができた。韓国も今の朴槿恵の反動の時代を超えて、そのような歴史の道を踏み続けねばなるまい。これで成熟した民主社会と言えるのではなかろうか。いわば革命のない、革命の時代をのり超えた民主社会である。この点でもアメリカは先頭に立って進んで行くといえるであろうし、その歩みを後進的な諸国民は追っていくのであろう。このような意味ではアメリカの先進性をわれわれは確かに認めねばなるまい。
もう一つそれにもかかわらずアメリカ史の暗い面を指摘せざるをえない。現代の国際秩序においてアメリカが自由貿易を主張するおかげで、実際、後進国はその線に沿って国家的発展を追い求めてきたといえるであろう。それはアメリカが今まで豊かな土地において足りない人力を機械文明で補いながら先導してきた文明に脅威を与えることにもなるであろう。それによって起こる貿易赤字をアメリカはどのようにカバーすることができるであろうか。多分アメリカの社会はほかの分野における優位性によってこれを補充しようとするであろう。世界の高級な頭脳がアメリカを目ざし、世界教育自体がアメリカを指向する。アメリカの頭脳だけではなく世界の頭脳がアメリカに指向して集結する。
それは一つの例に過ぎない。私は特にアメリカの武器輸出の問題を考えるのだ。例えば世界に対する核武器を含めた武器開発に対する抑制というのは世界のためでもあるが、アメリカの国家利益のためにも必要なことであろう。それでアメリカは世界平和を前提としながらも、一定の危機を必要としているのかもしれない。そのためにある意味ではイスラム国家、ロシア、中国もこのようなアメリカの国家利益のためになっているというアイロニーは世界史のジレンマでもあるといえようか。
このような人間社会の矛盾、そのような矛盾を担わざるをえないという人間歴史にすくっている不可避性は人間歴史の限界といおうか、エニグムとでもいおうか。そのような考えにふけりながらYへの返書をしたためた。出版文化の全盛時代も終わって行くであろう。コンピューターの時代をどう迎えるのか。書簡文の文学的価値を云々する時代は終ったのではないか。コンピューター通信は簡潔で便利でなければならない。修飾の多い文章は古文へと編入されて行くかもしれない。それは国文学の時間には残るかもしれないし、文学的営みのためには残っているといえるかもしれないが、われわれの平凡な生活の中からは消えて行くものと思える。それを文明の前進といわねばならないのではないか。このような文明の疾走をいま私たちはぼんやりとながめているかもしれない、後悔することもなく、この私にとっての最後の本も自費出版をしなければならない時代であるなどと考えながら。(2014年7月10日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
