特集 ● 2025年11月・秋
立憲民主党は自民・維新の高市新連立政権にどう立ち向かうのか
選択的夫婦別姓すら実現できない政治に、日本の未来を託することはできない
語る人 立憲民主党代表代行 衆議院議員 吉田 はるみ
聞き手 本誌代表編集委員(日本女子大学名誉教授)住沢 博紀
緊急質問:自民・維新連立政権に対する立憲民主党と野党の対決法案
1.ロンドンでの金融業の仕事から、日本政治への挑戦へ
2.3度の敗北と選挙協力のモデルとしての東京8区での活動
3.高市早苗自民党総裁誕生と立憲民主党の女性政治家のポジション
4.選択的夫婦別姓すら採択できない政治では、日本の未来はない
5.公明党の政権離脱と新しい野党協力の可能性と意義
緊急質問:自民・維新連立政権に対する立憲民主党と野党の対決法案
住沢 このインタビユーは10月17日に行われましたが、その後、自民・維新の連立合意がなされ、高市早苗首相が誕生しました。初の女性首相誕生ということで、当面は高い支持率を得るでしょうが、自民党の政治とカネの問題は何も解決していません。自民党と維新の会との連立合意文書は12項目の詳細なものですが、例えば「社会保障改革」に関しても多くの問題をはらんでおり、維新の会の要求を自民党が丸呑みしたような内容です。そこで11月6日現在までの新しい政治の動きを踏まえて、緊急質問としていくつかの問題点を設定しました。
1点目は、現在、公明党と国民民主党が政治献金を巡って、共同提案を提出している件です。具体的には献金先を限定するという事ですが、この政治献金の規制に関して、立憲民主党はどのような形で対応しようとしているのでしょうか。

吉田はるみさん
吉田 立憲民主党自身の政策としては、企業団体献金の廃止を掲げており、私も法案提出者の1人として法案を提出しています。しかし、政治資金規正法の議論において、高市総理の答弁を見ていると、非常に後ろ向きだと感じています。これ以上、積極的に取り組むつもりはないように見受けられます。したがって、少しでも事態を前に進めたいという思いから、公明党・国民民主党が提案している受け手側の規制については、可能性として検討する余地があるのではないかと考えています。
住沢 それは共同提案という形になるのでしょうか。
吉田 いいえ、法案は既に国民民主党と公明党から提出されていると思いますので、後から立憲民主党が共同提案することはないと思います。
住沢 具体的に、どのような形で協力されるのでしょうか。内容の修正を求めるのか、それともそのまま賛同されるのか。
吉田 申し訳ありません。私自身は、具体的な状況について担当ではないため、詳細を把握しておりません。ただ、立憲民主党としては、両党が提案した受け手側の規制という政治資金規正法の改正を、一歩前進と捉えているということです。
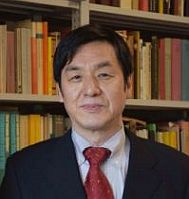
住沢博紀
住沢 承知いたしました。次の質問ですが、日本維新の会との協定の中で、維新の会が最重要課題として、選挙制度、特に小選挙区の定数削減を提案し、年内に結論を出すという話になっています。この問題に関して、多くの政党は反対すると思いますが、立憲民主党としてはどのように対応し、他の政党とどのように協力していくおつもりでしょうか。また、自民党の中にも批判的な意見があると思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
吉田 この点については、野田佳彦代表が以前、議員定数の削減を当時の安倍総理に要望した経緯があるため、削減自体には賛成の立場を示しています。しかし、そのやり方として、自民・維新両党が比例代表から50議席を削減するという案を提案していますが、これには反対です。
そもそも、現在の小選挙区比例代表並立制が導入された際、長い議論の末に小選挙区と比例代表の割合が3対2に決まりました。もし議員定数を削減するのであれば、小選挙区も合わせて検討しなければ、このバランスが崩れてしまいます。比例区だけを削減してしまうと、少数政党や多様な意見が反映されにくくなり、自民党と維新の会にとって都合の良い定数削減になる危険性があります。したがって、この問題点を明確にした上で議論していく必要があると考えています。
住沢 その理屈は理解できます。しかし問題は、維新の会が高市政権と連立を組むにあたり、この件を最も重要な条件としており、年内という期限を設けている点です。こうした点を踏まえると、むしろ自民・維新連立政権を追い詰めるような方法になると思いますが、多くの野党や自民党の一部が反対している状況で、どのような戦略をお考えでしょうか。
吉田 そもそも、今協議会を作るというニュースが流れてきましたが、どこまで進むかは正直分かりません。ただ、維新の会は、これが実現しなければ連立はあり得ないという立場を示しているので、何らかの法案を提出するとは思います。しかし、多くの野党が反対の立場を取っているので、反対の理由や問題点を明確にする必要があります。そうした方々と連携していくしかないと考えています。
それよりも、彼らがどう言おうと、真の身を切る改革は企業団体献金の規制です。維新の会抜きで、この問題に取り組むべきです。維新の会もかつては企業団体献金の廃止を主張し、共同で法案を提出したこともありました。私もその提出者の1人ですし、維新の会にも賛同者がいました。まずは、この議論を進めることです。廃止が難しくても、受け手側の規制について、国民民主党と公明党の案に賛同し、実現に向けて働きかけることが重要だと考えています。
住沢 わかりました。最後に、少し中長期的な話になりますが、給付付き税額控除方式についてお伺いします。これは立憲民主党が以前から提唱している政策ですし、税制・社会保障の学者の多くも賛成しており、高市政権も同じような言葉で異なる趣旨のことを言っているように思います。今後、内容が大きく異なる可能性がある中で、立憲民主党は、現在のインフレや物価高騰などの問題に対し、どのような具体的な対策を考えているのでしょうか。
吉田 まず、給付付き税額控除が実際に制度として実現するまでには、短期間では難しいでしょう。少なくとも1~2年はかかると思います。その間、物価高騰対策をしないわけにはいきません。そのために、立憲民主党は食料品の消費税0%を掲げています。
現在、食料品に対する消費税を5%に軽減したり、廃止を訴えたりする政党もありますが、消費税に着目している野党が圧倒的多数です。これらの野党が、消費税減税に関して意見を擦り合わせ、法案を共同提出できれば、可決される可能性は高いです。そうした取り組みこそ重要だと考えています。議員定数を削減しても、国民生活は豊かになりませんし、国民を支えることにはなりません。参議院選挙では、消費税について訴えた結果、一定の成果が出ました。したがって、消費税の問題についてしっかりと議論し、国民に訴える政策を実行していくべきだと思います。
ちなみに、参議院選挙では、自公で45議席、消費税に関して、食料品の税率を5%に軽減、もしくは廃止を訴えた政党を合わせると77議席になります。45対77です。公明党も、昨日の斉藤代表の代表質問で、軽減税率をもっと引き下げることも視野に入れると発言しており、消費税に言及しています。ここが鍵になると考えています。
住沢 しかし、立憲民主党の消費税減税は、2年間という期限付きだったと思いますが、食料品に関しては恒久減税ということでしょうか。
吉田 給付付き税額控除が実現するまでの措置ということです。制度設計が完了するまでの間です。
住沢 わかりました。近いうちに、公明党、国民民主党、そして立憲民主党という3党が、比較的安定した野党勢力として協力していくことになるかもしれませんが、公明党が自民党から離脱した後、そうした新たなコアを作る動きは進められているのでしょうか。
吉田 様々な形で、政策ごとに連携しようという動きが生まれています。今の消費税の話もそうですし、選択的夫婦別姓やガソリンの暫定税率についても、今年の実現は野党が協力して政府に働きかけた結果です。これらの政策については、立憲民主党が中心となって取りまとめてきました。今後も、そうした取り組みを続けていくことになると思います。
住沢 ガソリン税については、共産党も含め、野党全体で一致して実現したというイメージですが、立憲民主党が中心になってやったという報道はあまり見かけません。
吉田 立憲民主党の税制調査会長である、重徳和彦議員が尽力しました。
住沢 本日は緊急の質問に答えていただき、ありがとうございます。
1.ロンドンでの金融業の仕事から、日本政治への挑戦へ
住沢 高市早苗さんが、初の女性として自民党総裁に選出されました。今、維新の会と連立政権の交渉が進んでおり、初の女性首相が誕生するかもしれません。その問題は後に触れるとして、吉田はるみ衆議院議員は、立憲民主党の中では少し異色の経歴を持って政治の世界に参入されました。国際的に様々な形でキャリアを積まれる中、日本の政治や政治家をどのような段階で意識されたのでしょうか。
吉田 政治の力を意識したという意味では、20代後半に母が51歳で脳卒中で倒れた時が最初です。当時、政治に無知だった私は高額療養費制度を知りませんでした。母が3ヶ月間集中治療室にいた際の費用が、政治によってカバーされることを知った時、人生のセーフティネットとしての政治の力を感じました。
住沢 世界を色々回ったことが政治に関心を持つきっかけではないのですね。
吉田 全く違います。崇高な理由ではなく、無知だった自分が政治の力を感じたのが最初です。その後、ロンドンで仕事をしていたのですが、民主党政権の時代で、政治が変わることを感じていました。母のことがあり、自分自身も癌になったりして、人生の節目で立ち止まって考えることがありました。その時、世襲でなくても、周りに政治家がいなくても、困った時に支える力になりたいという思いで政治家になれないかと考え、民主党の公募に応募したのがきっかけです。
住沢 民主党の政権時代とすると、公募に応じた方々は様々なキャリア組やビジネス関係の人が多かったですか。また公募に申し込まれた際、一番のセールスポイントは何でしたか。
吉田 公募での応募は多かったと思います。応募は数千件あったと聞いています。面接も数日間行われたようです。面接では、政治と関係ない分野から来たこと、山形県の出身であること、母の病気がきっかけで政治を志したこと、そして当時ロンドンの金融業界にいたことなど話しました。田舎出身でありながらグローバルな仕事をしているというギャップが印象に残ったのかもしれません。
住沢 民主党(当時)を選んだのはなぜですか。
吉田 考え方が近かったからです。ロンドンの金融業界は市場自由主義の拠点ですが、私は権力や強者の理論とは相容れないところがあり、本当に政治が必要なのは投票に行けないような弱い立場の方々だという思いが根底にありました。そのような人たちに寄り添うのが民主党だと思いました。自民党は代々政治家の家系が多く、外部の人を歓迎する雰囲気はなく、庶民出身の自分はコンプレックスを感じるだろうと思いました。民主党は門戸を開放しており、誰でも受け入れる雰囲気がありました。
住沢 ロンドンで金融の仕事をされていて、民主党には国際関係のエリートもいましたが、どのように自分の強みをアピールしましたか。
吉田 日本経済の衰退と外国人との共生についてアピールしました。海外で仕事をしてきたからこそ、日本経済の衰退を強く感じていました。イギリスも移民政策を行いましたが、お互いを理解するまでに時間がかかりました。日本は人口減少社会なので、イギリスの経験から学び、共生社会を早く目指すべきだと訴えました。経済という意味では、金融の仕事をしながら、日本が衰退している原因を考えていました。周りの国が成長している中で、日本は沈没しているように見えました。金融業界にいたからこそ、対日投資や日本の立ち位置が下がっている理由を考え、魅力的な産業や技術がないことが原因だと考えました。
他国では、政治家が先回りして産業界を引っ張っています。日本は産業界が政治に期待せず自分たちの力で行こうとしていますが、政治ができることはもっとあるはずです。中国や韓国の政府はもっと早くから産業界を連れてプロモーションに行っています。政治経済というように、日本の政治がしっかりしないと経済は良くならないと感じ、政治の道に進みました。
私は過去30年の日本衰退の原因は教育にあると思い、教育×経済を提唱しています。教育分野での提言をたくさんさせていただきました。初等教育から高等教育まで全てです。公教育が衰退し、教員不足で大変な状況になっています。お金がないと良い教育を受けられず、少子化にも繋がっています。高等教育でも研究力が問われますが、運営交付金は削られています。自民党政権下で、教育も研究も削られてきた30年間でした。そういった問題点を訴え、後に立憲民主党の代表選挙にも出馬しました。
2.3度の敗北と選挙協力のモデルとしての東京8区での活動
住沢 民主党の公募候補者として、異なる選挙や選挙区で挑戦され、3度の落選を経験されています。それぞれの選挙戦では、その地域に合わせた訴えをされたのですか、それとも以前から訴えていた日本の大きな課題や女性問題などを訴えられたのですか。
吉田 政治家が政治の話をしても、あまり訴えは届きません。生活に根ざした、誰もが当事者意識を持てるようなことを訴えるようにしています。千葉での県議選、参議院選挙での岩手、衆議院選挙での杉並での落選という3回の落選を経験し、地域も異なりました。これは女性が政治に参加する際の問題点だと思います。全く政治家の知り合いがいない中で、志だけで飛び込みました。
一票の格差で市川・船橋にかけて新しい衆議院選挙区ができるので、まずは千葉で県議選からと思って始めました。しかし、落選しました。その後、参議院選挙で岩手に行きました。候補者がいませんでしたから、大船に乗ってこいと言われましたが、全然大船ではありませんでした。無知ゆえに選挙区を変えてきましたが、政治の基本や、勢いのある場所、可能性のある場所などを知っていれば、こんなことはしなかったと思います。
痛い思いをしましたが、杉並に来た時には、選挙区を離れず、徹底的に活動することが重要であると覚悟を決めました。トライアンドエラーの期間は貴重な経験でしたが、知っていれば避けられたこともあります。特に女性は候補者として使い捨てにされることが多いので、なくしたいと思っています。杉並での初当選の際に野党共闘で出馬しましたが、共闘ができたのは公示のわずか3日前です。その際はむしろ私が排除されそうになりました。
住沢 ご自分の応援団体は作られましたか。また労組の支援はどうですか。どのように地域の市民運動と結びついていったのですか。
吉田 杉並で国政報告会や集会などを行っています。労働組合の方々とは働く者の政策で連携しています。選挙はボランティア、後援会の方々が中心です。
最初の落選の時は、市民運動の方々と関わるのが怖かったです。批判的な目で見られているように感じ、政策や政治知識も未熟だったので、引け目を感じていました。しかし本音で語り合うようになり、2017年の落選を機に、次が最後だと思って、やりたいことをやろう、言いたいことを言おうと思い、市民の皆さんと本気で向き合うようになりました。そこから関係が大きく変わりました。都知事選で協力したり、地域のタウンミーティングを開いたりしました。社会運動的なものへの参加はなかったですね。
住沢 立憲民主党は小選挙区では野党間の選挙協力が重要であり、東京8区は紆余曲折がありながらも2021年衆議院選挙では候補者調整が成立して当選されました。そして2024年、昨年の総選挙では、多党化の流れの中でも再選されました。東京8区での吉田議員の体験と活動実績は、野党の選挙協力のモデル、あるいは成果と呼べますか。
吉田 モデルとしてというわけではありませんが、女性の議員が増えたモデル地域だと思います。私が当選してから6ヶ月後に杉並区長が初の女性になり、その後の統一地方選挙で議会の半数が女性になるパリテ議会ができました。この2年間の変化について、何がキーだったのかを皆が学びたいということで、色々な所でお話をしたり、女性議員をどうやって誕生させようかという話が来ることが多いです。
住沢 杉並以外で、立憲民主党が女性議員を増やしていくシステムは作られますか。
吉田 常にやっていかなければいけないと思います。反省点として、一人の議員が頑張るだけではダメです。自治体議員の力を引き出すことが必要です。立憲民主党には1300人の自治体議員がいます。立憲民主党は色々叩かれたりしますが、地域に根ざすネットワークもあります。熱意と志を持って政治の道に入ってきた人たちの力を引き出したいと思っています。それは男性女性と関係ありません。
議員同士で先生と呼び合うのをやめ、区議会議員、都議会議員、国会議員という縦社会ではないことを徹底しています。それぞれの議会でミッションを持って活動していることに敬意を払い、フラットな仲間として連携しています。自民党にはできないことだと思います。地域によっては浸透していないところもあるので、代表代行として各級議員が連携できる横の文化を浸透させていきたいです。
3.高市早苗自民党総裁誕生と立憲民主党の女性政治家のポジション
住沢 高市早苗さんが総裁になられましたが、高市さんをどう見ていますか。ネガティブなモデルですか。またSNSでは岩盤保守と思われる投稿者からの、高市新総裁への賛美と期待で溢れていますが、これをどう思いますか。
吉田 高市さんは高市さんの選択をされたのだろうと思います。私はその選択はしませんが、多様性や個人を大切にするのか、社会や国が先に来るのかという点で彼女とは大きく違うと思います。
SNSの匿名での言論は、複数のアカウントを使ったり、海外を経由したりして世論を形成しようとする動きもあるので、あまり流されたくないと思っています。岩盤保守というより、私が言うことにネガティブなことを入れてきます。ネトウヨの方によく絡まれますが、そういう反応もあると思っています。本質を考えることを放棄しているように感じます。分かりやすさや、日本の尊厳といった言葉は使いますが、表面的な印象で良さそうと感じていることに危機感を持っています。
住沢 高市さんとは多様性の問題の違い以外に、自民党の長老たちの存在があります。総裁としての視点について、有力政治家の操り人形ではないかという批判もありますが、どう思いますか。
吉田 それに乗っかって成功する方法もあると思いますが、静かに闘っている女性たちもいると思います。声を上げて闘う方法もあれば、静かに闘う方法もあります。正論を言っても通じない場合もあるので、文化を変える時には違うアプローチを考えなければいけません。しかし、決して諦めてはいけないと思っています。重鎮が後ろで糸を引いているのなら、あなたでなくても良い。あなたにしかできないことを政治家はやるべきだと思います。
住沢 立憲民主党は女性活躍を掲げており、候補者も半数にすると言っていますが、泉代表の時代の執行委員会では12人中6人が女性でした。現在、執行部の11人中4人が女性です。
吉田 数ではないと思います。そもそも女性の議員の数が少ないので、半数を女性にするとアンバランスになることもあります。男女関係なくやるべきだと思いますが、数のマジックに惑わされない方が良いと思います。政府が目標にしている2030年の女性管理職30%も、社外から入ってくる人が多く、生え抜きの人がいません。数字だけでなく中身を見なければいけません。候補者を半数にするのは比例名簿に名前を載せれば実現は簡単ですが、本気で当選させようと思っているのか、選挙区はどこなのかというところまで見ています。もちろん女性はもっと増えてほしいと思っています。
住沢 立憲民主党の執行部は、野田代表をはじめ旧民主党政権時代の男性政治家が多いイメージがあります。女性の活躍やそのための政策を提起しているだけに、このイメージは残念です。このため『現代の理論』では、立憲民主党に対して、男女の共同代表制の導入を提起してきました。ドイツの社民党、緑の党、それに極右のAFDまで共同代表制であり、それぞれ役割分担で成果を挙げています。
吉田 男女共同代表制は面白いと思います。ジェンダーのことをもっとも取り上げている政党としては、現在のイメージは弱いと思います。ネクストの影の内閣には一期生や二期生の女性議員が入っているので変化はありますが、執行部にもっと入っていくと良いと思います。女性が3割を超えると私たちの声は大きくなります。議会も組織も女性議員が3割を超えると変わってくると思います。
住沢 ヨーロッパでは極右ポピュリスト政党を女性党首が率いているケースが目立ちます。イタリアのメローニ首相(イタリアの同胞)、フランスのマリーヌ・ル・ペン(国民連合)、それにドイツのアリス・ワイデル(AfD)です。それぞれ雄弁で人気があります。この現象をどう見られますか。
吉田 女性政治家の発言は、耳を傾けやすく、言い切ることで力強い訴えに聞こえてきます。そして右翼的な人が現在は多いことだと思いますが、ポピュリズムを体現しているのではないかと思います。危機感を感じます。男性よりも、女性の方が忖度なく言ってくれると思っている人が多いのかもしれません。
4.選択的夫婦別姓すら採択できない政治では、日本の未来はない
住沢 日本社会がグローバルな発展に追いついていけない理由の一つに、女性の低い地位や活躍の場が少ないことが挙げられます。選択的夫婦別姓制度は、公明党を含めた野党はもちろん、連合、経団連、それに自民党の女性議員、国民の多数など、幅広い支持があるのに国会での法案審議に登場しません。山口二郎さんや中北浩爾さんなどの政治学者も、現在の政党配置ではなかなか難しいといっています。高市自民党やその岩盤支持層にとって、この問題は、日本の家族制度や「固有の伝統」を守るべき生命線としています。こうした制約を突破する道筋はどうすれば可能でしょうか。
吉田 これができないと日本の新しい1ページは開けないと私は思っています。選択的夫婦別姓の話をすると、もっと大事な経済政策があるだろうと言われますが、これが通せない国がどうやって変われるのか問いたいと思います。女性活躍と言ってきましたが、選択的夫婦別姓すら通せない国は変われないと思います。象徴的な変化になるので、通したいと思っています。
しかし、今、自民党と維新の会が一緒になり連立政権です。どちらも通称名使用の党ですよね。この状況は非常に難しいです。自民党の内部でも選択的夫婦別姓に賛成の議員がいますが、前回通常国会が一番チャンスでした。法務委員会で委員長を野党が取っていたので、自民党の賛成議員に、法案に党議拘束を外して賛成するのかと問いたいです。選挙の時は賛成と言っておきながら、採決の時に党がダメだと言って取り下げるなら、有権者に対する裏切りだと思います。政治家は選挙の時に賛成と言うけど、実際は党がダメだからと言うことがあります。
高市政権が誕生し、そこに維新が乗った今、選択的夫婦別姓を実現するには政権交代しかないと思います。今はあらゆる手段で潰されます。また選挙の対立軸にもならないかもしれません。これで票が増えるかと言われると、政策の優先順位からすると、日々の暮らしが先に来ます。選択的夫婦別姓に賛成の候補という点だけでは、票を入れる一番の理由にはならないかもしれません。若い世代でも、20歳の集いの後に政策アンケートを取ると、選択的夫婦別姓を知らない人が結構います。仕事をしていないと分からないですよね。
5.公明党の政権離脱と新しい野党協力の構想と政策
住沢 国民民主党の玉木さんが自民党と連立を組めば、多様なグループの集合体である立憲民主党の立ち位置は難しい面もあったかもしれませんが、公明党が政権から離脱し、維新の会が高市自民党と連立協定を進めている現在、立憲民主党、公明党、国民民主党が主要な野党を構成するという可能性が高まりました。70年代の社・公・民を想起させる政党配置ですが、先祖返りをしないためにも、21世紀の日本の立て直しを実現すためにも、新しい野党協力の構想と政策を聞かせてください。先ず今回の公明党の政権離脱をどのように評価されますか。
吉田 良いと思います。公明党が連立を離脱するのは永田町には衝撃的だったと思います。政策的には立憲民主党と重なる部分が多いのです。国民民主党も働く人のための政党なので、共通政策を出していくべきです。平和と福祉という意味では、公明党と重なる部分があります。政策を実現するために大きな塊を作れたら希望になると思います。それぞれの選挙区で聞こえてくる生の声も大切にしなければいけません。
住沢 多様な選択肢や政党間の交渉が続く現在、立憲民主党は求心力が増していますか。それとも党内では多様な意見が生まれてきていますか。玉木さんに対して、立憲民主党はどう対応しようとしていますか。トランプのアメリカは、NATO同盟国に対して、ロシアとウクライナを取り持つ局外者のような立場に立っています。当然、安保法制に関してもその前提が大きく変化してくる可能性があります。安保法制と原発継続を立憲民主党との和解不能な基本政策として掲げる玉木国民民主党に対して、立憲民主党はこうした「分断」路線を乗り越える、どのような構想を持っているでしょうか。
吉田 むしろ求心力が出てきているのではないですか。この局面で何ができるのかを考えています。公明党が連立を離脱したことは驚きでしたが、腹を決めて野党集結の大きな塊をつくらなければいけないと思っています。
安全保障問題に関しては、外交防衛の部会等で議論しています。自民党に変わる政権として、立憲民主党は議員数が多いだけでなく、人材の幅も大きいです。中国・韓国や台湾そして東アジア諸国との議員外交を積極的に行っています。現実的な外交防衛のあり方を考えています。対トランプに対しては、日米同盟を基軸としながらも、国際法が守られないという問題がある時は、絶対に譲歩しないという立場を強く打ち出すべきだと思います。
力を入れているのが議員外交です。私は今夏、韓国に行きましたし、韓国の議員も先日日本にいらっしゃいました。日米韓の議員間の会議も予定されていましたが、アメリカの議会が不正常になり来日されなかったので、日韓だけでやりました。アメリカとしては、日韓がアメリカのいないところで親密になるのを嫌がっているのかもしれませんが、安全保障面でも情報を共有しながら関係を作ることは大切だと思います。
住沢 最後に、吉田さんは代表代行として立憲民主党の執行部の中心にいますが、自分の役割やできることは何だと思いますか。
吉田 全国にいる立憲民主党の自治体議員、党員の方々の力を引き出したいと思っています。立憲民主党は本来、ボトムアップの政党だったと思いますが、少し変わってきているところがあるので、もう一度ボトムアップを引き出したいと思っています。女性議員の力をもっと発揮してほしいので、ジェンダー政策に力を入れたいと思っています。
候補者の募集に関しても、一時期よりは減ったかもしれませんが、この時期に応募される人は素晴らしい方が多いです。参政党など数百人も応募が来ていると報道されていますが、全員が議員になれるとは思えません。人間は苦しい時に試されるので、こんな時だからこそ、立憲民主党を選んでくださる方々が当選して議員になってほしいと思います。
議員という仕事は大変ですが、素晴らしい仕事だと思います。たくさんの声に触れ、たくさんの出会いがあり、誰かの力になることができる。法律や予算編成にかかわることもできます。やりがいがあるということをもっと発信していくべきだと思います。誹謗中傷、過酷な選挙、そしてワークライフバランスのない厳しい状況など、大変そうで割に合わないと思っている人が多いので、もっと人の役に立てる議員の魅力を発信していきたいです。
若い世代が挑戦することに関して、その人たちが地方議員になった場合、その後のキャリアをどうするのかという問題があります。一生政治家でなくても良いと思います。選挙は、仕事を辞めて挑戦するのでハードルが高いです。落選したら仕事に戻りたいと思っても、履歴書に特定の政党かつ選挙に立候補したと書くと、採用されにくいという現実があります。政治は一つの通過点にしても良いと思っており、キャリアとして政治に挑戦することをポジティブに捉えてもらえるような社会の理解が必要です。被選挙権改正で18歳や20歳の議員が誕生することは素晴らしいことですが、その方が、一生涯議員でいる必要はないと思います。キャリアのステージを変えていけるようにしたいです。
よしだ・はるみ
1972年、山形の八百屋の長女として生まれる。
立教大学文学部卒業。英国立バーミンガム大学大学、経営学修士(MBA)。
15年間、東京、シンガポール、ロンドンの投資会社、証券会社に勤務。KPMGヘルスケアジャパンで経営コンサルタント。
法務大臣小川敏夫の大臣秘書官を務める。
法政大学兼任講師、青山学院大学非常勤講師、目白大学准教授、神田外語大学特任教授を歴任。専門は、経済・経営。
甲状腺がんを克服。
2021年10月、衆議院議員選挙で初当選。2024年9月、立憲民主党代表選挙に挑戦。同年10月、再選を果たし、現在2期目。2025年9月、立憲民主党代表代行に就任。
特集/2025年11月・秋
- 高市・延命自民党よりも野党に課題本誌代表編集委員・住沢 博紀
- 立憲民主党は自民・維新の高市新連立政権にどう立ち向かうのか立憲民主党代表代行・吉田 はるみ
- MAGA的ポピュリズムが蔓延する世界の行方神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- トランプのスロークーデター第2幕国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ヨーロッパにおけるポピュリズムの進展を読む龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- 不公平感に揺れるドイツ社会在ベルリン・福澤 啓臣
- 見えない左、右への落石は山体崩壊の兆か大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 今こそ、まっとうな日本の気候政策を創ろう京都大学名誉教授・松下 和夫
- 洗練された全体主義の行方労働運動アナリスト・早川 行雄
- 最低賃金発効日の繰下げは許さない!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆
