連載●池明観日記─第29回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫金敬先生へ≪
日本の堀真清教授が、私が書くこの随想録を日本でも出版してみてはといわれたので、その閒今までの分も翻訳して日本に送るために、だいぶ長いこと本文を書き進めることができなかった。これは私の最後の本として満90歳になる日に最後の文章をかくことにしてはどうだろうかと思っている。この頃は本をあまり読んでくれない時代であるから、自費出版にして数百部を出して、友人たちの間で私の遺書として読んでもらえることができればと思っている。

ほんとうに長いこと頭にあったが、このころとても強く考えるようになった問題が一つある。韓国教会の説教において見られることであるが、アメリカにおける韓国人教会の若い牧会者たちの場合においてもそうである。説教の時になぜ「私」と「皆さん」というように説教者と聴衆を区切って語るのであろうか。私と皆さんを一つにして「われわれは」ということができないのであろうか。「私は牧会者」「私は羊飼い」「私は主の僕」であり皆さんは羊の群れとして私に無条件に従わなければならないというのであろうか。どうしても皆さんも一つにして「われわれ」とはいえないのであろうか。いつからこのような言葉遣いが定着したのだろうか。私は主の御ことばを代言する者であり、あなたたちはこのことばに服従しなければならないということなのであろうか。ここにも韓国教会の伝統的傾向、その歴史がしみこんでいるであろう。
啓蒙時代に私に従えと言った先覚者たちの姿勢から来たものであろうか。またはアメリカ宣教師たちが聴衆である韓国人たちと自分をいっしょにしてわれわれというのは難しくてそのような言葉遣いになったのだろうか。このようなことに対してなぜ神学校などで説教学的検討をしていないのだろうか。これは説教において私は聖なる人、あなたたちは俗世界のなかにいる者というように聞こえてくる。それは何よりも現代的な用語としては伝わってこない。われわれ皆が罪びとであり、主につき従うといいながら迷っているというようには響いてこない。われわれ皆が同じような人間性を抱えて悩んでいるとは聞こえてこないのだ。そのような言葉遣いであれば説教内容にも関係するのではなかろうかと思われる。神のみことばの前で苦悩する説教者の姿というのはそこにおいては見出し得ないであろう。
この頃日本から送られてくる『福音と世界』(2014年2月号)に去る12月25日クリスマスの日の朝、元社長秋山憲兄先生が亡くなったという知らせがのっていた。96 歳で車椅子に乗っていらしたが、なくなるまで新約聖書ギリシャ語の辞典のような企画に手をつけていらっしゃったということであった。秋山先生は私の一生に対して決定的な関係を持っている方である。1964 年の春であっただろうか。たぶん彼が『福音と世界』の前身『基督教文化』の編集長をされていた頃ではなかったかと思われる。日韓に国交がまだ正式に開かれていないころ、ソウルに来られて、私を呼んでくださった。私はちょうど『思想界』社に就任した頃であった。これがやがて1965年12月に私が初めて日本に行って信濃町教会において森岡巌と出会い新教出版社はもちろんのこと、日本のキリスト教界が韓国の民主化運動を積極的に支援する契機となった。その後岩波書店の『世界』の編集長安江良介との関係へと続き15年間私が『韓国からの通信』を書くことへと発展して行った。日本の教会は世界教会と韓国教会の間で韓国教会の民主化闘争を日本の社会はもちろん世界の教会と世論に仲介する役割をなしたのであった。それはわれわれの考えを超える神の理摂であったというべきではないかと思われる。1972年に私が日本に行くようになるのは東京大学の隅谷三喜男の仲介的役割によったものであるが、それも新教出版社の仲介によって可能になったのであった。
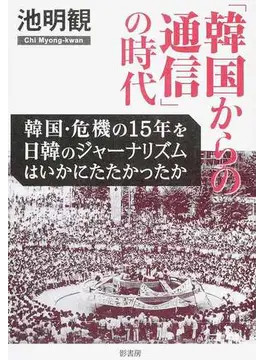
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
そのすべてのことに先き立つ話であるが、1965 年に日本に行くようになる数年前、軍事政権が始まったばかりの暗い時代に、新教出版社に日韓出版会の交流のために私が手紙を出したことがあった。どういうつもりでそのような書信を出したのかは記憶ははっきりしないが、その時私は日韓関係は必ず両国キリスト教の間でまず開かれなければならないと思ったのであろう。新教出版社からは書信に対する返事はなしに『基督教文化』を一冊送ってきた。そのことを新教出版社でも記憶していたかどうかは確かめあう機会がなかった。秋山はそれを心にとめていて訪韓となると私に会われたのかもしれない。
秋山氏の逝去とともに今は私自身の最後のことを考えながらいろいろと整理をしなければならないのにと思うようになる。歴史の中ですべてが永遠なる忘却へと消えていくのであるが、誰かの心に何かを残して行く。ハンナ・アレントが人々が取り交わすことばと交わりに限りなき価値を認めたように。
金敬につぎのような文章をEメールで送った。このこともこの時点における忘れられないこととしてここに記しておきたいと思う。
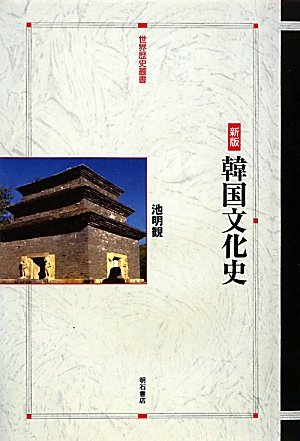
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
金敬先生
お便りありがとうございました。私も健康上、あちらこちら不便なところが少なくありません。老いをいかに生きるかは大きな問題のように思います。今年中に随想録は終わりにしたいと思います。
わが国の問題に対しても私は長いこと北東アジアの枠で考えなければならないと考えてきました。そこにはEUの問題が参考になるという考えでです。近代以降われわれ日中韓のあいだで韓国が平和的役割をなさなければならないといってきました。韓末から3・1運動に至るまでわれわれの先達たちが唱えてきた「東洋平和」ということの思想史的な意味とか役割をよく吟味してみなければならないと考えます。その一方で、韓国の政治勢力がそのような役割をなして行くことがいかに困難であるかと思いながら、私は常に 40年以上ヨーロッパ統合のために努力してきたEUの場合を考えてきました。そして、そこに参加してきた知識人たちの役割も考えたのでした。その動きを当事国らはもちろんのことアメリカなど世界が平和のための動きとして認めたわけではありませんか。韓国が北東アジアでそのような歴史的な役割を果たすことができるほど成熟してくれればと望んでいます。地政学的に見てもそうではありませんか。そのことのためには政府よりも国民が先に立たねばならないのですが。まずその始まりに教会とか宗教勢力が立ちえないものかと夢見たのですが、そのためには今が適切な時期でなかろうかと思うのです。ヨーロッパの場合は1952年の欧州石炭鋼共同体の時から統合の動きが活発になったのではないかと思っています。
昨日こちらのデパートを見て回りました。衣服は中国製のものが圧倒的に多かったのです。国際関係を政治的葛藤の面からのみながめるのではなく、このような経済関係または人間関係における可能性を見てそこに出発点を見い出すのがリアリスティックなことだろうと思います。民間研究所のようなところでイニシアティブをとるのもいいでしょう。行動を導き出すためには否定的な面よりも肯定的な面を見て楽観的にならねばならないのではないのでしょうか。私はアメリカはこのような可能性を許容しうる国だと考えます。もちろん現実的にはそのような大国らが諒解してくれることが出発点とならねばならないでしょう。
私はアメリカやヨーロッパがヨーロッパの平和のつぎにはアジアの平和、特に北東アジアの平和を模索し、そのつぎには中南米、そしてアフリカへ、東南アジアへと世界平和構想を広めていくという、楽観的な歴史を描いているのではなかろうかと思っています。日本の2020年度オリンピックは日本が極右路線へと向かう今の政治動向を牽制するようにならざるをえないでしょう。それに2018年度の韓国の平昌冬季オリンピックもあるではありませんか。このすべては北東アジアの平和のためにわれわれに与えられた機会ではないでしょうか。そのためにもわれわれは日本における朝日、毎日のような良識のあるメディアを決して軽視してはならないと思います。そのような方向のための日韓知識人たちの交流がとても重要でしょう。その頃にでもなれば現在の日本の極右の政治など過ぎ去ってしまうのではないのでしょうか。
私はこのような肯定的な世界政策を提示しえない韓国の政治または知識人勢力が口惜しいと思いながら、私自身も恥じ入る思いです。私が多少活動しえた時代にはせいぜいが日韓関係の門戸を開くという程度のことでした。振り返って見ますと、すべてのことがそのような限界にとらわれているのではないでしょうか。個人の考えが力を発揮できるとすれば、その背後にはそれを可能にしてくれる機関とか勢力がなければならないのではありませんか。その意味では韓国の場合も今までその機会を逸してきたといわざるをえません。これからよき動きが現れ、歴史的な役割を果たしてくれるようにと祈っています。ひとの国と他人に期待するよりはわれわれが何をなしうることかと考えるのが重要だといえましょう。このころは最近書いた文章を日本語に移すことに日々を費やしています。こちらは過ごしやすい天気です。今日はこれで失礼いたします。(2014年1月21日)
実際このような枠組みで韓国の南の知識人たちが政治を超え、今までの南北関係を超えて北の方にアピールをしなければならないと考える。南北問題においても政治権力者は南北ともども責任を強く感じなければなるまい。このような立場からこちらにいる李昇方(イ・スンマン)牧師とも一度話しあいたいと思っている。
何か月かかったのであろうか、やっと日本語訳の『金瓶梅』を読み終えることが出来た。明の時代16世紀末から17 世紀の初めに至る間に書かれた通俗小説であるといわれるが、この頃すでに中国人はこのような長編を編み出したのであった。わが国の『春香伝』はその後250年たってようやく現れたといわねばならない。
『金瓶梅』は大作で、中国人の長い息遣いを感じざるをえなかった。非儒教的であり非倫理的で土俗的仏教の雰囲気が底を流れていると感じられた。女性の貞操という面から見ただけでもこれほど奔放であるというのは驚きである。韓国特に朝鮮朝の儒教的な社会に比べて中国も日本も庶民の倫理においては、特に性的な面において実に奔放であったといえるのではなかろうか。このような見地から東アジア三国の文学を比較して見ればと思った。それはこの三国の伝統社会を比較して理解することとなるであろう。
中国の社会がもっとも倫理的に自由であって朝鮮においてそのように朱子学的牽制が支配することがなかったといえるであろう。朝鮮朝は道徳的統制でその長い王朝を支えてきた。日本では武士社会の統制で強い社会的紀綱を保ってきたのであるが、町人の遊びの文化において見られるように一種の息抜きの余裕が与えられていたのであった。『金瓶梅』においても結末を仏教的に閉じようとしたことは、彼らにおいては因果応報というものがもっとも重要な宗教性であったことを意味したからであろう。生と死、そのような人生を解釈して説明するのには仏教以外の道がなかったのではなかろうか。『春香伝』はこれに比べると朝鮮朝における儒教的倫理を強く押し出したのであった。日中韓の比較思想として比較文化的な研究が求められる。『金瓶梅』においては中国のその華麗な日常生活の中で月娘の倫理性のみがはっきりと提示されたといおうか。(2014年1月22日)
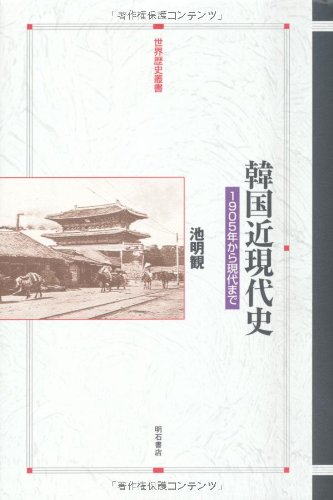
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
日本の東京都の知事選挙では執権党の自民党系の人物が圧勝したと伝えられる。ニューヨークタイムズの報道である。東京都知事の保守系の時代があまりにも長く続くような気がする。日本の政治全体の保守系の時代が長々と続く。韓国でも朴正煕系、慶北保守反動の時代が続いているのであるが。北東アジアでは特に中国が日本に対して批判を加える時代が長く続き、韓国の場合も日本との関係の正常化はたやすく到来するとは思われない。日中韓の間には島々を中心とした領土問題がからんでいる。中国は韓国における北の問題もあって北東アジアの平和の方向へとたやすく動くとは思えない。中国は徹底した自国中心主義をもってどのように世界をリードして行くというのであろうか。韓国も終戦以後の歴史において自国主義の枠を超えて北東アジアという発想の軸を示したことがないのではないか。そのような発想など考えることができなかったといえよう。そういう中で2018年の平昌冬季オリンピック、まして特に2020年の東京オリンピックにどのように対応しようというのであろうか。私はアメリカが北東アジアの平和という絵を描きながら東京オリンピックも平昌冬季オリンピックも押し出すだろうと思っているのだが。
日本は危機が来れば引っ込みがちであるという伝統的姿勢をたやすく抜け出すことができないであろう。韓国の場合は危機が来ればそれを克服して行こうとすると思ったのであるが、この前の選挙では朴槿恵を選択するのをためらわなかったことで、今までの行動方式を変更するようになったかと思わざるをえなかった。何よりも野党が執権して見せた政治に失望したからだと思った。しかしまた春となれば、騒々しくなるかもしれないという思いを打ち消すことができないでいる。朴槿恵は国民の統合を志向するのではなく、朴正煕時代の保守反動勢力が勝利したことにして、国民分裂の時代をまた引きずっていこうとするであろう。数年後、このつぎには国民統合のリーダーシップを築き上げてその影響が北にまで及ぶようになることを願っている。北に対する新しいレトリックで国民の間における良心的な勢力が新たにこの国が進むべき道を提示することができればと思っている。北は今も時代錯誤的に反対派と決めつけてはそれを急襲して処刑する。その処置においては封建時代の三族を滅するという古代史そのもののおぞましさを見せつけているではないか。中国はそれに向けてどう対応すべきか迷っているのであろう。
国民が南北に別れている両親と再会してともに暮らしたいという素朴な人間的な願いが南北の政治によって遮られているという現実ではないか。一体自分の父母にあいたいという時にそれに銃撃を浴びせる国家がこの地上のどこにまたあるというのであろうか。そのような事件が実に深刻な問題を、今やほとんど無感覚になっているわれわれの目先につきつけている。すでにそのような牢屋のような国において両親はほとんど先に逝ってしまったという現実ではないか。ほんとうに残忍な政治暴力であるといわなければなるまい。家族が再統合したいというのに、政治権力がいかなる名目でそれを遮るというのであろうか。人権の上に政治権力が君臨しているではないか。私は敵をも愛しなさいという御ことばをこの異国の空の下でわびしく口ずさんでいる。(2014年2月10日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
