特集
政党政治のグローバルな危機の時代
深掘り対談 ―― 石破少数与党政権と立憲民主党などの野党は、国民の不安にどこまで答えられるか
深掘り対談 ―― 石破少数与党政権と立憲民主党などの野党は、国民の不安にどこまで答えられるか
法政大教授 山口 二郎
中央大教授 中北 浩爾
聞き手 住沢 博紀(本誌代表編集委員、日本女子大名誉教授)
1.安倍政治を生みだした諸条件の消滅と2025年の日本政治の枠組み
2.中道保守とナショナル・ポピュリズムの結合の危険性
3.政党の新しいリーダー選出とその効果は?
4.2024年衆議院選挙:「政治とカネ」だけではない投票行動の変化
5.新聞・テレビ世代とSNSの若い世代との政党選択の背景の違い
6.少数与党政権のもとで新しい政策論争や政権構想は生まれるか
1.安倍政治を生みだした諸条件の消滅と2025年の日本政治の枠組み
住沢 2022年7月、参議院選挙中に安倍元首相襲撃事件があり、その後、自民党と統一教会の癒着問題につながり、さらには自民党政治資金パーティの裏金問題が発覚し、2024年の選挙の年になるわけです。石破政権の成立と衆議院選挙での自公敗北により、安倍長期政権の後、日本政治も流動期に入りました。2024年は世界的な選挙の年で、トランプ大統領選出をはじめ、G7諸国はどの国でも政権が不信任を突き付けられ、これまでの左右の中道派による国民的合意に立つ議会政治が危機に陥っています。
こうした世界的な動向を踏まえたうえで、日本政治のこの3年間ほどの動向、さらにはその到達点についてお話しください。

山口 多くの人が政党政治の危機といっていますが、私も非常に深刻な危機だと思っています。こういう世界的な政治の混乱が同時に進行しているというのは初めて見る状況だろうと思います。まず日本の国内政治から見ていくと、今年は戦後80年という1つの節目ですが、いろんな意味で戦後政治が終わったと思っています。
それは、リベラル側から見れば、戦争の経験、記憶を土台にした戦後デモクラシーとか戦後平和国家という路線が、どんどん訴求力を失っていく、国民的な共有財産ではなくなっていくということ。他方で、戦後システムなるものに、大変な敵愾心を持ってこれを転換しようと図ってきた安倍晋三という人が、長期政権を実現したものの、戦後レジームを主体的、能動的に転換するということはできなかった。そうこうしているうちに暗殺され、その暗殺の理由というのは、旧統一協会の、ある種の被害者の怨恨に基づく犯行であった。
暗殺自体は民主政治を破壊する犯罪ですが、冷戦的な反共主義に安倍がどっぷり浸っていたことが、ある意味で招いた結果であったという面もあるわけですね。だからこう、戦後を固守しようとしたリベラル側、革新側も、どんどん地盤沈下していくけども、これを躍起になってというか、むきになって壊そうとした保守というか、右派の側も1人相撲を取っているうちに自滅していった。で、残っているのは、本当に混沌とした状況という感じがするわけですね。
だから私自身は第2次安倍政権のもとで、安保法制反対運動から始まって、野党共闘の運動をしてきたのですけども、これも安倍という人がいたからできた話であり、その安倍的な、戦後への攻撃に対して、戦後の進歩派、左派を束ねてなんとか戦後を守るみたいな運動でした。安倍なき今、あるいは安倍派の独善的政治が自壊した今、野党協力ももう歴史的な意味は失ったんじゃないか。そういう意味で私は最近、野党共闘にもだいぶ冷ややかになってしまったという状況ですね。
住沢 中北さんはやはり政党政治史というアプローチで、自民党、公明党、共産党、それに民主党から立憲民主党への変遷まで、日本の現代政治を研究され、さらにはメディアでも発言されてこられましたが、その分析枠組みそのものが、過去2年・3年間で変化したといえますか。

中北 まず国内の話から入ると、大きな枠組みが全て崩れているとまでは言えないと思うんですね。私はこれまで2つの議論をしてきました。
1つは政党ブロック間の力関係です。総体として言えば、自公ブロックは支持基盤が厚いし、結束力も強い。それに対して野党ブロックは両面において弱く、ブロックとしての体をなしていない。この状態が変わったのかというと、おそらく変わってないということだと思うんですね。野党がバラバラであるがゆえに、先の衆院選で自公が過半数を割ったにもかかわらず、今もなお自公政権が続いている。そればかりか、一部の野党が自公政権にすり寄ることで影響力を行使し、政策を実現しようとしています。
もう1つの議論は、自民党と公明党が持っていた固定票が、どんどん弱くなってきていて、野党の方もそうだけども、無党派層的な有権者が増えてきているということです。この傾向がSNSを媒介としてはっきりと出たのが、昨年だったというふうに思いますね。自公の過半数割れも、そうした中で生まれたといえるでしょう。日本政治全体が流動化してきていて、閾値を超えつつあるんじゃないかと思います。
加えて言えば、こうした傾向は戦後80年ということとかなり関係していると思います。一昨年、創価学会の池田大作氏が亡くなり、去年は読売新聞の渡辺恒雄氏が亡くなりました。いよいよ「戦後」が遠くなってしまいました。
実際、創価学会という巨大宗教団体も弱くなってきているし、読売をはじめ新聞の発行部数も激減している。社会が組織化された状況から、組織が弱くなった状況というのを象徴していると思います。日本の多くの社会団体は、終戦直後の時期に組織化されたものが多いと研究上、言われています。団塊の世代も後期高齢者になり、その耐用年数が切れてきているということでしょう。
そういう大きな見取り図とともに、もう一方で山口先生も強調されたような話というのがもう1つあって、安倍晋三氏が2012年に政権の座に復帰した後、「一強」と呼ばれるほどの強力なリーダーシップを行使しました。これがどんどん崩れてきているのが、今の局面です。「ポスト安倍」の流れは、最終的に石破さんという反安倍のリーダーが首相になるというところまで行き着いたわけです。
しかし、ポスト安倍のリーダーシップを構築できるかというと、全くそういうことになっていません。自民党についてもそうですが、野党の方もそれに代わるような権力を作れるかというと作れていなくて、全体として「権力の空白」、言い換えれば無秩序に近づいているといえます。現在、「無党派層の増大」と「権力の空白」が相まって、非常に混沌とした政治状況が生まれているというふうに思いますね。
2.中道保守とナショナル・ポピュリズムの結合の危険性
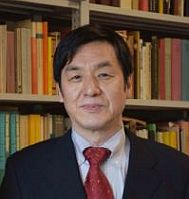
住沢 どうもありがとうございます。それでは次に、欧米の民主主義諸国、とりわけG7の諸国では、これまで比較的安定していたドイツも含めて、第二次大戦後の政党政治が、さらには政党システムそのものが不安定になっています。大統領制、議院内閣制など政党政治の制度的枠組みにより違いはありますが、おしなべて左右の中道政党による政権が、左右の「体制外」の新興勢力から大きな批判をあびて、国民を統合し統治する基盤が不安定になっています。トランプ選出に見られるように、共和党など伝統保守とナショナル・ポピュリズムが結びつけば、現在では多くの国でも多数派になります。EU諸国では、保守政党がグローバルな立憲主義を堅持し、右翼ポピュリズムと一線を画することが自由民主主義体制を維持する生命線となっています。
日本も昨年の衆議院選挙の結果、石破少数与党政権に至ったわけですが、こうしたグローバルな流れと日本政治の現段階との関連を見て取れるでしょうか。
山口 日本の場合、良くも悪しくも自民党という統治能力を持った圧倒的に巨大な政党が長年統治してきて、官僚機構も掌握している、それから社会的ないろんな団体もネットワーク化しているということで、この統治の安定性という点では日本は今の世界の中では非常に良好な状態。あんまり良好なんて言いたくないですけど、他と比べれば、政治の安定度は高いことは確かですね。
他方で、アメリカとか西ヨーロッパの場合は、日本人にはわからない移民問題の深刻さというのが政治、社会を根底から変えてきているということは確かだろうと思います。日本は要するに人口減少を放っておいて、移民を入れないという政策で過去数十年やってきて、それは社会的、経済的活力を非常に低下させていくわけだけども、政治、社会の安定性という意味では、今のところはヨーロッパのような、非常に大きな対立とか分断とかを招かずに済んでいるということが言えるんでしょうね。
去年の都知事選とか兵庫県知事選あたりから急に注目を集めたSNSの影響の拡大、それからSNSを武器にした新興勢力が、中央レベルの政治に参入して大きな勢力になっていくのか、これは本当に大きな問いです。けれども今のところは衆議院選挙というのは参入障壁が高いですが、これも世代の入れ替わりがもっと進んで、10年ぐらいの単位で考えれば、本当に政党システムの構成が根本的に変わっていくということもありうるのかなというのが私の現状認識ですね。
住沢 わかりました。今その移民問題、日本の高齢社会化と人口減による成長の停滞という問題をいわば犠牲にした形で政治的安定が生まれているということで、後に議論したいと思います。中北さんに同じような問題でお願いします。
中北 私も山口先生とほぼ同じ認識です。この不安定化には、短期的要因と中長期的要因とがあって、短期的要因はインフレの問題ですね。庶民の生活への不満が、政権や与党に向かって、昨年かなりの数の政権交代が各国で起き、日本の場合、そこまでには至らなかったけれども、少数与党に陥りました。
中長期的要因についていえば、先ほども言及したように、社会の個人化とか脱組織化とかいう流れがあり、SNSで無党派層が動員されることで、不安定化に拍車がかかっている。ですから、インフレという短期的要因が解消されたとしても、中長期的には、こういう不安定な政治状況というのが恒常化していくんじゃないかなというふうに、私は見ています。ただ、山口先生もおっしゃったように、欧米諸国に比べると日本の変化は緩やかです。
世界的な流れで考えると、グローバル化とそのもとでの新自由主義という時代は、2010年代後半にほぼ終わったと思います。「アメリカ第一主義」のトランプ政権もそうですが、格差の拡大を受けて、それを是正すべく各国でポピュリスト政党が台頭していることは、そういうことでしょう。それが意味するところは、イギリスのEU離脱をはじめ、国民国家の復権ということなんじゃないかと思います。
日本でも、現在の経済政策は「賃上げ」に「経済安全保障」ですからね。しかし、行き過ぎたグローバル化と新自由主義を是正する主導権を社会民主主義勢力が担っているかといえば、そうではありません。むしろ右派ポピュリズムに押されている。
日本の場合、これまでもグローバル化と新自由主義は徹底した形で行われてきませんでした。移民も増えてはいるけれども、欧米に比べて人口比で考えると少ない。こういったことを背景に、日本では右派ポピュリズムの台頭があまりみられないなど、政治の変化がマイルドになっているんじゃないかなと思います。
3.政党の新しいリーダー選出とその影響は?
住沢 地政学の復権、中道政党も国家利益・国民の利益第一主義を掲げるなど、そうした国家、ナショナルな復権は確かに見られます。しかしEUやAPECなどのグローバルな地域主義と脱EUのイギリスを含め自由貿易圏の拡大の流れ(トランプ・アメリカを例外にして)、グローバル金融資本主義の継続はいうまでもなく、中国を含めてのグローバルなサプライチエーンの存在、GAFAMなどのグローバル企業による情報社会の発展、さらに移民・難民問題、地球環境問題、ウクライナ戦争とエネルギー資源高騰など、ナショナルで規制あるいは解決できる分野は少ないと思います。EU諸国での政権担当政党が、適切な解決策を国民に提示できず政権不信につながることもここに起因しているわけです。
日本でももちろんこうしたグローバルな課題に直面しているわけですが、日本の場合は、30年と続く閉塞状況を切り開く課題や政策は何なのか、という問題が先ずあります。昨年は多くの政党のリーダーが変わりましたので、ここから入っていきます。
石破自民党、野田立憲民主党、それから前原・吉村維新の会、玉木国民民主党、斉藤公明党、田村共産党、それぞれ指導者が変わったわけですけども、そのもとでの政党のイメージ、あるいは新しい可能性がみられるようでしたら、語っていただけますか。
山口 玉木国民民主は、去年の東京都知事選挙における石丸現象と同じような流れで、政治的なコミュニケーション手段をうまくイノベートして、特に若い世代に到達することに成功したという点で、小規模ながら成功した起業家みたいなイメージでしょうかね。だけど、この政党はもともと民主党にそのルーツを持ちながら、立憲民主党と対抗することに自らの存在理由を見出しているんで、政権交代を起こすことで日本の政党政治を転換していくという大きな役割を担うということはほとんど期待できない。その意味で誠に困った存在だなという風に見ていますね。
だから、例の年収の壁の問題にしても大事な問題提起ではあるし、それから、私たち民主党時代から応援をしてきた政治学者や大沢真理さんみたいな経済学者、社会保障学者は、ずっと前からもうこういう問題は指摘してきたわけです。要するに、働き方とか家族の構造が変わっている中で、税と社会保険の仕組みを刷新しなきゃいけないということはずっと言ってきて、それを民主党、それから立憲民主党が見落としてきたことが、今こういう形で現れてきている。
維新は、私はある意味賞味期限が来たのかなと思います。大都市、地方政府に巣食う既得権、利権の構造みたいなものを批判して、ある種の新鮮さをアピールしていたわけだけど、もうそれから10年経って維新自身がその既得権の中心にいて、かつ万博なんていうもう時代錯誤もいいところの開発を進めていく、カジノもそれからやるということで、維新の新しさというものはもうなくなったと思うし、前原さんがとりあえず国会での暫定的なリーダーになったということからしても、かつての90年代、2000年代の非自民政党の中の、右派プラス新自由主義みたいな感じの部分を継承するという形になっているのかなという印象で見ていますね。
公明党も、学会の高齢化、組織の老朽化みたいなものの中で、色々悩みは深いんだろうと思いますが、今の日本の政党なり、政党を支える組織の中では、圧倒的な実力をまだ持っていますから、公明党がある意味これからの政党政治の権力の軸というんですかね、権力の担い手をどういう風に作るかという点では、依然として鍵を握る勢力なのかなと思いますね。
伝統的な革新政党である共産党と社民党は、私はもう歴史的役割は終わったという風に見ていまして、党勢の回復はもう無理だと私は思っていますね。ああいうイデオロギーを軸にして組織を作っていくというやり方はもう無理だろうと思うし、特に共産党の去年の総選挙に対する総括を見ていると、もうなんかすごい時計の針を逆回しにしていると。非常に内向きな発想でやっているなという印象ですね。
住沢 中北さんお願いします。
中北 この前の総選挙では、数字を見てもそうですけど、中道化が進んだ一方で、断片化も進んでいるというのが全体の傾向なんだと思いますね。中道化というのは、先ほども言ったような「ポスト安倍」の動きを示していると思いますけど、断片化というのは、無党派層が増えただけじゃなくて、SNSを使って有権者を部分ごとに動員することが可能になったということですね。
そうした中で、山口先生が以前に指摘された専門店の強み、今回の国民民主党の玉木代表は「103万円の壁」に特化した政策アピールが成功しました。立憲民主党の野田代表も述べていますが、二大政党が総合デパートであるのに対して、ユニクロとかワークマンでもいいけど、専門店みたいな政党の方が明確なアピールをしやすくて、議席を伸ばした。こういう状況ですね。
二大政党はなかなか難しい立ち位置で、今回の衆院選ではれいわ新選組とか国民民主党とかが伸びて、断片化が進んでしまった。その背景には、既存の政治に対する不信がある。こうした政治状況は小選挙区比例代表並立制という衆議院の選挙制度とミスマッチを起こしているわけで、事態は深刻です。
4.2024年衆議院選挙:「政治とカネ」だけではない投票行動の変化
住沢 昨年の衆議院選挙では、自民党の裏金問題が鍵であったといわれています。しかしここでは二つのことに注目します。一つは若者世代の自民党離れです。朝日新聞の10月27日の比例区投票への出口調査では、18・19歳で26%(前回42%)、20代で20%(同40%)、30代で21%(同37%)と若い世代で大幅に減らしています。安倍政権の時代には、若者の雇用状態が改善されたので自民党が改革政党として若者世代に評価された、という説がありました。今回は、若者世代は玉木・国民の「103万円の壁の178万円への引き上げ、手取りを増やす」という目玉政策に引き寄せられたといわれています。とすると、その都度、もっとも自分たちの世代に響く政策で(あるいはそのような情報から)、政党選択を行っていることになります。
SNSがこうしたその都度の若者の投票行動の変化を増幅させている可能性があり、それが二つ目のテーマです。先ず最初の問題からお願いします。
山口 生活が厳しい。その生活の厳しさに対するその人々の意識、困窮しているという意識は、私たちのような年寄りには想像できないほど大きいんだろうなと思いますね。
20代、30代も給料がほとんど上がらない状態で過去10数年生きてきたし、福祉国家と言いながら、既存の社会保障政策の恩恵に全然浴していない。
児童手当は、党派を超えた合意政策となった。しかし、そもそも野田政権で税と社会保障の一体改革をするときに、全世代型の社会保障って一応言っていたんだけど、基本的には社会保障は高齢者中心というイメージは変わってない。まさに手取りというキーワードが非常にヒットしたのは、それだけ現役世代の生活が苦しいということの表れだろうと思います。
ただし、年収の壁というか、所得控除の問題だけ切り取って手取りを増やすってことをいっても、全体としては現役世代の豊かさを底上げするような政策には繋がらないということははっきりしているわけなんで、国民民主の一点突破型の政策提起というものの限界というのはいずれ見えてくると思うんですけれどね。
ただ、税金に対する不満というのが財務省に関する陰謀論みたいなものと繋がっていて、非常にタチの悪いポピュリズム、右左を問わない両翼のポピュリズムから出てくる。政策の合理性とか、責任感のある政策論議みたいなもの自体を否定するような風潮がこれからどんどん広がっていくということについては、困ったなという感じで見ています。
住沢 中北さんにお聞きしたいんですけが、自民党の金権政治に対する批判とかインフレに対する生活不安が、立憲民主や維新の会じゃなくて、むしろ国民民主の選択につながった背景はどのように考えればいいですか。
中北 これについては色々と調査がありますけど、以前からですが、若い人に国民民主党支持が多いんですね。その理由の1つは、SNSの影響なんでしょうが、もう1つは、今回、「103万円の壁」という若者向けの政策がうまくいった。それでバズったということなのでしょう。
若い頃、我々もそうでしたけど、社会保険とか税の恩恵ってほとんどないわけですよ。地方自治体といったって、ごみ収集ぐらいしか世話にならない。家庭を持って子どもが生まれれば、保育園に入るとか、医療費の補助とか、色々な支援を受けるけれども、若いうちって、税とか社会保険料とか取られるだけで、返ってくるという実感を持ちにくいというふうに思うんです。
さらに、これだけ高齢者が多くなって若者の数が減ってくると、先行きに対する不安が強まる。結局、自分たちが社会保険料や税金を払ったって、自分が高齢者になった頃には戻ってこないんじゃないか。学生などと話していても、こういう感覚が広がっていて、ならば税や社会保険料を減らしてもらって、自分でNISAを始めて貯めた方がいい。そういう発想になってくるということなんだと思うんですね。
社会的な連帯、世代間の連帯ですね、それがかなり失われてきている。どうやって連帯を取り戻すのか。実際、12月7-8日に行われたANNの世論調査では、年収の壁の引き上げと税収減について、手取りを増やすためにサービスの低下はやむを得ないという回答が、53%を占めているんです。
こういった若者の声をどうやって汲み上げるのか。それが問われていると思います。国民民主党のやり方が正しいとは思わないんですけれども、これについての回答を立憲民主党は全く持ち合わせていないとみられているんじゃないかと思いますね。現役で働いている若者をどうやって連帯の中に引き戻していくのか。そのための提案が求められていると思うところですね。
5.新聞・テレビ世代とSNSの若い世代との政党選択の背景の違い
住沢 現在すでにメディア利用と世論形成に関して世代的な分断がありますが、これからどんどん新聞、テレビなどの伝統的なメディアが衰退し、編集されない多様な情報が氾濫する時代になるわけです。近代に新聞が作り出した議論する公衆、あるいはテレビの公共的役割など公共性が後退し、私的関心やアルゴリズムによるランク付けが判断基準になるわけです。この情報社会の政治に与える影響、とりわけ議会制民主主義にたつ政党政治に与える影響に関して論じてください。
山口 これはね、私なんかに聞かれてももう答えはないわけですよ。公共性という言葉が出たけど、まさに公共的空間がもう崩壊してきているわけですよね。私はよく自虐的にこういう例え話を言っているのですが、SNSはじめとするそのIT革命というのは、グーテンベルクの印刷術以来のメディアの大変化をもたらしている。500年単位の変化だと思いますね。
グーテンベルクの時代は、印刷術で本、活字を大量生産で広めることが始まった。で、ルターの宗教改革とうまくシンクロナイズして、西ヨーロッパの精神的な世界を大きく変えることに繋がっていったわけです。しかしルターの時代は、万人祭司主義とは言いながら、まだ神様がいたわけで、人々は神様と向き合いながら自分の行動を律していたわけですよね。活字メディアというのは啓蒙という作業とも相性が良かった。
ところが今のSNSというのは、神のいない時代の万人祭司主義を作ったわけですね。もう権威なんてどこにもないから、啓蒙という作用そのものも否定されている。みんなが好き勝手に教祖になって、いろんなことを無責任に言っている。またそれを受け取る人たちがいるという状況ですね。そういう状況の中で、ファクトチェックをするとかね、論理的な思考を重んじると言うと、それ自体がすごく権威主義的に響いてしまうという状況なんでしょうね。だから、私なんかは長年プロテスタントのリーダーのつもりで権力を批判してきたけど、今やルターの時代のカトリックのお坊さんみたいなもんで、伝統的なメディアでものを言うということ自体がもう権威主義的で上から目線でというふうに受け取られる時代です。
だから、SNSの時代でも、どういう形で啓蒙を成立させるか、つまり責任感のある政策論を議論できるかというのは困難な問いです。ファクトとか論理を無視したら政策は絶対失敗するので、そういう真面目な議論の必要性は全然減ってないんですけど、SNSの時代にそういう真面目な議論をするオピニオンリーダーとはどういう人たちかというのも、これは今の若い人の中で出てくるのを期待するしかないと思いますね。
住沢 深刻な問題ですね。中北さん、どうですか。
中北 山口先生がグーテンベルから近代の話をされましたが、もう少しレンジを短く捉えると、そこまで悲観する必要があるのかなと思います。
例えば、戦間期のヨーロッパでは、ドイツなどで民主政の崩壊が起きました。当時は部分社会に立脚する組織政党の全盛期でした。例えばドイツだったら、労働者階級の社民党があって、カトリックの中央党があって、さらにナチズムが台頭してというように、政党が拠って立つ部分社会が相互に敵対的で、社会全体として分極化している。こういう状況がありました。
ところが、第二次世界大戦後、組織政党や部分社会を前提としつつも、エリート間で協調することによって安定的な中道支配が成立しました。新聞とか活版印刷術の時代に、常に公共空間というのが幅広くできていたとは言い難い。そうしたマスメディアは、部分社会を強化する方向にも機能し得た。こういう歴史的展開をみると、やがてはどこか落ち着きどころを見出すんじゃないかという気がしています。
そう考えた時に、SNSっていったって、一般市民が勝手にやっているわけじゃなくて、当然YouTubeとかXとか様々なプラットフォームを使っているわけです。プラットフォーム企業に規制をかけたり、運用の改善を求めたりしていくことが、第一歩になるんじゃないかと思います。まだまだ改善の余地があるから、あまり悲観していません。当面は色々な議論がなされないといけないし、混乱も生じるんじゃないかということは確かでしょうが。
6.少数与党政権のもとで新しい政策論争や政権構想は生まれるか
住沢 石破政権の少数与党内閣のもとでの通常国会が間もなく開かれますが、野党側のいくつかの要求項目を挙げておきました。予算審議を出発点として、7月参議院選挙に向けいくつかの論争的な政策をめぐり与野党、また野党同士での駆け引きが始まるわけです。立憲民主党でいえば、企業団体献金禁止を軸とする政治とカネの問題、選択的夫婦別姓、それに103万円の壁から106万円の社会保険の壁がテーマになりますが、この展開をいかに見ていますか。少数与党政権のもとで、新しい政策論争や政権構想が生まれますか。
山口 正直、私はあんまり展望がないですね、本来は国民民主の問題提起を引き取って、やはり雇用形態とか正規、非正規とか性別とか関係なしに、個人を単位とする税と社会保障制度のパッケージってものを打ち出していくのが立憲民主党の任務です。それでかつて民主党時代に言ったように、基礎年金についてはもう税金できちっと保障していく。あと弱者対策は給付できっちりやってくみたいな、そういう政策体系を打ち出すべきタイミングなんだけども、立憲民主党の人たちを始め野党が何をやっているか全然見えてこないわけですね。
選択的夫婦別姓も、それはやればそれに越したことはないけど、これは別に政権をひっくり返すようなテーマじゃないわけです。今までよりも連立政権の枠組みを作るという作業は非常に難しくなってきている。2009年の民主党政権を作った時とは全然状況は違う。あの時よりも本当複雑になってきているのは確かですが、そうは言っても、軸になるべき立憲民主党がもうちょっときちんとした骨組みを作っていかないと。
2009年に向けたマニフェスト、あれと同じものを作れとは言いませんが、基本的な柱を3本、4本立てて、ここはこういう風に変えてくみたいな政権ビジョンというものを作らないことには、連立政権の議論も進まないですよね。そこのところを今、野田さんたちがどう考えているのかというのが見えてこないんですよね。
住沢 確かに立憲民主党の様々な文書など見てもですね、山口さんがいわれたような包括的な社会保障改革の案をもってはいるのですが、それを前面に押し出していませんね。この自公政権からの基本政策の転換の主張が弱い感じがしますが、中北さんはどうですか。
中北 山口先生と全く同意見です。立憲民主党は、この前の衆院選で「政権交代こそが最大の政治改革」というキャッチフレーズを掲げて、野田代表を先頭に戦いました。したがって、衆院選後には政権交代に向けて色々な手を着々と打っていくと期待してみていましたが、残念ながら止まっているようにしかみえません。国民民主党が積極的に手を繰り出しているのに、立憲民主党は受け身の対応しかできてない。
政権交代を最大の目標として掲げているのだから、立憲民主党がやるべきことはシンプルです。1つは外交・安全保障政策の現実化。これをやらないともう政権担当の資格なしと、有権者は思っています。国民民主党との政策協議が行われようとしていますが、両党間の距離を縮めていく上でも、非常に重要です。これやらない限りは、スタートラインに立てないでしょう。
もう1つは、山口先生もおっしゃったように、分かりやすい3つぐらいの目玉政策をきちんと打ち出していくことです。2009年の政権交代前の民主党は、子ども手当をはじめ、高速道路無償化、ガソリン税の暫定税率の廃止、高校授業料の無償化などを主張していましたが、それに匹敵するような政策ということです。
住沢 山口さんも中北さんも立憲民主党の幾人かの政治家には、政策提言やレクチュアーもしており、内部事情もよくわかると思うのですが、どうしてこうした提起ができないのですか。
中北 論議してないんじゃないかな。
山口 野田さんという人は政策、どういう社会を作るかみたいな関心があんまない人なんでしょうね、
中北 政調会長は長妻さんから重徳さんに代わりましたが、期待したいところです。こういう点では国民民主党の方が、貪欲です。「103万円の壁」に続いて、就職氷河期世代対策を次の目玉政策として打ち出そうとしている。政策の内容もターゲットも非常に明確で分かりやすい。立憲民主党は、国民民主党に比べて活力が乏しいような印象で残念です。チャレンジャーとして失敗を恐れず、どんどん前に進んでもらいたいですよね。
山口 これ、受け身というかね、なんか主体的になんかやろうという姿勢が見えてこないのが1番なんか情けないところです。
住沢 それは、どういう理由があるのですか。お2人の分析では。
中北 2020年の合流以降、図体だけでかくなって活力がないんでしょう。
住沢 立憲民主は重点課題の一つとして女性議員を多くしていることがありますが、それは看板にはならないですか。
山口 例えば、個々に話すとそりゃ優秀な人もいるとは思うんだけど、なんだろうな、2009年と比べると、党のトップレベルの指導者において政権交代への意欲が全然違うと思います。
中北 女性に限らなくて、立憲民主党になって議員になった人々は、ジェンダーなど文化左翼的なアジェンダに関心が強いように感じます。野田代表はそうではないけれども、政治改革にフォーカスしようとしている。今国会でも、選択的夫婦別姓の実現や企業・団体献金の廃止が、立憲民主党の実現すべき課題の中心に据えられています。それはそれで重要なんですが、政権交代を目指すならば、やはり国民の生活に関わる経済政策や社会政策こそが前面に押し出されるべきですね。
山口 そう、「国民の生活が第一」を今こそもう1回掲げるべきなんですけどね。
中北 それがない。
住沢 アメリカで言われたリベラルの限界ってやつですね、要するに。
中北 同じような空気は感じますよね、そこにね。
住沢 あと東京一極集中とパラレルな過疎化する地方と地方再生の課題、それに先送りされている高齢社会と労働力不足から生じる移民労働者政策、これは間違いなく日本社会や政治の不安定要因になりますが、それに耐えるオープンな社会や人々の普遍的な権利を擁護する政治をいかに作り出していくか、という課題が残されていますが、今回はここまでの議論とします。
やまぐち・じろう
1958年岡山市生まれ。81年東京大学法学部卒業、同年東京大学法学部助手。84年北海道大学法学部助教授・教授を経て2014年より法政大学法学部教授。専門は、行政学・政治学。著書に、『政治改革』(1993年岩波新書)、『日本政治の課題』(97年岩波新書)、『イギリスの政治 日本の政治』(98年ちくま新書)、『戦後政治の崩壊』(2004年岩波新書)、『内閣制度』(07年東京大学出版会)、『政権交代論』(09年岩波新書)、『政権交代とは何だったのか』(12年岩波新書)、『資本主義と民主主義の終焉』(2019年4月祥伝社、水野和夫との共著)、『民主主義は終わるのか―瀬戸際に立つ日本』(2019年10月岩波新書)、『民主主義へのオデッセイ』(2023年12月岩波書店)、近刊に『日本はどこで道を誤ったのか』(インターナショナル新書)、など多数。
なかきた・こうじ
三重県生まれ、大分県育ち。1991年、東京大学法学部卒業。1995年、東京大学大学院法学政治学研究科中途退学。博士(法学)。大阪市立大学助教授、立教大学教授、ハーバード大学客員研究員、一橋大学教授などを経て、2023年より現職。専門は、日本政治史、現代日本政治論。近著に、『自民党―「一強」の実像』中公新書、2017年、『自公政権とは何か』ちくま新書、2019年、『日本共産党』中公新書、2022年など。
すみざわ・ひろき
1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、フランクフルト大学で博士号取得。日本女子大学教授を経て名誉教授。本誌代表編集委員。専攻は社会民主主義論、地域政党論、生活公共論。主な著作に『グローバル化と政治のイノベーション』(編著、ミネルヴァ書房、2003)、『組合―その力を地域社会の資源へ』(編著、イマジン出版 2013年)など。
特集/混迷の世界をどう視る
- 政党政治のグローバルな危機の時代法政大教授・山口 二郎×中央大教授・中北 浩爾
- 日本は知識経済化ーイノベーティブ福祉国家へ慶応大学名誉教授・金子 勝
- トランプ2.0、パワーアップの秘密を暴く神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 立憲民主党は政権運営の準備を急げジャーナリスト・尾中 香尚里
- どこへ行くか 2025年のヨーロッパ龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- ショルツ政権の崩壊とポピュリズム下の総選挙在ベルリン・福澤 啓臣
- 追加発信韓国の「12・3戒厳」は、違憲で違法の内乱聖公会大学研究教授・李昤京
- 創造的知性の復権労働運動アナリスト・早川 行雄
- 時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労働基準法体系の解体を許すな!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆
- 『現代の理論』とアリスセンター近畿大学経営学部教授・吉田 忠彦
- 追加発信時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
