論壇
地域国際機構という存在
『人権保障と地域国際機構 ―アフリカ連合の役割と可能性― 』を上梓
して想う
富山大学学術研究部教育学系講師 五十嵐 美華
制度化の進む国際社会
2023年2月に、株式会社晃洋書房様より『人権保障と地域国際機構―アフリカ連合の役割と可能性―』を出版させていただいた。本稿では、これを執筆するに至った問題意識とその内容について、簡単に述べさせていただこうと思う。
国際社会は、制度化されつつある。19世紀初頭までの自然発生的なコミュニケーションと主権国家間の勢力均衡を基盤とした国際社会(René-Jean Dupuyのいう関係的社会)から、産業革命や第一次および第二次世界大戦を経て、さらには科学・技術の進歩とそれにより引き起こされた地球規模の問題へ協力して対処する必要性から、次第に制度化された社会の側面を増しつつある。つまり、国際社会における行動者注1である国家は、体系的かつ安定的な制度を形成し、共同利益を達成しようと協働する仕組みを形成してきた。
国際社会の制度化が進む一方、各国家は、それぞれ異なる背景を持つ。例えば、本書で扱うアフリカ地域の国家については、植民地支配の影響から、国際的な制度形成の初期段階からではなく、形成過程の途中またはある程度確立されたのちに関与することが多かった行動者とも言える。さらに、後述のように、アフリカ地域は「人権の尊重」に関しても、西欧文化圏発祥の普遍的とされる人権概念とは異なる価値を持つことも特色として挙げられる。
それにもかかわらず、アフリカの多くの国家や地域は、共同利益を認識し、国際的な制度に参加し、他の行動者と協働していくという選択をとる場面が多い。実際、アフリカ連合(AU)の「アフリカ連合設立規約」や「人及び人民の権利に関するアフリカ憲章」(バンジュール憲章)では、国連憲章や世界人権宣言について言及され、国際協力を促進することが述べられている。このような文脈において、AUが国際的なシンボル・システム(後述)とも言える国連憲章や世界人権宣言を尊重することは、どのような意味を持つのかという問いが生じる。AUは、国際社会の制度化にいかに貢献するのか、あるいは貢献しないのか。さらに、そのような国際社会において、AUはいかに自己の主張を現実のものとしていくのか。こうした問題意識から、本書に関する研究を進めることとなった。
(注1) 本稿における行動者は、主として国境を超えたレベルにおける行為者のことを指す。
共同利益の実現
ただし、研究を進めるにあたっては、もう少し国際社会の協働の基礎について踏み込む必要がある。すなわち、国際社会においてその実現を目指される共同利益および「人権の尊重」とはどのようなものか。また、それを担う行動者は誰か。
共同利益とは、ある国家にとっては直接的に自己の利益とは言えないが、それが社会の一般的な利益として認められ、その結果としてその利益が関連しない国家においても受け入れられるものである。このような共同利益は、個々の国益に優先されるべき性質を持つ。「人権の尊重」の重要性について、現代においては、それを表立って否定する国家は存在しないといえよう。つまり、「人権の尊重」は、国際社会において共同利益である。
そのような性格を持つ「人権の尊重」については、実現の仕方と、それを担う行動者の多様化が見られる。そもそも人権というのは、キリスト教社会の国際法秩序の中から生じたものである。イギリスの権利章典(1689年)、ヴァージニアの権利章典(1776年)、アメリカ独立宣言(1776年)、フランスの人及び市民の権利宣言(1789年)などがその先駆けである。このような社会的起源を持つ人権概念は、その後ヨーロッパ以外の他の国々に波及し、現在の国際社会では普遍的な価値として認められている。
しかしながら、「人権」という概念は、人間らしく生きることを保障するものである。何をもって人間らしく生きるかについては、文化的背景によって異なるため、「人権の尊重」の具体的な実現方法や解釈には違いが生じる。世界人権会議のアジアにおける準備会合で採択された1993年の「バンコク宣言」では、「アジア的人権論」が主張され、1981年に採択されたアフリカ統一機構(OAU)によるバンジュール憲章(後述)においても人権のアフリカ的な概念が反映されている。実際、国際社会においては、「人権の尊重」に加えて「多様性の確保」も重要性を認められつつあるといえよう。ウィーン宣言第5項では、人権の保護にあたり「国家的及び地域的独自性の意義、並びに多様な歴史的、文化的及び宗教的背景を考慮しなければならない」としており、人権の文化的な側面について触れている。また、2001年に採択されたユネスコの「文化的多様性に関する世界宣言」にも明示されるように、「多様性の確保」もその価値が認められつつある。
また、「人権の尊重」をめぐる国際制度の特性としては、現在に至るまで、国連を中心とする国際社会全体レベルだけでなく、地域レベルの人権保障体制が形成されてきたことがある。従来国内問題であるとされてきた人権の問題は、第二次世界大戦以降国際法上の重要な課題として浮上してきた。現代では、国連を中心とする国際社会全体レベルの人権保障体制から、欧州評議会による「人権及び基本的自由の保護のための条約」(欧州人権条約)や米州機構による「米州人権条約」、そしてバンジュール憲章などの地域レベルの人権保障体制が存在している。「人権の尊重」は、したがって、多様な行動者によって多元的に担われていることが認められる。
このように「人権の尊重」の実現を担う行動者が多岐にわたり、その価値も統一的でない国際社会では、「人権の尊重」という普遍的価値の受容や実現の仕方について行動者間で齟齬が生じる場合がある。
本書では、このような齟齬を軽減・回避するための試みの一つとして、地域国際機構による制度形成を捉える。なぜならば、地域国際機構は、以下のような機能を有する存在であるためである。
地域国際機構は、まず第一に、加盟国の利益実現を目的とする。加盟国は自国の国益追求のために地域国際機構を形成し、国家間での協力によってその達成を目指す。しかし、地域国際機構の機能はこれだけにとどまらない。第二に国連に代表される普遍的国際機構の役割を補完し、第三にグローバルな規範の形成と発展を促す。地域国際機構は、普遍的な国際機構が対応しきれない地域固有の問題について地域の実情に合わせて補完する。さらに、域内で妥当する規範を提示することにより、「人権の尊重」や安全保障、環境問題などグローバル・ガバナンスに関わる規範の発展を促すのである。
つまり、地域国際機構も国際社会という場に置かれ他者との相互連関の中で行動している。地域国際機構は、当初地域内の加盟国の集合的利益を追求するための組織として形成されるものの、域内の問題への対処における地理的境界線への固執が解決を困難にする場合があることを認識し、その結果として他の行動者や国際社会全体での連関の中で解決を図る。その意味で、地域国際機構は単に加盟国の集合的利益を追求するための組織にとどまらず、国際共同体(後述)の在り方や共同利益の達成に貢献する存在である。言うなれば、地域国際機構は、自然発生的に生ずる加盟国の利益追求を基盤とした「関係的社会」と「制度化された社会」の両側面を持つのである。
それを踏まえ、本書は、共同利益である「人権の尊重」における普遍性と「多様性の確保」が衝突する場面において、地域国際機構がいかに機能し、自己の利益を達成しつつ国際社会の共同利益を追求するのかを明らかにすることを目的とした。
行動を捉える枠組み
上記の目的を踏まえて、本書では、普遍的とされる価値が生じた欧米文化圏とは異なる価値や地域的事情を持つアフリカに焦点を当てた。それにより、普遍性と共に「多様性の確保」を中核とする人権制度ないしそのダイナミズムを分析することを試みた。
アフリカには、「人権の尊重」に関して独自の価値が存在するとされる。後述のサンゴールの主張に見られるように、アフリカの人々は個人と共同体を分けることなく人権観を形成してきた。またアフリカは、他の非欧米文化圏よりも「人権の尊重」における制度化が進んでいる地域である。AUはアフリカ独自の人権観を含むバンジュール憲章を採択しており、そこでは「人及び人民の権利に関するアフリカ委員会」の設置を定めるなど、「人権の尊重」を実現するためのメカニズムを形成している。この特異性と発展過程から、AUの「人権の尊重」に関する制度を、本書の事例として選んだ。
さらに、本書における主題である「人権の尊重」における普遍性と「多様性」の衝突に関しては、廣瀬の行動システム論(以下廣瀬理論)注2の適用が有用である。廣瀬理論は、行動者の行動を分析の出発点とし、行動者の個々の利害行動に基づく「利害システム」、行動者が置かれている全体の利益の視点から行動者に期待される役割期待行動に基づく「役割システム」、そして、伝統、道徳、規範などからなり、その二つを媒介する機能を持つ「シンボル・システム」の三つのシステムから法現象を説明しようとする社会学的枠組みである。この理論を用いることで、国際社会を共同利益を達成するための一つのシステム(=国際共同体)として捉え、行動者の相互連関を分析する。この理論を方法論として用いることにより、アフリカにおける「人権の尊重」のメカニズムがいかに形成され、また発展するのかという動的過程を分析することができるのである。
(注2) 廣瀬和子(1998)『国際法社会学の理論 複雑システムとしての国際関係』東京大学出版会ほか、廣瀬の著作を多数参考。
アフリカ連合にとっての「人権の尊重」
本書は、「人権の尊重」と「多様性の確保」を理念として持つ国際社会において、普遍的な価値の実現と地域特有の事情の両立がいかに志向され、その際に地域国際機構がどのような役割を果たしているのかをAUを事例に明らかにした。その道筋を概説する。
第1章では、「人権の尊重」を共同利益とする国際共同体について述べた。国際共同体における普遍的なシンボル・システムとしては、国際的な合意のもとで形成された法や、国際的な宣言が挙げられる。世界人権宣言など国際的なシンボル・システムに表される西欧文化圏発祥の人権概念が、個別の国家の利益の擁護ないし実現のためではなく、国際共同体全体の理念の実現のために文化的相違を問わず受け入れられている。
しかしながら、上述のバンコク宣言やバンジュール憲章、さらにはイスラム人権宣言(1981年)などが採択されていることからも明らかなように、「人権の尊重」については、その実現の仕方に「多様性」が現れる場合がある。つまり、現代国際共同体にける「人権の尊重」は、国際的なシンボル・システム、文化相対的なシンボル・システム、さらには両者の側面を持つシンボル・システムが存在し、それらが多層的・多元的に関わって、「人権の尊重」を共同利益とする行動主体に影響を与えているのである。
第2章では、パン・アフリカニズムの発展を通じて、AUやその前身であるアフリカ統一機構(OAU)が設立に至った経緯を探ることで、「人権の尊重」という共同利益の達成を目指す国際共同体の行動主体であることを明らかにした。
OAUおよびAUの設立に関する法的な枠組み、すなわちOAU憲章やAU設立規約の形成過程には、かかる地域社会を超えた国際共同体からの影響が多分に見て取れる。実際、シンボル・システムであるパン・アフリカニズムの発展過程においては、植民地主義に反対し、その被害を被ったアフリカ人民の人権保護とアフリカの解放を求めることのみならず、国際共同体から求められる他国に介入される存在という役割システムに否を唱え、アフリカの独立を確立することを目指すという利害システムが存在していた。その後パン・アフリカニズムという理念は、OAU憲章やAU設立規約に反映される形で発展していくことになるが、それはアフリカ諸国が独立と自決を求める過程で、国際共同体からの要求に直面したことに起因する。具体的には、アフリカ諸国は、国際共同体における「人権の尊重」に対してどのように対応すべきかという問題に取り組む中で、自らの立場を定義する必要に迫られた。OAU憲章では「人権の尊重」については十分に盛り込んでいなかったものの、アフリカ地域の人権保障体制について国際的な期待が高まるなかで、国際共同体からの要求に従い、バンジュール憲章を採択するなど徐々にその枠組みを修正していったのである。最終的に現在、AU設立規約では「人権の尊重」に関する規定が多く盛り込まれている。この変化は、OAUやAUが単に自己の利害を追求するだけでなく、国際共同体全体の共同利益を考慮し、その達成に貢献する必要があることを認識した過程、すなわち、OAU/AUが「人権の尊重」を内面化した過程であった。
上記を踏まえて、第3章では、OAU/AUがアフリカ地域内で国際的なシンボル・システムが広く受け入れられるための規範を提示する機能を持つことを明らかにした。
OAU/AUは、アフリカ諸国の統一を促進し、アフリカの価値や地域特有の事情に基づく自己主張を歴史的に試みてきた存在である。「人権の尊重」に関して言えば、アフリカには独自の人権概念が存在するとされる。例えば、セネガルの初代大統領であるレオポルド・セダール・サンゴール(Léopold Sédar Senghor)は、ヨーロッパ社会は個人の集まりであるのに対して、アフリカ社会は集団が個人に優越するものであり、個人の活動や必要性よりも連帯を重視する社会であるとする。この共同体主義がアフリカの本質であり、個別の人間の発展についても共同体は必要不可欠のものだとする。OAU/AUは、このアフリカ特有の人権概念を反映させたバンジュール憲章を採択した。しかし、重要なのは、バンジュール憲章がサンゴールが述べたようなアフリカ独自のシンボル・システムのみではなく、世界人権宣言や国際人権規約など、普遍的とされる国際的なシンボル・システムもが反映されているという点である。つまり、バンジュール憲章はアフリカの文化相対的な価値と国際的な人権規範が調和した結果である。
OAU/AUは、バンジュール憲章の採択によってアフリカの価値を包含した「人権の尊重」を主張している。これは、OAU/AUが地域内に妥当するシンボル・システムを新たに提示し、それに依拠することを選択してアフリカにおける「人権の尊重」を志向し、国際共同体の共同利益の達成を目指した過程であった。
アフリカ連合の主張と国際共同体
このように第3章まではOAU/AUが国際共同体から影響を与えられた事例について検討したが、続く第4章では、逆にOAU/AUが国際共同体に影響を与える可能性について検討する。具体的には、国際刑事裁判所(ICC)とAUの関係悪化の経緯を取り上げ、それに伴うAUのアフリカ司法人権裁判所の設立の決定(2014年)および「脱退戦略文書」の採択(2017年)という行動に焦点を当てる。このAUの行動は、アフリカ内のみならずICCという国際共同体全体レベルの国際機構にも作用しうる機能である。
AUは2009年以降、ICCに対する懸念を表明してきた。特に、2009年2月のAU総会で、ICCがスーダン共和国の当時の大統領であったバシール(Hasan Ahmad al-Bashīr)を被疑者として捜査していることを問題視し、これが最初の反発となった。さらに、ケニアの事例でもAUはICCへの批判を強めた。ケニアでは2007年から2008年にかけて発生した大統領選挙後の騒乱において、1300人とも言われる多くの死傷者が出た。この事態について、ICCの検察官が2012年にケニヤッタ(Uhuru Muigai Kenyatta)大統領らの訴追を行ったことについて、AUは遺憾の意を表明している。
これらのAUのICCに対する反発の背景には、ICCが扱う事件の顕著な地域的偏りや、免除の原則注3があるにもかかわらず、現職や元国家元首といった指導者層が訴追の対象になっていることにある。
この反発の結果、AUはアフリカ司法・人権裁判所の設立を決定し、さらにICCの改革を求める「脱退戦略文書」を採択した。しかし、このAUの行動はICC設立の根拠であるローマ規程に謳われる「処罰の徹底」や「平和構築」を軽視したものではない。むしろICCのメカニズムを再検討することと、アフリカ独自の法的枠組みを通じてこれらの目標を達成する方法の模索として位置付けられる。つまり、AUとICCは共に「平和構築」を目指す国際共同体の一員であると言える。
システム論的に言えば、同一システムの行動者の行動は、他の行動者に影響を与える。したがって、AUの行動は、アフリカ内のみならず、ICCにも影響を与えうるものであり、この相互作用は国際共同体の共同利益やその実現方法に関する議論を喚起する。本書で事例とした両者の関係悪化については、事態をどのように扱うかについてICCとAUの間で齟齬が生じたことが原因であろう。AUの反発は、事態の扱い方について両者が正当と認める価値基準の必要性を示している。したがって、国際社会全体レベルの規範に基づいて判断を下すICCと、当事国の意思をより反映しやすい国際地域機構であるAU間との間に、協議会という制度を形成することによって、国際社会の規範の生成・発展を促すことが可能になることを示した。
(注3) 従来、国家元首や閣僚、外交官など、国家を代表する公的地位にある者には、外国の裁判管轄権が及ばないとされる。
普遍性と「多様性」の相剋を乗り越える
アフリカ地域およびAUは、制度化が進む国際共同体の行動者である。ただし、その国際共同体の制度については、主体的に形成に関与するのではなく、後から組み込まれ参加していくことが多かった。そのため、国際共同体の制度にはアフリカの文化的、社会的背景と調和しないシステムが存在する場合がある。その齟齬に直面した際、AUは自身の利害システムに基づきアフリカの利益を追求するために、独自のシンボル・システムを構築してきた。これは、OAU憲章やAU設立規約、バンジュール憲章、さらにはアフリカ司法・人権裁判所設立の決定や「脱退戦略文書」が採択されていきたことからも明らかである。AUは、地域的なシンボル・システムと国際的なシンボル・システムを調和させた独自のシンボル・システムを作ることによって、アフリカにおける「人権の尊重」をアフリカの理想を反映したものにしてきた。この調和の実現は、AUが単に自己の利益だけでなく、国際共同体から求められる役割をもその行動原理に含むからこそ可能になったものである。つまり、AUの行動は、国際的なシンボル・システムと地域的なシンボル・システムを調和させることによって、多様性を通じた普遍性の尊重を意図したものであると言える。以上から、地域国際機構であるAUは、国際共同体全体のシステムとアフリカ特有のシステムとを、独自のシンボル・システムの形成によって調和させる、いわば調整役としての機能を持つと言える。
以上が、本書を通して得られた地域国際機構の機能である。このような調整役の存在は、共同利益達成のための協働体制をより柔軟かつ効果的に構築する役目を果たし、結果として国際共同体の制度化に対してより一層の豊かな発展を促進するであろう。
いがらし・みか
富山大学学術研究部教育学系講師。立命館大学大学院国際関係研究科博士課程後期課程修了。博士(国際関係学)。立命館大学衣笠総合研究機構客員協力研究員を経て今年2月より現職。
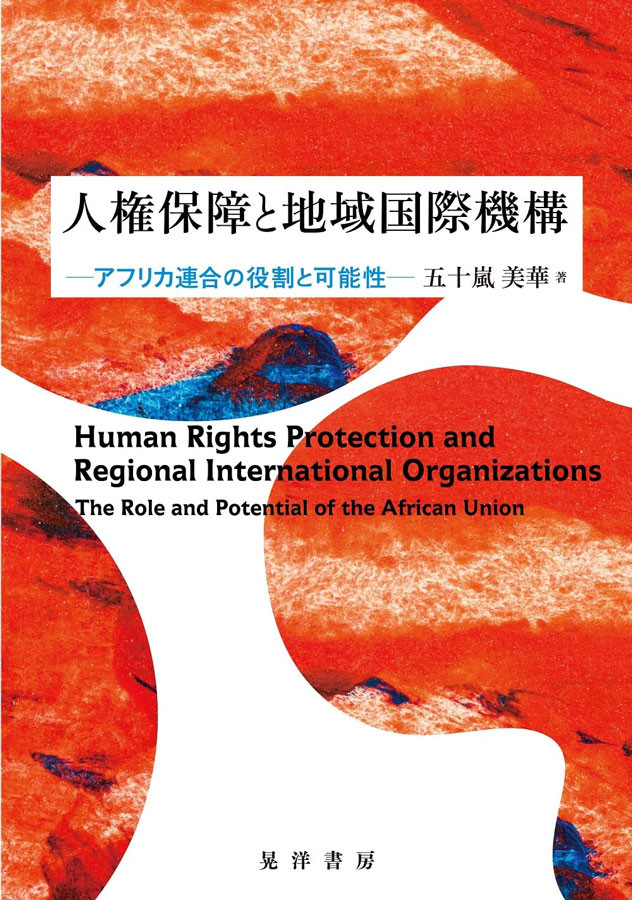
目 次
序 章 現代国際社会における「人権の尊重」
第1章 方法論としての行動システム理論
第2章 パン・アフリカニズムの国際共同体の変動
第3章 アフリカ連合による国際的な人権規範の受容―バンジュール憲章の事例から
第4章 アフリカ連合による国際的な規範への働きかけ―国際刑事裁判所との緊張関係から
終 章 地域国際機構の機能
書名:『人権保障と地域国際機構―アフリカ連合の役割と可能性―』/著者:五十嵐美華(富山大学学術研究部教育学系講師)/出版社:晃洋書房 /発売日: 2024.2 /定価:2,860円
論壇
- 「ポジショナリティ」概念から考える沖縄と日本との権力関係沖縄国際大学教授・桃原 一彦
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(上)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- 地域国際機構という存在富山大学学術研究部教育学系講師・五十嵐 美華
- 皇国史観に汚染された教科書もどき元河合塾講師・川本 和彦
- ちんどん屋を書いた文学者たちフリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 『韓国1964年 創価学会の話』をめぐって本誌編集委員・黒田 貴史
