特集 ● 混迷の世界をどう視る
『現代の理論』とアリスセンター
『NPO支援組織の生成と発展――アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』より
近畿大学経営学部教授 吉田 忠彦
昨年(2024年)の11月に有斐閣より『NPO支援組織の生成と発展;アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』を上梓した。
アリスセンターとは1988年に発足し、2023年に解散した「まちづくり情報センターかながわ」の通称である。今日で言うところのNPOのサポートセンター、あるいは中間支援組織のパイオニアと目されている団体である。
このアリスセンターが設立される背景には、神奈川県を中心としたその当時の市民運動や革新自治体に関わっていた人びとのネットワークがあり、その後もそのDNAを引き継いだ人たちによって運営が行われた。ただ、その35年の間にはNPO法が成立し、5万を超えるNPOが登場したりと、市民運動や市民活動を取り巻く環境は大きく変化し、またアリスセンターを支えるメンバーの顔ぶれやその事業内容も変化していった。2023年7月の解散も、そうしたアリスセンターを取り巻く環境と、アリスセンターを支える人たちとの間の変化などによるものであった。ここでは、とりわけ本誌『現代の理論』とアリスセンターとの関わりを中心に、本書の概要を紹介したい。
設立を構想した3人
アリスセンターを構想したのは、建築家の緒形昭義、元横浜市職員で関東学院大学教授の鳴海正泰、そして生活クラブ生協・神奈川の横田克己の3人であった。
緒形は設立後もアリスセンターの代表となり、最もアリスセンターにコミットしていた人物である。1927年に東京に生まれ、その後旧制の東京府立高等高校を経て東京大学で建築を学んだ。その後は建築家として活躍するが、その一方で市民運動に積極的に参加していた。そもそも緒方の高校、大学の同級生の友人に全学連初代委員長の武井昭夫がおり、緒形は彼と共に高校時代から運動に参加していた。また、大学時代の友人には東京都政調査会から横浜市に移った田村明もいた。
鳴海正泰は、革新自治体の旗手と評されていた飛鳥田一雄の右腕として横浜市で活躍し、その後に関東学院大学の教授になっていた。1963年に飛鳥田が横浜市長になった際には、緒形は革新市政、革新県政や市民参加を支える大学研究者や文化人の会のメンバーとなっていたが、それらを裏方として仕切っていたのが鳴海だった。革新自治体の時代と呼ばれていたその頃には、横浜市、藤沢市、仙台市などの市長をメンバーに全国革新市長会が発足しており、神奈川県においても長洲一二が知事となっていた。1975年の神奈川県知事選挙にあたっては、長洲を応援する「革新県政を推進する学者・文化人の会」が発足し、鳴海は裏方となり、緒形もメンバーとなっていた。この二人は自宅も同じ横浜市の磯子区で、地域の自治会の活動にも積極的に参加するような仲だった。
この「革新県政を推進する学者・文化人の会」で、緒形は藤沢市長だった葉山峻から紹介されて生活クラブ生協・神奈川を率いていた横田克己と会い、生活クラブの新しい社屋の設計などを任される。その後、同会において横田が市民の手による情報誌が必要だと唱えたことに緒形と鳴海が共感し、それを実現しようとして始まったのがアリスセンターの発端だった。
横田克己はもともと東急労組で活動していたが、1960年に結成される社青同に参加し、藻谷小一郎が呼びかけ人となって発足した組織問題研究会で、後に世田谷で生活クラブを立ち上げる岩根邦男と出会い、神奈川で生活クラブを立ち上げることになった。藻谷は満鉄調査部で石堂清倫のもとで活動していたが、組織問題研究会の中ではグラムシの勉強会など行っていた。そこには岩根や横田等の構造改革に賛同する若手が集まっていたのである。
岩根はカメラマンを目指す京都出身の若者だったが、60年安保のデモに参加したのをきっかけに政治活動に入り、社青同の世田谷支部委員長となり、1963年の統一地方選において党の指示で世田谷区議選に立候補するも惨敗し、社会党に限界を感じて、市民活動による社会変革を目指すことになった。岩根は生活クラブから生活協同組合を立ち上げ、順調に活動を広げていったが、自宅の関する新聞報道をきっかけに、生活クラブ生協の一線から退くことになった。一方、生活クラブが生活協同組合になる頃から、東急の職場班などを作ってそこに参加していた横田は、やがて神奈川県でみどり生協を立ち上げ、その理事長となった。これが生活クラブ生協神奈川となり、横田は生協のさまざまな事業を展開し、同時にワーカーズ・コレクティブや福祉生協等の新しい事業や、神奈川ネットワーク運動(NET)などの政治活動にも積極的に関与した。そうした流れの中で、横田もまた長洲を支える学者・文化人の会に顔を出していたのである。
また横田は、現代の理論社を主宰した安東仁兵衛とも懇意で、彼の著作の多くは安東のすすめによって執筆されたものだった。
オルタナティブとしての市民活動のために
1980年代には「オルタナティブ」がひとつのキーワードになっていた。もちろん、ルドルフ・シュタイナーやイヴァン・イリイチといった学者の説く理論もあったが、必ずしも厳密な定義がなされていたわけではなく、既存の価値観や社会の体制に対する市民による主体的な変革といった志向を表す概念として、市民活動や文化活動などさまざまな場面で用いられていた。松下圭一など構造改革派の仲間とさまざまな活動に参加し、古くからの友人たちから「アナキスト」と揶揄されるアンチ体制派だった緒形は、市民が自らの活動のための市民による情報のセンターという横田の構想に共感したのである。
緒形はそうした市民による情報誌をつくる拠点としてのセンターのコンセプトを以下のようにまとめた。これはセンターを立ち上げる際に、協力者を募るために緒形自身が作成したチラシに記されたものである。
「もうひとつの、いきいきとした、わかりやすい地域社会と環境づくりのためのセンター」(Center for Alternative Live Intelligible Community & Environment)
このコンセプトを英訳したものの頭文字をとって「ALICE」としたのが、その後に正式名を超えて市民活動の世界で知られることになるアリスセンターという通称となったのである。もっとも、「センター」という中央集権的なニュアンスを嫌った緒形は、「センター」ではなく「基地(Base)」とし、「アリスセンター」ではなく、「アリス」とすることを唱えていたという。
事業を模索した3人の初期スタッフ
緒形、鳴海、横田が構想したアリスセンターは、「革新県政を推進する学者・文化人の会」のメンバーを設立発起人、そして設立後の運営委員として1988年に始動する。その前年には、実際の事業を担うスタッフとして3人の若者が着任した。ひとりは唯一の専従スタッフで事務局長となる土屋真美子であった。
土屋は大学院を修了した後に一般の企業に就職していたが、その後退職し、大学院で知り合った上村英明、片岡勝らと菅直人の選挙運動に関わったりしながら、その後生活クラブ生協に就職した。生活クラブの中では同僚となった宮城健一や宮崎徹らとシンクタンク的な役割を担った。そして生活クラブの子会社の所属から出向という形でアリスセンターに赴任したのである。出向というのはアリスセンターの人件費を生活クラブが負担するための口実で、実際には土屋はアリスセンターの専従となった。土屋は大学・大学院に所属していた頃には、女子学生としての立場から岩波の『世界』や『現代の理論』に寄稿していた。
アリスセンターの立ち上げ期のスタッフの3名のうち、土屋以外の2人はアルバイトという形でスタッフとなった。そのアルバイトひとりは川崎あやであった。川崎は学生の頃政治学を学び、社会党女性候補の市民選対のアルバイトをしたりしていた。学生時代の下宿生活の中で、生活クラブで活動する女性たちと出会っており、そしてワーカーズ・コレクティブの第一号となる「にんじん」のメンバーたちといっしょに活動することになった。
もうひとりのアルバイトは東京大学の学生であった築雅之であった。築はニュー・アカデミズムが台頭する中で文化人類学を学んでおり、その後は東京大学の大学院に進み、学生・大学院生として勉強しながらアリスセンターのスタッフとして活動した。
このアルバイトスタッフであった川崎と築もまた、若くして『現代の理論』に寄稿していた。安東仁兵衛は社会変革を担う新しい動きと、その担い手である若者に期待していたのであろう。こうした若い人たちにも『現代の理論』に書かせていたのである。
この3人はアリスセンターに集うまでは、それぞれ全く面識もなければ、それぞれのことも知らなかった。また、アリスセンターに採用される経緯も異なっていた。しかし、緒形、鳴海、横田らが構想した新しい市民による市民のための情報センターを担うスタッフとして、『現代の理論』に寄稿していたというそのネットワークの中から見出された若者たちであったのである。
アリスセンターの事業の模索
市民による市民のための情報誌という最初のアイデアは横田によるものだったが、アリスセンターが実際に立ち上がってからは、横田はほとんどコミットしなくなっていた。アリスセンターの3人の人件費は、相変わらず生活クラブ生協・神奈川から賄われていたものの、横田あるいは生活クラブとしてアリスセンターの活動に介入することはほとんどなかったのである。それは、横田が生協の事業の多様な展開に加え、福祉クラブ生協、ワーカーズ・コレクティブ、そして神奈川ネットワーク運動(NET)などの多方面の活動にも手を広げていたためで、そうした生活クラブ運動の全体の中でアリスセンターの位置づけも横田の中ではあったものの、緒形や鳴海がアリスセンターにしっかりコミットしていたこともあり、具体的な活動についてはもはや口をはさむ余地や余裕がなかったと思われる。
一方、アリスセンターの代表となった緒形は、自らの設計事務所と同じ建物の同じフロアーにアリスセンターの事務所を置き、日常的にアリスセンターの活動に関与していた。しかし、スタッフの川崎が「カオスの人」と評するように、緒形は具体的な事業をについて指揮するというタイプではなく、3人のスタッフは具体的に何をすべきかが分からず、途方に暮れながらディスカッションを続けていた。そして、アリスセンターの目的として緒形たちから示されていた、①市民活動の情報交換の拠点の提供、②市民活動・市民事業のサポート、③新しいプログラムの創出の3つの中で、もっとも分りやすい情報交換の拠点を、まず手がけることにした。
その中心的な事業となったのが、解散まで続く情報誌の発刊だった。ニューズレター形式の『らびっと通信』が約10年で275号、その後を引き継いで冊子となった機関誌『たあとる通信』が25年で40号発行された。ただし、その初期においては情報をめぐって、重要な転回が起こっている。「市民活動の情報交換の拠点の提供」という目的を果たすために、土屋たちは神奈川県下のさまざまな市民活動団体を訪問し、かつ団体に機関紙への投稿を呼びかけて、市民活動に関する広報版づくりを進めていた。しかし、そうした市民活動の情報は、市民や市民活動団体にとって有用であったというよりは、市民活動の動向を知りたがっていた行政やシンクタンクにとって有用なものであった。それに気づいた土屋たちは、あらためて市民活動のための情報のあり方を模索すると同時に、事務所や活動の資金を確保する必要性を痛感していた。そうして事業を模索し、市民活動の事務局を請け負う仕事、行政やコンサルからの委託調査などの収入源や、ファイバー・リサイクル運動など、さまざまな活動を手がけていた。
NPO法人となったアリスセンター
そうしてアリスセンターは10年近く活動を続け、市民活動の世界で一定の認知を得るようになった頃、NPO法が成立し、その前後からアリスセンターはその先駆として日本NPOセンターなどを通じて全国的に知られるようになっていた。そして、アリスセンター自身も法人格を取得してNPO法人となった。そのNPO法人化をめぐっては、法人の機関や定款を定める中で、これまでの運営委員会のメンバーとは異なる顔ぶれの役員を入れるなど組織の変革をもたらす動きが起こった。
すでに緒形も実際の事業にはあまり口出しをしなくなっていたし、運営委員会もほとんど土屋たちの決めたことを追認するだけの存在となっていた。そうした状況を背景として、法人としての役員の人選はかなりの若返りが図られた。最初の理事長こそアリスセンターの顔として緒形が就任したものの、はじめから任期は1期のみとされており、2年後の第2期には2代目の理事長として、まだ30歳になったばかりの大学助手の饗庭伸が就任した。緒形との年齢差は44歳だった。
また、初代の事務局長だった土屋は、行政からの委託授業を受けるために設立した有限会社の代表となっており、アリスセンター本体が法人格を取得したため有限会社も不要となるという状況だった。アリスセンターの事務局長は川崎が担っていた。築はすでにアリスセンターを退職し、大学教員となっていた。NPOがブームのようになる中でアリスセンターは先駆者として注目され、土屋や川崎はさまざまな所から講演等の声がかかるようになっていた。欧米のNPOの状況を知るための海外視察などにも駆り出された。
市民活動とNPO
そうしたNPOのブームのような状況の中で、土屋や川崎はある種の違和感を覚えていた。それは、「NPO」というより世間的に認知された団体に、これまで自分たちがいっしょに活動してきた団体とは毛色の異なるものが多く含まれていたことへの戸惑いだった。法人格取得によるさまざまなメリットが喧伝されていたために、補助金がもらいやすくなるからといった動機でNPO法人になろうとする者、そもそも何をしたいのかも曖昧なままに、とにかく流行りのNPOをやりたいという者などからの相談が多くなっていたのである。
また、土屋は台頭するNPOの中でヘゲモニーを握ろうという野心を持つ者と同席する機会が増え、そうした人びとといっしょにやっていくことへの違和感を拭えなくなっていた。そして土屋はアリスセンターを抜けることを決断した。
一方、川崎はNPOやサポートセンターの先駆者としてのアリスセンターの顔として登壇する機会が増える中で、NPOというものへの違和感を覚えながらも、その流れを利用し、アリスセンターのプレゼンスを高め、自分たちのスタンスを示すことで目指す活動を推進することを目論んでいた。ところが、多忙となる中で家族の介護に追われる事態となり、自分自身の体調も崩し、やはりアリスセンターを去ることになった。
NPO支援施策の充実化とアリスセンターの衰退
1998年に成立したNPO法によってNPOというものが急増し、また法人の認証事務はじめ行政の側でもNPOや市民活動を支援する施策はマスト・メニューとなった。とりわけ、支援施設を設置することは、市民参加の実践や遊休施設の有効活用という点から行政側にもメリットがあった。また、サポートセンター、中間支援組織とよばれる民間団体にとっても、行政の支援施設の管理運営の仕事を受託することはメリットがあったため、公設民営の市民活動センターが全国的に普及し、同時に中間視線組織も増えていった。
こうした状況によって、市民活動支援のパイオニアであったアリスセンターの活躍の場が狭めていくことが危惧された。とりわけアリスセンターの地元の神奈川県では、阪神・淡路大震災のあった1995年に元大蔵官僚の岡崎洋が知事に就任し、積極的な市民活動支援に乗り出した。そして就任の翌年には横浜駅からほど近い絶好のロケーションに県民活動サポートセンターをオープンさせた。この神奈川県直営の県民(市民)活動支援センターは、駅近でスペースも広く、かつほとんど無料というもので、多くの利用者を引きつけた。さらに、会議室や作業のための施設などのハードだけでなく、市民活動に助成金を出す基金21、市民活動の紹介や助成のアナウンスを掲載する広報誌『ジャンクション』などソフト面での支援メニューも徐々に充実させていった。また、この神奈川県直営の市民活動センターの盛況は、周辺の自治体にも影響し、公設の市民活動センターのネットワークも形成された。
こうした流れの中でアリスセンターは、公設の施設での市民活動支援では、どうしても限界が生じることを危惧していた。そして、県民活動サポートセンターが運営する「かながわボランタリー活動推進基金21」の運営に対して民間側としてアドボカシー活動を行った。要するに、市民活動を支援するのが目的である基金の運営は、よりオープンで、市民側もその中に参加するするべきであるという主張をし、県側と交渉する活動を開始したのである。こうした展開になった背景には、総額で100億円という県の債権を利用した基金21が、岡崎知事によるサプライズとして市民側にほとんど情報提供されないままに、計画が新聞発表されたという経緯もあった。
行政が設置したセンターの管理運営事業を受託し、団体運営の安定を得る中間支援阻組織が増加し、その行政との関係性の良好性からその他の委託事業もそれらの中間支援組織が受託する流れの中、アリスセンターはむしろ行政と対峙する姿勢を明確化したのである。
時代の変化と解散
土屋、川崎に続いて三代目の事務局長に就任したのが藤枝香織だった。藤枝は、川崎が体調を崩し、休職せざるを得ない中で公募され、就任した事務局長だった。すでに有名になっていたアリスセンターの事務局長の公募には、市民活動の分野でかなりの実績を持つ者も応募していたが、面接やグループディスカッションなどを経て藤枝が選ばれた。その能力の高さと人柄が評価されたのだろう。それはその後の藤枝の活躍ぶりからも伺える。
ただ、その頃の藤枝はそもそもアリスセンターのこともよく知らず、子育ての都合から転職先を探していた折に、アリスセンターも設立に加わっていた神奈川子ども未来ファンドに興味を引かれたものの、そこでの就職口がすでに埋まっていたことからアリスセンターの事務局長へ応募したのである。国際協力関係の仕事に携わっていたが、いわゆる市民運動などについてはあまり知識や経験はなかったのである。
藤枝が事務局長に就任した2006年ごろには日本経済にも陰りが見られるようになっていた。逆にいえば、アリスセンターの初期のころはいわゆるバブル経済の中にあり、行政でもまだ予算に余裕があった。それが民間への委託調査事業等の形でアリスセンターや委託事業受託のための有限会社(アリス研究所)にも及んでいたのである。専従職員は藤枝ひとりで、あとはアルバイトスタッフで運営が続けられた。アリスセンターのこれまでの実績や知名度、そして役員たちのサポートもあったが、藤枝にはもはや荷が重い状況となり、解散を視野に入れた検討がなされるようになった。
こうした状況を知った川崎らかつてのアリスセンターの関係者の何人かが、設立の25周年事業を起案し、設立25周年シンポジウムと『たあとる通信』の特別号を4カ月連続で刊行した。そして、そのままその25周年事業の実行委員会のメンバーがアリスセンターの役員を引き受ける形となり、藤枝はアリスセンターの事務局長を降りた。しかし、アリスセンターの常設の事務所はすでになく、ホームページ上でのニューズレターとして「らびっとにゅうず」が時々更新され、問合せには役員が分担して対応するという状態になった。そんな中で、会計を担っていた役員による不正が発覚したり、川崎が倒れるといったことがらが重なり、2022年には解散が決められ、翌年の7月に正式に解散となった。
乗り物としての組織
アリスセンターが活動した35年間、そして設立の背景となる期間も含め、さまざまな人びとがアリスセンターに関わった。もちろん、それはどんな組織でも同じことがいえるだろうが、アリスセンターの場合には、そもそもの目的の抽象度の高さ、市民活動やNPOの状況の変化もあり、多様な立場の人びとが直接・間接に関わった。それらの人びとは、それぞれの意図や価値観をアリスセンターに持ち込み、それがアリスセンター自体の組織としての多面性、事業の多様性として発現された。
最初の発案者の横田の意図、それを受けて実現化に奔走した緒形や鳴海の意図も、そのままで土屋たちに受け取られずに、彼女たちの間でその解釈が討議され、具体的事業が模索されながら、組織としてのアリスセンターは動き出した。ここでは詳しくは触れないないが、その過程では事務所の近くの新聞社、県庁の関係者、パソコン通信のマニア、労組関係者等々の多彩の人びとが出入りしていた。アリスセンター内のスタッフや役員も顔ぶれが代わっていったし、出入りする人びともまた代わっていった。
アリスセンターという看板は同じであっても、時代によってその内容やロジックの構成が変わっていたのである。そうした多様な人びとの乗り物としての柔軟性が、ただでさえ持続が難しい市民活動団体の世界で、大きな時代の変化の波に翻弄されながらも、35年存続したアリスセンターの特徴だったのである。
よしだ・ただひこ
1959年京都市生まれ。近畿大学商経学部卒業、近畿大学大学院商学研究科博士後期課程修了。近畿大学豊岡短期大学を経て現在近畿大学経営学部教授、京都大学公共政策大学院、立命館大学経営学部非常勤講師。著作に、『地域とNPOのマネジメント』(晃洋書房、編著)、『非営利組織論』(有斐閣、共著)、『市民社会論』(法律文化社、共著)、『市民社会創造の10年―支援組織の視点から』(ぎょうせい、共著)、『日本のコレクティブ・インパクト: 協働から次のステップへ』(中央経済、共著)など。
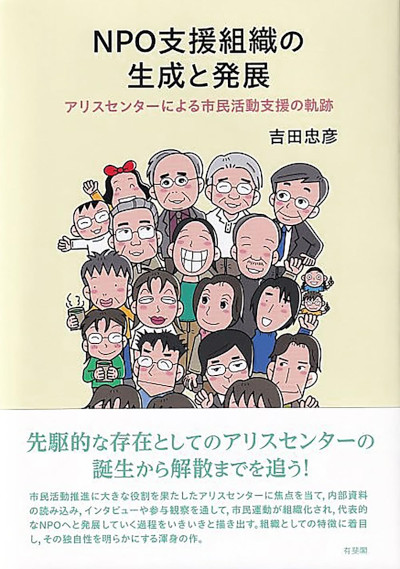
目 次
プロローグ
序 章 なぜアリスセンターに着目するのか
第1章 アリスセンター設立の経緯
第2章 アリスセンターの事業構想と模索
第3章 NPO法とアリスセンター
第4章 中間支援組織としてのアリスセンター
第5章 アドボカシーとアリスセンター
第6章 おおぜいのアリスたち
終 章 乗りものとしての組織
資 料
書名:『NPO支援組織の生成と発展―アリスセンターによる市民活動支援の軌跡』/
著者:吉田忠彦(近畿大学経営学部 教授)/出版社: 有斐閣/発売日: 2024.11.28
特集/混迷の世界をどう視る
- 政党政治のグローバルな危機の時代法政大教授・山口 二郎×中央大教授・中北 浩爾
- 日本は知識経済化ーイノベーティブ福祉国家へ慶応大学名誉教授・金子 勝
- トランプ2.0、パワーアップの秘密を暴く神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 立憲民主党は政権運営の準備を急げジャーナリスト・尾中 香尚里
- どこへ行くか 2025年のヨーロッパ龍谷大学法学部教授・松尾 秀哉
- ショルツ政権の崩壊とポピュリズム下の総選挙在ベルリン・福澤 啓臣
- 追加発信韓国の「12・3戒厳」は、違憲で違法の内乱聖公会大学研究教授・李昤京
- 創造的知性の復権労働運動アナリスト・早川 行雄
- 時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
- 労働基準法体系の解体を許すな!全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長・大野 隆
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆
- 『現代の理論』とアリスセンター近畿大学経営学部教授・吉田 忠彦
- 追加発信時代の転換を読む(上)――少数与党自公政権に売り込み競う維新と国民民主大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員・水野 博達
