論壇
大逆事件と再審法改正
揺らぐ日本の「法の支配」、民主主義と同じく日々更新が必要
ジャーナリスト 西村 秀樹
「大逆事件の生き字引」が本を出版 / 大岩川嫩さんとは / 大逆事件とは / 再審請求 / 名誉回復 /
大逆事件の読み方は「ダイギャク」か、「タイギャク」か / 刑事司法記録の保存 / 第二次再審請求 /
再審法の改正問題 / 「法の支配」は日々更新
「大逆事件の生き字引」が本を出版
寒さがこたえる2月中旬、私(西村)の携帯電話に一本の電話がかかってきた。電話の主は、「大逆事件の真実をあきらかにする会」世話人を40年余り務め、この事件の真相究明に尽力してきた大岩川嫩(ふたば)さん。私が心の底からリスペクトするお方だ。
「本を書いたので」とおっしゃる。やがて拙宅に本が届いた。
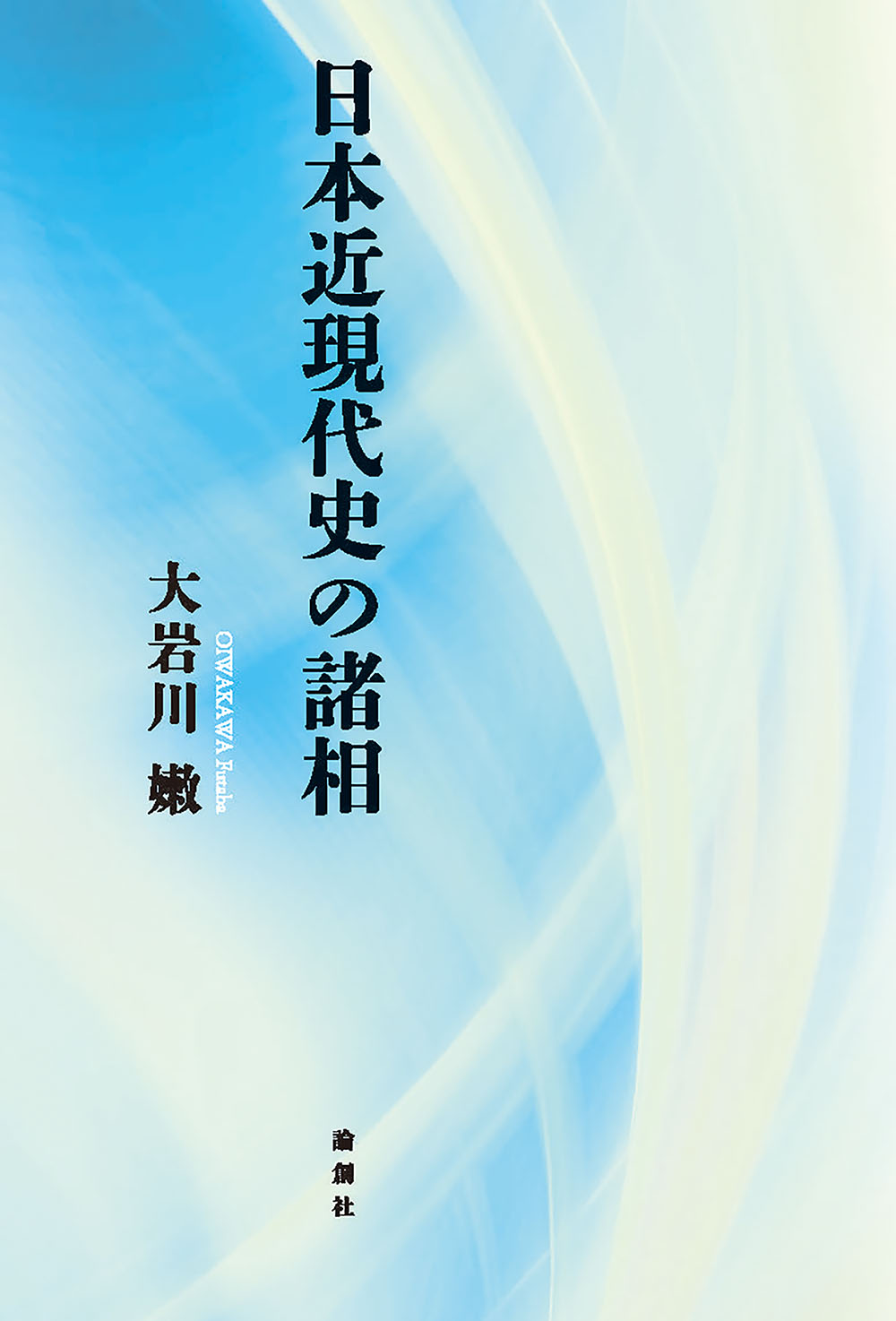
大岩川嫩著『 日本近現代の諸相』(論創社刊、2024.12、752頁、8000円+税)
タイトルを『日本近現代の諸相』(論創社刊、以下本書と書く)という。出版元の論創社はこれまで大逆事件に関する著作を熱心に出版してきた会社だ。びっくりしたのはその分厚さ。752ページ。イタズラ心で物差しを当てると、4.8センチ(ちなみに定価は8000円+税金)。
内容は、第一部が「大逆事件とその周辺」。第二部「歴史学へ」。第三部が「アジア経済研究所」当時の著作。第四部が書評と解題のまとめ。第五部が「出会いと別れ」。第五部の最後に「早野 透さんのおもかげ」と題したエッセイを掲載している。
早野 透さんは、朝日新聞のコラムニスト時代、「担当している『ニッポン人脈記』の連載に大逆事件を取り上げたいので」と、大岩川嫩さんに協力を求めた。だから早野 透さんと大岩川嫩さんの出会いは2005年に始まる。早野 透さんは四年後の2009年に全14回の記事を一人で書き上げ、2010年新聞社退職後、桜美林大学で教鞭をとる。のち早野 透さんは体調を崩し、2022年急逝する。それを大岩川嫩さんは印象深い文章でまとめている。
大岩川嫩さんとは
私は文章を書くとき、通例、女性の年齢を記載しないのだが、本書を紹介するのに重要な要素なので、本書の筆者の年齢を書く。なんて大層なことを言わずとも、本書の「序」で、明治大学副学長を務めた山泉進・元法学部長が最初のセンテンスをこう始める。「本書は、本年満91歳になられた大岩川嫩さんがその生涯にわたって発表された著作をまとめられたもの」と年齢を明示している(ちなみに山泉進さんは、土佐・四万十市(かつての中村市)出身。この地は、読者お分かりのとおり、幸徳秋水の出身地でもある)。山泉進さんは、大岩川さんを「大逆事件の生き字引」と紹介する。
本書の著者略歴によると、大岩川嫩さんは1933年生まれ。1957年國學院大学文学部史学科卒業後、作家資料助手、史料集編纂業務などに従事、1963年アジア経済研究所入所、海外業務室参事、広報部主幹などを経て1994年定年退職と書いてある。
多くの人は大岩川さんを「大逆事件の真実をあきらかにする会」世話人と承知している。
私が大逆事件と出会ったのは浄土真宗大谷派の名誉回復運動がきっかけだった。浄土真宗大谷派は、大逆事件で検挙され死刑判決を受けた新宮・浄泉寺の住職・高木顕明(けんみょう)の僧籍を剥奪する重い譴責処分を下したが、1996年名誉回復した、そのことを大谷派の知人、山内小夜子さんに教えられ、私は和歌山県の新宮に通うようになった。そのころ、大岩川さんに出会ったと記憶している。東京の新宿にある正春寺で、毎年1月24日の死刑執行日前後に行われる追悼会で、大岩川さんがあれこれ段取りしている姿を拝見した。
大逆事件とは
本書の「序」で、山泉進さんは事件の概要を次のように紹介している。
「現在から一世紀を少し超える前、1911(明治44)年1月18日東京の大審院において、幸徳秋水を首謀者とする明治天皇暗殺事件があったとして24名の社会主義・無政府主義者に死刑判決が下された。当時の刑法第73条の大逆罪に該当する事件として大逆事件と呼ばれる」。
事件の背景をはっきり書いているのは、中学生向けの教科書だ(『ともに学ぶ人間の歴史』学び舎、2020年文部科学省検定済)。引用する。
「社会主義運動と大逆(たいぎゃく)事件。労働者が増えると、労働条件の改善を求める労働運動が活発になった。1901年には、日本で最初の社会主義政党・社会民主党(しゃかいみんしゅとう)が結成されたが、政府によって解散させられた。
1910年、明治天皇の暗殺を計画したとして、幸徳秋水をはじめ、多くの社会主義者たちが逮捕され、12人が処刑された(大逆事件)。現在では、秋水ら多くの人が無実だったことがわかり、名誉回復がはかられている」。
ここで、山泉記述と中学の歴史教科書とで死刑の処刑人数に差があるのは、天皇の恩赦があったからだ。検察が大逆罪の罪状で検挙・起訴した被告は26人、うち大審院が死刑判決を下したのが24人(残り2人は有期懲役刑)。そして明治天皇の恩赦が判決直後(翌日)に出され、半数は死刑から無期懲役に減刑された。逆に言えば、天皇の恩赦があってなお、12人は判決からわずか一週間後、死刑を執行された。
私たちの同時代で言えば、1995年3月オウム真理教による地下鉄サリン事件など一連の犯罪で、2018年7月教団の幹部13人の死刑が執行されたが、私たちはそのときの衝撃をきのうのことのように記憶している。幸徳秋水大逆事件での12人死刑執行当時、当時日本にいた海外の新聞記者は大きな驚きをもって海外に伝えたという。
再審請求
死刑判決後、無期に減刑された、被告の一人、坂本清馬(せいま)さん(高知県出身)は、刑死した森近運平(岡山県出身)の妹・森近栄子さんとともに再審請求の準備をする。
1960年「大逆事件の真実をあきらかにする会」(以下「あきらかにする会」)は、坂本清馬たちを支援する目的でスタートした。大岩川嫩さんはこの「あきらかにする会」結成当時から事件の真相究明に尽力してきた。だから大岩川さんの活動は半世紀どころか65年を超える。大岩川さんが「大逆事件の生き字引」と呼ばれる由縁である。
大逆事件50年を期して、1961年1月、坂本清馬さんたちは再審を請求したが、最高裁判所は1967年請求を棄却。だから法的には24人に対する死刑判決は有効のままだ。
坂本清馬さんについては、ノンフィクション作家の鎌田慧(さとし)さんが『残夢—大逆事件を生き抜いた坂本清馬の生涯』を週刊金曜日に連載した(金曜日刊、2011)。もっと遡れば、神崎清さん(『獄中手記 大逆事件記録1』実業之日本社、1950。『革命伝説 大逆事件の人々』芳賀書店、1968)、佐木隆三さん(『小説 大逆事件』文藝春秋、2001)、田中伸尚さん(『大逆事件—死と生の群像』岩波現代文庫2018)と錚々たる作家が真相究明に挑んでいる。
にもかかわらず、大逆事件の被告たちの法的地位は、死刑の有罪判決が降りたままというのは先述のとおり。
名誉回復
片方で、研究者、法律家による大逆事件の真相究明が進んでいる。
浄土真宗大谷派が明治期に大逆事件で検挙された高木顕明の名誉回復を果たしたが、大谷大学教授だった泉恵機(いずみしげき)さんの先行研究が大きな要素となった。高木顕明は日本国中がロシア憎しのナショナリズム一色に染まるなか、親鸞の教えに基づき、日露戦争に反対し、和歌山県庁が新宮の熊野早玉大社近くに公営の遊郭設置を計画したことに対して反対を訴えた。また、檀家の被差別部落民の惨状を目の当たりにして自らもあんま・マッサージの修行をしたとも伝えられている。そんな反戦、フェミニズム、人権など時代を先取りした思想を持つ僧侶に、真宗大谷派は僧籍剥奪という、厳しい譴責処分を下した。
大谷派が高木顕明の処分見直しを決めたのは、総理大臣が靖国神社を参拝し、真宗大谷派の僧侶を含め、それは政教分離を定めた日本国憲法に違反するという裁判を起こした時期に当たる。そうした活動の延長上に、「先の大戦」当時、中国大陸に侵略寺院を設置するなどの過去を調査していった。そうした自らの「戦争責任」追求のプロセスの中で、日露戦争当時、反戦を唱えた高木顕明を「発見」した経緯がある。教団内部で議論し、1996年高木顕明の名誉を回復した。
その大谷派の名誉回復運動を受けて、和歌山県新宮市では、同じく死刑判決を受けた医師・大石誠之助に対する名誉回復の市民運動が起こった。没後107年目に当たる2018年1月24日、平和・博愛・自由・人権を唱えた先覚者として、大石を名誉市民に認定した。(和歌山県新宮の大逆事件被告たちの名誉回復を目指した市民活動については、拙論「大逆事件の志を継ぐ〜二河(にこう)通夫」『現代の理論』特別号に記述した)。
大逆事件で死刑執行されて100年目に当たる2011年、幸徳秋水の出身地、高知県四万十市をはじめ、日本の各地で改めて大逆事件を考えるイベントやシンポジウムが開催された。
「あきらかにする会」でも、100年目の記念行事を模索したが、山泉進事務局長と大岩川嫩世話人という実質二人の戦力でできることは限られると判断し、「あきらかにする会」ニュースの復刻版出版を果たした。『大逆事件の真実をあきらかにする会ニュース、第1号〜第48号』は、2万6千円と高額ながら、2010年ぱる出版から世に出た。
大逆事件の読み方は「ダイギャク」か、「タイギャク」か
本書の興味深い点は、ものごとを根源的に考える大岩川さんの姿勢を学べることだ。例えば「大逆事件」の読み方。「ダイギャク」か、「タイギャク」か。私は濁点なしで「たいぎゃく」と長く読んできた。理由は周囲の人たちがそう読んでいるから、という付和雷同の典型だった(ちなみに先ほど引用した『学び舎』中学教科書のふりがなは、濁らず「タイ」)
本書で大岩川さんは明快な答えを導いている。濁点つき、「ダイギャク」が正解だという。根拠となったのは、日本大学法学部教授で、法制史家の新井勉の著作『大逆罪・内乱罪の研究』(批評社、2016)だった。新井教授の根拠は養老律令。養老律令というのは、西暦718年、藤原不比等らによって作られた律令のことで、律が刑法、令は行政法のこと。いわば「法の支配」という。本書から孫びきする。
「養老律のなかの八虐の一つの罪名『謀大逆』にさかのぼる。大の字は漢音がタイ、呉音がダイ、逆の字は漢音がゲキ、呉音がギャクで、謀大逆はムダイギャクと読む」。
その新井教授の根拠列挙を受けて、大岩川さんの結論。つまり、漢音と呉音を混同しない限り、「タイギャク」の読みは成立せず、呉音の「ダイギャク」が正しい、ということになると。
刑事司法記録の保存
「あきらかにする会」が坂本清馬らの大逆事件の再審請求を支援する目的で結成され、その再審請求は最高裁判所で棄却されたことは先述したが、検察による26人起訴、大審院による24人への死刑判決は法的には確立されたままだ。
いま、幸徳秋水大逆事件の第二次再審を目指す動きがある。
課題は二つ。一つは、刑事司法記録の保存の問題。もう一つは、再審法の問題だ。
本書はその刑事司法記録の保存の問題に対し真正面から取り組んだ論文を最初に掲載している。大岩川嫩著「幸徳秋水等大逆事件記録の歴史的意義」だ。そしてこの論文は二年前に出版された論文集に寄稿された。
オリジナル論文集は長いタイトルをもつ。編著者は石塚伸一・龍谷大学名誉教授。『刑事司法記録の保存と閲覧〜記録公開の歴史的・学術的・社会的意義』(日本評論社、2023.2)という。この本に大岩川嫩さん、山泉進さんに加え、田中伸尚さんが論文を寄せている。
田中伸尚さんは、1941年生まれ、朝日新聞記者を経てノンフィクション作家。『ドキュメント昭和天皇』(全8巻、緑風出版、1984-92)、私には、箕面忠魂碑訴訟を弁護士なしの本人訴訟で闘った神坂哲・玲子夫妻を中心とした市民の闘争記録『反忠 神坂哲の72万字』(一葉社、1996)に親しみを感じた。裁判当時、当該の忠魂碑の近所に住まいしていたから、神坂さんとも親しく付き合った。
刑事司法記録の保存の問題に話を戻す。ここで思い出すのは、2023年度日本新聞協会賞を受けた神戸新聞のスクープ(取材班代表 霍見(つるみ)真一郎・編集委員)だ。
神戸新聞は、2022年10月22日付け朝刊で「神戸連続児童殺傷事件の記録廃棄をめぐる一連の報道」を報じた。もう少し具体的に述べると、1991年小学生5人が襲われ、2人が殺害された神戸児童連続殺傷事件で、神戸家庭裁判所が「当時14歳で逮捕された少年Aに関する事件記録」を破棄していたことをスクープした。さらに少年事件の事件記録が神戸家裁にとどまらず日本各地の家庭裁判所でも同じように破棄していたことを続報した。はじめ突っぱねていた最高裁判所は、神戸新聞のスクープから半年後に方針を転じ、調査と検証を開始した。最高裁には珍しくと言ってはなんだが、調査結果を公表し、各地の家庭裁判所での記録破棄に対する自らの責任を認め、記録保存に向けた理念規定の導入や第三者委員会の設置など、適切な保存に向けた改革を図る方針を打ち出し、謝罪の会見を開いた(2023年5月26日付け朝刊)
ジャーナリズムが権力監視に役立った目覚ましいスクープだった。
第二次再審請求
大逆事件について、改めて、二次の再審を請求する動きがある。
大阪の金子武嗣弁護士が、昨(2024)年12月、一冊の本を出版した。『幸徳秋水 大逆事件の研究〜「再審請求」を追究して』(日本評論社)。内容紹介に「本書は再審請求の実現を目指す書である」と謳っている。
世俗的なつながりの話で読者には怒られそうだが、金子弁護士は、私が北朝鮮に7年間抑留された第十八富士山丸事件の取材をしていた当時、日本に帰国した紅粉勇船長と栗浦好雄機関長が日本政府を相手取って国家賠償請求訴訟を起こした二人の代理人だった。私は大阪・北区の金子弁護士事務所をたびたび訪れ、取材したことを記憶している(『北朝鮮・闇からの生還〜富士山丸スパイ事件の真相』光文社、1997。のち『北朝鮮抑留〜第十八富士山丸事件の真相』岩波現代文庫、2004)。その金子弁護士が大逆事件の再審請求について研究中だと聞いていた。
大岩川嫩さんの著作に金子弁護士の言及がないが、金子弁護士の共著作者は石塚伸一龍谷大名誉教授であり、一方、大岩川さんらが刑事司法記録についての論文三本を寄せた論文集の編者は同じ石塚名誉教授というつながりが見えてくる。
再審法の改正問題
再審の問題で思い出すのは、袴田事件だ。冤罪の防止や救済は、民主的な法治国家の根幹にかかわる問題だ。
昨(2024)年9月26日、静岡地裁が袴田巌さんに再審無罪を言い渡し、10月9日検察が上訴権を放棄したことで、無罪判決が確定した。
事件の発生が1966年6月30日、静岡県清水市(現在の静岡市清水区)で、味噌製造会社の専務宅が全焼し、焼け跡から専務一家4人の死体が発見された。警察は、味噌工場の従業員で元プロボクサーの袴田巌さんを逮捕、拷問の結果、袴田さんは犯行を「自白」し、裁判所は死刑判決を言い渡し、1980年最高裁で死刑が確定した。その後、二度にわたって再審が請求され、2020年最高裁は、東京高裁決定を取り消し、静岡地裁に差し戻した結果、2024年無罪が確定した。袴田さんにとっては、事件発生後逮捕され、無罪確定まで58年が経過した(経緯は、日本弁護士連合会のホームページを参照)
この袴田無罪確定を受けて、再審法見直しの動きが活発になっている。問題点は多々あるが、一番の問題点は「開かずの扉」と呼ばれるハードルの高さ。そして時間がかかることだ。袴田さんのケース、最初の異議申し立てから再審決定まで40年以上かかった。日弁連は、請求手続きにおける証拠開示の制度化、開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止などを求めている。
袴田事件の再審請求では、警察・検察が持っている証拠資料が新たな証拠として開示されたことが再審請求スタートのきっかけになった。
再審法改正をめぐっては二つの動きがある。一つは立憲民主党を中心とした議員立法の動き。もう一つは法務省が法制審(法制審議会)に法改正を諮問し見直しを検討する動きだ。
法務省は、2025年4月21日、法制審の初会合を開いた。およそ20人の部会メンバーには、袴田事件で11年前静岡地裁の裁判長として袴田さんの再審開始を認めただけでなく釈放を認めた村上浩・元判事や、日弁連の再審法改正実現本部の本部長代理として先頭に立ってきた鴨志田祐美弁護士が選ばれた。
これだけを読むと、法務省は再審法の改正に前向きかと理解されそうだが、実はそうではないというのが、鴨志田弁護士の主張だ。
アムネスティ・インターナショナル日本支部と日弁連が合同で開催した再審法についての勉強会に、私も参加したが、鴨志田弁護士は、現行再審法の問題点をすでに日弁連で洗い出しており、法務省は再審法の改正が実現する「議員立法」を潰すのが目的だと主張する(刑事弁護OASIS「再審法改正で大きな動き 法務省の方針は「議員立法潰し」)。
その指摘が当たっているかどうか。少なくとも数年の時間がかかるか、議員立法で早く決まるかは別にして、再審法の見直しは目に見えるところまできた。
「法の支配」は日々更新
かつて安倍晋三総理は「日本は法の支配、自由と民主主義」を謳い、中国やロシア、北朝鮮の一党独裁とは違うと、胸を張っていた。
しかし、その日本の「法の支配」をきちんと検証してみると、その「法の支配」の法体系が、たとえば再審制度は大正時代につくられ、以来一度も法改正はない。あるいは、選択制夫婦別姓制度を導入すれば日本の伝統が損なわれるという、自民党内の保守勢力の主張に対し、法務省の民事局長はつぎのように国会で答弁している。「夫婦同姓制度は江戸時代には存在せず、明治時代の民法制定により導入された」(2024年12月13日、参議院予算委員会)。諸外国では、アメリカ、イギリス、ロシアでは夫婦別姓を選択でき、フランス、韓国、中国では原則として別姓、夫婦同姓を法律で義務付けているのは現在では日本だけ。夫婦同姓制度は、明治時代からの「イエ制度」の結果なのだ。
さらには、帝国主義の反省と脱植民地主義の問題でも、日本の法体系は不作為だ。京都帝国大学が「同意」なく奪った琉球遺骨の返還請求訴訟で、大阪高裁は「琉球民族は先住民族だ」「日本帝国による琉球の植民地支配」を日本の国家機関として初めて認定したものの、肝心の遺骨返還については認めなかった。
国連を中心に、21世紀に入り、国際的な「法の枠組み」が変化している。民主主義と同様、法の体系も不断に改良が求められている。
冒頭に紹介した大岩川嫩さんや山泉進さんの作業は、110年以上前の冤罪の名誉回復だけでなく、日本の「法の支配」の欠陥という岩盤を穿つ貴重な作業なのだと、改めて痛感した。
にしむら・ひでき
1951年名古屋生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、毎日放送に入社し放送記者、主にニュースや報道番組を制作。近畿大学人権問題研究所客員教授、同志社大学と立命館大学で嘱託講師を勤めた。元日本ペンクラブ理事。著作に『北朝鮮抑留〜第十八富士山丸事件の真相』(岩波現代文庫、2004)、『大阪で闘った朝鮮戦争〜吹田枚方事件の青春群像』(岩波書店、2004)、『朝鮮戦争に「参戦」した日本』(三一書房、2019.6。韓国で翻訳出版、2020)、共編著作『テレビ・ドキュメンタリーの真髄』(藤原書店、2021)ほか。
論壇
- 寄稿――『朝日新聞』が記事で「先住民族」を「先住人民」と表記フリーライター・平野 次郎
- 琉球の脱植民地化と徳田球一(中)龍谷大学経済学部教授・松島 泰勝
- テキヤ政治家・倉持忠助の「電力問題」(上)フリーランスちんどん屋・ライター・大場 ひろみ
- 「海の遺骨収容」の可能性切り開く「新聞うずみ火」記者・栗原 佳子
- 大逆事件と再審法改正ジャーナリスト・西村 秀樹
- 四国はどうなる、地方はどうなる松山大学教授・市川 虎彦
