論壇
政治の「失われた50年」を取り戻すために
山口二郎著『日本はどこで道を誤ったのか』を読む
本誌編集委員 大野 隆
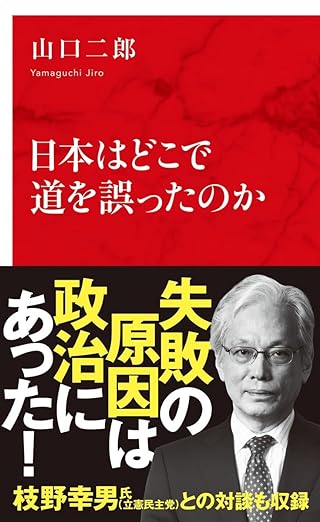
山口二郎著『日本はどこで道を誤ったのか』(インターナショナル新書2024年)
著者は著名な政治学者であるが、現実政治の世界でも市民連合の中心として立憲政治の確立のために行動されている。その著者が日本政治の過去を振り返り、高度成長の終焉以降を「失われた50年」として総括している本である。高度成長期までの日本の経済・社会は、それなりに生き生きとして「一億総中流」と言われていた。それが今や一部の大企業や富裕層に富が集中して、日々の食事にも困る人たちが出てくるという、超格差・分断社会になってしまっている。日本の政治にそうなる以外の道はなかったのかと、時代ごとに発表されていた政治の主張を振り返り、そこからありえたであろう可能性を確認して、今後のこの国のあり方を変革する指針を探ろうとしている。
私は学者でも歴史を勉強しているわけでもないので、生意気にこの本を評価することなどできない。内容を紹介して、読者各位に本書を読むことを勧めたいと思う。
著者が言う通り、政治は経済活動に関するルールや富の配分を決める。その点で政治は人々の暮らしに直結しており、改めてその政治のあり方を見直すことは重要である。
バブル崩壊以降ほぼ30年、経済をめぐっては「失われた30年」と言われる。その30年はいわゆる「一世代」だが、今や年齢50代になるこの国の中堅を担っている人たちは、すべてその「失われた30年」の中で人生を送ってきたと言ってもよい。
1970年代に二度の石油ショックによって高度成長は終わったが、日本は省エネなどの技術革新を進めて競争力を強めて、80年代には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるまでになった。しかしその後はイノベーションが起こることなく、実質賃金が減少を続ける時代になる。そして今や、「公共部門を切り刻み、公務員を減らしたり待遇を悪化させたりすることを改革と呼ぶ、粗雑で反知性的な用語法がまかり通っている」時代になってしまっている(本書17頁)。これをどう転換するか、それは経済の課題である以前に政治の問題であるわけだ。以下、本書の内容を、50年の前半を中心に紹介する。
高度経済成長の終焉
1970年代半ば「石油危機」を契機に高度成長は終わる。やがて小泉政権の「構造改革」を経て新自由主義が日本を席巻し、安倍一強政治の挙げ句、現代に至っている。
高度成長が終わったことは大きな危機感を呼び起こしていたが、現実には、「70年代半ばの日本の失業率は2%前後で、経営者は安易な首切りをせず、人々は働きながら不況を耐え忍んだ」のだ(49頁)。日本的雇用慣行が最もそれらしさを発揮していたのだが、香山健一などが、その「危機」をもたらしたのは戦後民主主義の考えや文化であったとして、未だ成立していない福祉国家批判を行なった。その主張は、頑迷な保守派を助け、新自由主義のための地ならしであったと言えよう。
一方で、74年三木内閣は「ライフサイクル計画」を打ち出し、「西欧型の公的制度によるリスク処理と、日本における企業、家族という共同体によるリスク処理のベストミックスを模索」していた。そうした体制内進歩派の構想があったとのことだ(56頁)。その考えはその後大平正芳によって継承されようとしたが、その大平の急死によって頓挫、「一般消費税」構想が支持を得られなかったことを受けて、80年にあとを襲った鈴木善幸は「増税なき財政再建」を掲げた。これが土光敏夫の「第二臨調」に繋がる。
新自由主義の浸透・拡大――自己責任の時代へ
土光臨調は、歳出削減と民営化・規制緩和を唱導した。国鉄、電電公社、専売公社の民営化はその象徴だった。生活リスクへの対処も、「公的システムによるカバーと自助努力を組み合わせるのではなく、家族さらには擬似的イエとしての企業にリスク対処を求める」発想となり、「日本型福祉社会」と呼ばれて広がるところとなった(60頁)。その後の「個人間でも競争第一、勝ち組・負け組の世界」に続いていって、現在の日本社会の現実へと至ることになる。
同じ頃1985年には労働者派遣法が成立し、低賃金でギリギリの生活をせざるを得ない非正規労働者が急増するようになる。臨調行革が求めた「家庭と企業からなる日本的システムによるリスク処理」が壊れ、バラバラな個人が自力でリスクに対処せざるを得ない社会が始まったのだ(61頁)。
著者はここで「他の民主主義国における普通の左派政党の不在」が特色だったとして、当時の社会党を批判する(66頁)。江田三郎「構造改革論」にも触れながら展開される著者の議論は、「構造改革論」に正面から取り組んだことがあるであろう本誌の読者にはどのように届くだろうか。
90年代後半の金融危機は政治改革論議と並行した。そして最初の政権交代が起こり、細川政権は選挙制度改革を行なったものの、政治改革にはほど遠かったと言えるだろう。その後の「自・社・さ」村山政権でも、とりわけ日常の国民生活に関わる政策では、大きな特色は出せなかったのではないだろうか。
その後橋本政権が成立、一方で共産党を除く野党が合流して新進党ができる。橋本政権は「小さな政府」を強調して、行政改革を行なった。しかし金融危機の亢進によって徹底せず、その後の小渕政権も首相の急死で政策は不徹底にならざるを得なかった。しかも90年代末の金融危機の処理に当たって、公的資金の投入で責任者が救われてもその責任追及もされず、国民の負担が大きくなるばかりだった。民主主義が破壊されたが、その問題点は全く明らかにされずに「犯罪者が居すわる」状況になった。バブル崩壊は壮大な責任転嫁を生み出した。著者は「先進国随一の長時間労働に耐えてきた国民に対して、『政府の支援が過剰だった、これからはもっと努力しなければ幸せになれない』と政府が説教する」ようになったという(145頁)。
そして小泉政権が誕生する。小泉は「構造改革」を言ったが、中身は郵政民営化ばかりで、どこまで「改革」が広がるのか、必ずしも明らかではなかった。時代の閉塞感が小泉に対する大きな国民的支持に繋がったのであろう。小泉が「痛みに耐えて」と繰り返した(155頁)のは、結局肝心な「責任」を曖昧にすることを狙っていたのではないかと思われる。
小泉政権から民主党政権を経て安倍政権へ
小泉政権以降については、時代も新しく本書の叙述も詳しいので、ぜひ直接読んでいただきたい。ただ、その頃労働法制の規制緩和が進み、ホワイトカラーエグゼンプションが議論されたことは重要だ。競争、それも強者の自由な競争が前面に出され、かなり社会的にもそれが受け入れられる素地ができたことが重要だろう。
著者は、当時の労働政策審議会の委員で派遣会社を経営していた奥谷禮子が2007年に言ったことを引用している。「格差社会と言いますけれど、格差なんて当然出てきます。仕方がないでしょう。能力には差があるのだから。・・・経営者は、過労死するまで働けなんて言いませんからね。過労死を含めて、これは自己管理だと私は思います。・・・労働基準監督署も不要です。個別企業の労使が契約で決めていけばいいこと。・・・労働者が訴えれば民法で済むことじゃないですか」と(165頁)。今の労働政策にもこうした考えが繋がっていると思われる。
そうしてやがて、民主党政権をはさんで、第二次安倍政権が登場する。著者は、選挙制度改革や民主党政権に関しては他の著書で述べているからもあるのだろうか、叙述は少ないように思うが、民主党については原則的な批判が展開されている。
終章は「アベノミクスと戦後日本の終わり」と題されている。著者は「女性活躍」や「働き方改革」などに触れ、アベノミクスでは「様々なキャッチコピーが貼りつけられただけで、統合的な世の中の形は明らかにならなかった。そのことの大きな理由として、安倍および安倍を支えた自民党右派の家父長的権威主義が21世紀の日本を切り拓くものではなかった」ことがあると指摘している(221頁)。
著者は安倍政権に対する支持の根拠に日本社会の現状肯定気分の高まりを見ている。しかし、それはナショナリズムの亢進とは異なるとも言う。安倍を支えた右派的なナショナリズム(政治的に活発で他国民を排斥するような自国中心主義)とは違うということだ(28頁)。今後の社会をみる上で、この「現状肯定」をどう捉えるか、大きな課題でもあろう。
自民党の綱領
一般には余り注目されないが、ここで自民党が2005年と2010年に綱領を変えていることに注意したい。2005年では「小さな政府を」と言って新自由主義を宣言しているが、一方で「持続可能な社会保障制度」を見出しに掲げている。しかし2010年では「日本らしい日本の姿を示し」とか「活力ある日本像を目指す」として「家族、地域社会、国への帰属意識を持ち、自立し、共助する国民(を目指す)」と言う。
明らかに新自由主義に加えて、右派的復古的考えを唱導している。ここは著者の指摘を裏付けるものであろう。自民党はそういう政党になっているのだ。
私たちはとかく「自民党に昔のようなリベラルがいないから問題だ」などと言うが、そもそも自民党にはリベラルが入り込む余地がなくなっていることを忘れてはなるまい。
以上、明るい気分になれることではないかもしれないが、本書を読んで「失われた50年」をどう終わらせるか、考えることが求められているということだろう。
おおの・たかし
1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会副委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。
論壇
- 維新「財政ポピュリズム」論を検証する大阪公立大学人権問題研究センター特別研究員/水野 博達
- 国際経済は高校でどう教えられているのか(下)元河合塾講師/川本 和彦
- 一体誰のための再開発か?フリーランスちんどん屋・ライター/大場 ひろみ
- 他者の声への応答歴史知研究会/川島 祐一
- 政治の「失われた50年」を取り戻すために本誌編集委員/大野 隆
