連載●池明観日記─第27回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
≫越南(ウォルナム)と越北(ウォルブク)について≪
私はほんとうに告白的に私の一生について書かねばならないと思っている。そうするほどの人生でもないのにと考えてながらもである。実はそのような告白録を書くだけの自信もない。ただ多少公的なこと、例えば韓国の政治状況と私の一生という観点から書くとしてもほんとうに多くのことを書かねばならないといえよう。『太白山脈』が描き出したあのような一種の左翼同調的な傾向というのは、戦後南においてある意味では共通した雰囲気であったのではなかろうか。実際、私が1947年頃忠州師範付属小学校にいる時もそうであったし、48年頃のソウル大学の雰囲気もそうであった。それである意味では李承晩は政治権力を志向する限り現実政治勢力として過去の親日勢力と接触せざるをえなかったともいえよう。そのような雰囲気は小作制を基盤としてきた南では当然であったといえるかもしれない。

しかしこのような雰囲気は6 ・ 25 を経ながら変わってきたのではなかろうかと思っている。嶺南地方はついに朴正煕(パク・チョンヒ)時代に入ってまるでかつての朝鮮時代の時のように政治権力を独占するようになったではないか。46年の10月1日のいわゆる暴動事件を引き起こした大邱(テグ)はいま見られるように保守的嶺南政権を支持する本拠となっている。終戦後急速に左翼に傾いたその反動とでもいおうか。
私は嶺南地域を考えながら韓国史または韓国戦争史の聖書的または信仰的解釈というものを考える。今やこの地域がこの国の政治や社会権力をほとんど独占している。また一方で湖南地方もそうであるといえるかもしれないが、その地域の過ぎ去った時代に対する我執ともいえようか、かつての統一志向という北に対する善意の共感の残影ともいえるものがある。私は一家をほとんど左翼として犠牲にされねばならなかった家庭出身の、今はあの世の人となったある教授が忘れ難い念願としていた左翼的ともいえる南北統一に対する郷愁のことを記憶している。そのような人びとそしてそれに共感している勢力が今も綿々と流れているのではないかと考える。自分の家族が左翼として犠牲にされた記憶を持っている人びとがどのようにして南の体制に対して満足して暮らしていけるだろうかと考えるのである。
北の金日成大学で出会った北において生活の場をさがそうとしていた南出身のいわば越北してきた教授と学生たちを思わざるをえない。彼らはまったく元気のない姿であった。その後、彼らは越北した共産勢力の中心まで失ってしまってどうなったのであろうか。ある意味では中東における部族関係と政治の問題に類似しているといえるかもしれない。そこに政治イデオロギーは付随的について廻ったといえるかもしれない。私は越北人士たちのことを考える時に、いつも小説家李泰俊のその優れた容姿を思い浮かべては嘆息をついている。
南下したわれわれは北において経験した苦しみのために、南の情勢を我田引水的に解釈し、ほとんど本能的に南の政治勢力に従って行ったのではなかろうか。そのような状況から南の勢力は6 ・ 25の戦争を経験してから李承晩勢力下においても自分たちの領土探しを決意したのではなかろうか。そこで北から南下した勢力は政権周辺から退き経済力も失うようになる。ここに嶺南勢力と湖南勢力の台頭そしてやがてこの二つの勢力のあいだに反目と争いが続くという政治舞台がくり広げられたといおうか。このような歴史的風土に対する描写は、書かれた歴史には現れない正史とはいえない正史であるといえようか。このために私は常に書かれた歴史の限界にぶつかるのではないかと思う。
そういう中で先にアメリカへの移民を決意したのは越南した少数勢力であったといえよう。彼らは心の片隅に北の勢力が南下すれば自分たちは生き残れないという潜在意識に近い恐怖感を持っていた。そのような意識に私もとらわれていたことを告白せざるをえない。私もそのような意識を持って、1950年朝鮮戦争が起こると死を覚悟してさまよった。そして家族については渡米することができればそれが救いの道であると考えた。1967 年にアメリカに留学することができた時も私はこのような考えにとらわれていた。一方では政治の正常化された韓国を望みながら、腐敗した権力に対する疑惑を感じ抵抗しながら、子ども達のためにはアメリカに留学させる道をさがし廻った。一方ではまともな国を夢見ながらもう一方では自身と家族の安全を求めたといおうか。子どもたちは海外に送っておいて一人居残って家族に対する心配などなく戦うという考えであった。故郷を失って心の置き場なくアメリカへの幻を抱いていたといおうか。韓国の独裁政権を支援するアメリカということで、あれほど批判し抵抗しながらも。
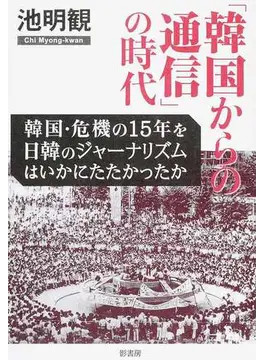
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
韓国を平常心を抱いてながめながら暮らすようになったのは、私にとっては1990 年頃からではなかったかと思われる。その時は20年以上も日本にいてから帰国した時であった。このような過去を思い出しながら今日はまた1950年代の朝鮮戦争のことをしきりに思うようになる。戦争のことだけではなくその頃われわれの歴史と人生に対する考えが全面的に転換したという思想史的観点からである。今や北の共産主義に対する恐怖はない。ここまで歩いてきた思想的な道をたどって見なければならない。この頃は特に世俗的な歴史と信仰の救済史的観点から見た歴史という二重史観とでもいうべき見方でいろいろと迷っている。このような二つの史観をこめて歴史を考えるということは許されないものであろうか。
1950年の 6・25 において南下する侵略を遮ってひとり残るようになった嶺南地方。それを私たちは世俗の歴史において実証的に記録しうるであろう。しかし、もう一方で信仰的な目においてそこだけが特別に残されたという事実をどのように受け入れるべきであろうか。それを神の恩寵によるものだと受け入れるとすれば、どのように考えることになるであろうか。その嶺南がこれから韓国の政治史において執権勢力を生み出すほとんど伝統的な地域になるとすれば、信仰的にそこにどのような解釈をほどこし、その地域だけではなく韓国全体にどのように伝えなければならないのか。世俗的権力を喜び、それに安住してしまうならば神のネメシスを呼ぶヒューブリス(極度の自尊心)に陥るのではないか。そのような歴史に対するキリスト教的メッセージとはどのようなものであろうか。
韓国の歴史のために新しい召命を受けた地域であるという責任意識を呼びさまそうとしなければならないのではないか。私に与えられた力をひとり享受するのではなく、それを奉仕の機会とする謙虚な姿勢である。そのような歴史解釈を行い、そのような使命を与える教会的メッセージがなければならないのではなかろうか。そのような大胆なケリュグマ(御ことば)で嶺南の教会は目ざめて行かなければならないのではなかろうかと思うのである。そのような道を進まなければ嶺南が見捨てられることもありうるという聖書的メッセージを謙虚な心で受け入れなければならないのだ。そのような信仰の道を選ばなければ、それは韓国全体の不幸ともなりうることであろう。そうであってこそ韓国にキリスト教的リヴァイバルが訪れてくるのではなかろうか。
聖書的に見れば苦難の時代に安全に保護された地域とか部族は新しい歴史のために使命を与えられるものと考える。それで60余年前の歴史をわれわれは今になってようやく正しく理解するようになったといえるかもしれない。過ぎ去った歴史の渦巻きの中で南北において先に逝かねばならなかった悲しい霊魂のことを思い起こしてかみしめる思いである。
旧約聖書を読みながら二重的史観という問題を一層考えるようになる。たとえばモーセの時代を聖書はそれこそ救済史的な観点からながめた。たとえばイスラエル民族がこのようなことをしたがために神は怒りを発したし、それでこのような不幸がやってきた。そこでこのようにしたら神はその怒りを解き祝福して下さったというのである。このように歴史をたんたんと世俗の歴史として記録したのではない。世俗史と救済史がとり混ぜられている。このような問題意識をもって韓国の解放とそれ以後の歴史に対してキリスト教がどのように理解し、どのようなメッセージを与えるべきかを考えなければならないのではないか。かつて咸錫憲(ハム・ソクホン)は日本統治下で『意味から見た朝鮮史』(注:1934~35 年に書き、終戦後加筆)を書いたではないか。このような思考がなければ、キリスト教のケリグマ(告知者が告知する行為やその内容)ではないといえるかもしれない。
われわれはこのような歴史的認識をキリスト教から排除し、世俗の世界史とは何ら関係なく、歴史的現実とは関わりのないケリグマを伝えようとしてきたといえるのではなかろうか。このような問題をいまどのように反省して解決しようとするのか。われわれは 1945年の解放、または1950年の6 ・ 25の戦争では信仰の立場から歴史を救済史的に解釈をしようとしたのであるが。その後半世紀以上の歳月の間われわれはそのような問題から離れて、歴史とは関係のない個人的な御ことばの方へと逃避してきたのではなかろうかと思われる。(2013年9 月28日)
≫知識人という生き方の終焉について≪
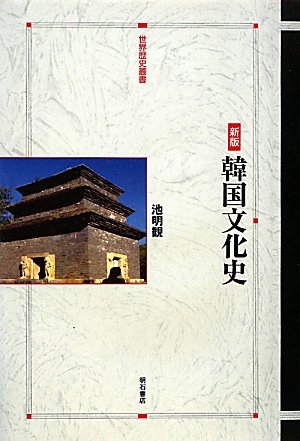
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
知識人の台頭とその終焉について思想史的研究をしてみたいという気がする。私は長い間知識人に対するリーズマンの定義を使用してきた。アイデアを職業としている人びととは違って知識人はアイデイア即ち理念の実現のために努める人びとであるといった。知識人の場合は社会的に批判的機能を果たさねばならないと考えたわけである。しかし今日においてはそのような区別も消滅したように見える。批判的機能に従事する職業の人々と特定する必要がないといおうか。
知識人消滅論が台頭しているといえるかもしれない。知識人という概念は封建時代の遺物として20世紀までようやく生き延びたといおうか。しかし政治にかかわる人びとのように短い想像力しか持っていない人とは異なる知的な人びとを歴史は必要としているのではなかろうか。たとえば北東アジアの今日における政治的または経済的得失を念頭に日中韓のことを問題にする人びともいるであろう。もう少し進んで北東アジアとか世界の平和と繁栄を展望しながら考える人びともありうるはずではないか。そのような将来のためには今日において利益を論議する立場に牽制力を働かせることも想定しうるのではないか。しかしそれだからといってこの二つの領域に属する人びとを明白に区分しうるのかどうか。実際、リーズマンも知識人とアカデミシャンを人間的にではなく機能的に区分して考えたではないか。
たとえば韓国の国家利益のために発言しうる場合と北東アジアの平和のためにもう少し先のことを考えながら発言しうる場合とが両立しうると考えることも可能ではなかろうか。今日の政治家という人物が世界平和論者であるということも可能であり、そのような両面性が同時性を持ちうると考えるわけである。韓国の国家利益について発言しながらもそれを超えて、ある意味でもっと後日の問題であるといえそうな東洋平和、世界平和について発言しうると思うのである。時にはこの二つのことが対立するようなことがあるかもしれない。それはリアリズムとアイディアリズムとの衝突ともいえるかもしれないが、もともと人間とはそのような矛盾を生きて行くものだと思うのである。
今日のあのような政治体制に抵抗することが平和への道であるともいえるし、ある意味では人間とはそのような矛盾をかかえて生きて行くのだといえるかもしれない。そのことはここではこのような選択をし、あちらではあのような選択をするとでもいおうか。政治に参加しては国家利益を優先させ、その一方で東洋平和を論じ、そこに参加することができるということである。人間と歴史の現実はそれほど困難なものであり、多岐多難であり、しばしばわれわれの想像を超えていると思う。ほんとうに誰が人類の前途を正確に予想しうるといえるのだろうか。
私は日本でよく使われている複眼的ということばを思い出す。一方では現実政治をながめながら、また一方では歴史の行き先をながめながら絶対的な人間倫理の立場を受け入れるのである。一つは今日の生活の立場から生まれる相対的な思考であり、もう一方は永遠の立場からながめるという、より絶対的な立場であるといえるかもしれない。一方は利己的な現実における私の勝利のために考えることであり、もう一方は利他主義的で理想を志すものであるとでもいえよう。
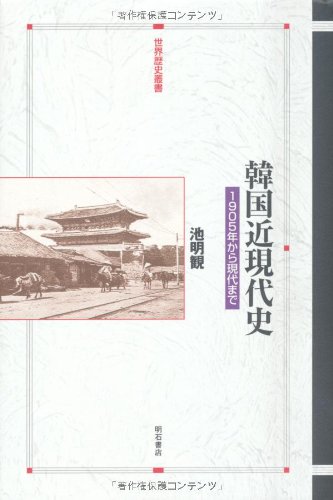
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
複眼的というのを二重的思考、多重的思考といっていいのかもしれない。a man of double thinking ということばをかえって肯定的に評価したいのである。かつての知識人が単細胞的であったとすれば、これはずっと複合的なもので、政治に参加して政治的利害関係においてのみ生きて行く単細胞的な人間ではない。政治においてはそれほど政治的な利害関係において考えながらも、その一方で知識人的だといおうか、正しい歴史を展望するとでもいおうか、そういった場においては異なった光に照らされながら対話に参加するということである。
知識人の立場といっていつでも現実政治に対して対決するというのではない。一人の人間がこのように多元的な判断をしながら、時によってもっとも賢明な立場を設定して現実的な判断力を発揮するというのである。そこで従来の知識人という階層、そのような相対的な概念はかつての階級的社会の遺物として消えて行くであろう。エリートと大衆という区別もなくなったではないか。批判的な役割はあっても、そのようなことをなす階層などは存在しない。単一のアイデンティティではなく、これからは一人の人間が多元的なロイヤリティを時には矛盾を感じながら担って行くのである。われわれは今まで現実政治に参加する勢力をあまりにも差別してきたのではなかろうか。
一元的なアイデンティティは去って行くのであろう。もともと人間とは家庭における人間、職場における人間、今日を生きる人間、永遠を求める人間、私としての人間、われわれとしての人間、そして動物としての人間、理性としての人間などなどと時と場所によってその姿を異にする存在ではないか。単一な人格とは虚像であり偽善であるかもしれない。それでは現代における誠実性とはなんであろうか。それはこの多種多様な人間をそのまま認めて生きることであり、そこに虚像を介入させ虚偽を装うことが無いという事ではなかろうか。単一な人間像に対する希望は虚妄であり、偽善ではなかったかとこの頃私は考えている。ラインホルト・ニーバーのキリスト教倫理を思い出しながら。彼はキリスト教倫理において絶対的倫理と相対的倫理を考え現実においては相対的立場をとらざるを得ないと痛みを語ったのではなかったか。
知識人、インテレクチュアルとは何であるのか。われわれはアメリカではインテレクチュアルは成立しないと、ややもすれば軽蔑するかのように語ってきたではないか。アメリカにおいては啓蒙主義の時代はなかった。ミシェル・フーコーが指摘したように、このような「消去」即ち「不在」に関する研究が重要である。われわれはそのようなインテレクチュアル不在の状況を持ったアメリカを軽蔑のまなざしで見ようとして来たのではないか。アメリカにそれがなかったということはアメリカは封建社会の存在とその崩壊過程がなかったためではなかったか。
だからこそアメリカには伝統的社会において見られた革命はなかった。特権階級がなかったのだから。独立戦争と奴隷解放のための南北戦争があっただけである。大衆の意識的な政治参加が初めからあったと言わねばならない。知識人問題に対する各国における比較研究が必要なのではなかろうか。そしてその知識人または知識階級とその階級にひきいられた革命的な階層の継続と挫折の歴史をたどってみる必要があると考える。ロシアにおける知識人階級の成立とその革命化そして執権後の乱れと独裁、このような歴史の流れを検討してみなければなるまい。知識人の背信のことも議論されなければならない。アメリカの歴史における知識人不在、革命不在の事も現代的問題として深く検討されるべきであろう。
韓国の歴史における知識人問題―もちろんそれは儒教的伝統社会とも関係するのであるが、それが3・1独立運動と関係したことも考えなければなるまい。それで知識人は歴史において栄誉ある位置をしめるようになったし、4・19とその後の歴史においても知識人と学生勢力は革命勢力となって登場したのであった。学生勢力は准知識人勢力といおうが、革命行動勢力といわなければならなかった。今日においてもその余勢は残っているといえるかもしれないが、段々とその勢力も衰えていくのであろう。しかし、革命が求められるとすれば、革命勢力化する可能性をもっとも濃厚に担っているのが、やはり学生勢力ではなかろうかと考えられる。マルクスが考えていた労働者勢力について革命と関連して云々することは今日においては現実的ではないような気がする。学生勢力は量的に巨大であるだけでなく質的にもっとも純粋であり、行動するとすれば全国民的心情から出発し、たやすく国民的共感をかちうるであろう。そのために私は今日においても特に学生勢力に対しては注目しなければならないのではなかろうかと思っている。(2013 年10 月31日)
今までの歴史から考えるとロシア革命においてみられたように、知識人を押し立てた革命勢力が現実において政治的に犯した誤りはあまりにも大きいといえるかもしれない。韓国でもおなじことがいえるのではなかろうか。そこでは時代と共に保守的大衆の隆起が続いた。彼らはかえって保守反動を選択したのであるが、それは革命にたいする絶望と失望から芽吹いた諦念をその根底に持っているのであり、政治権力に対するそこ深い軽蔑を抱いているものであろう。選挙の時代などに革命的な美辞麗句でも並べ立てられると、民心かえって遠のくであった。多くが、かえって朴正煕の方がよかったとその娘の方を選択したではないか。革命とか理念とかに対する冷笑主義の時代、反モラルの時代が現れているのである。
今日は政治における反理念の時代、非理念の時代であると私は考えている。モラルなどを口にすることもためらっているといおうか。韓国だけでは無くてほとんどすべての国において政治はそのようなスランプに陥っているのではなかろうかと思われる。1967年、私が初めてアメリカに来たときは、日曜日であればほとんどの商店が店を閉めていた。南アメリカの人々がやっているみすぼらしい店が一つ、二つ、開いている程度であった。この頃は日曜日に店を閉めていた商店を見ることはほとんどない。世の中はこれほど世俗化したと言えるであろうか。その傾向がわれわれの慣習、道徳、文化に同じようにしみこんできたであろう。そこにおいて静寂や絶対的善を求める宗教がいかに生き残ることができるというのであろうか。宗教はそれに抵抗するのではなく、ひたすらそれから離れて心の安らぎを求めるというのであろう。
大きな武力を行使する戦乱はない。戦争をいのちをかけて拒否しようとした高潔な人の事を思わざるを得ない。いまは日常的にそれこそ銃声のない戦いの中で私は決断することをもとめられているのであろうか。この歴史はわれわれに当然のこととして大衆への迎合を求めているといえるが、その一方ではなはだしい孤独の道へと強いるようである。求心力と遠心力が同時に働くのであろう。 踏雑の中の孤独といおうか。これが現代の文化というものかもしれない。大衆への道が平面的に私に押し寄せてくるともいえるし、孤独への道が垂直的に私に迫ってくると言えるかもしれない。そこに今日の知識人の人生というものがあるであろう。この先の苦悩に残り少ない日々を嘆息しなければならないといえようか。(2013年11月1日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
