この一冊
『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』(水野和夫著 集英社新書、2017.5)
「快癒の希望はないかもしれない」が
狭山市立水富小学校学童保育指導員 福島 肇
経済ド素人の私の紹介、読者の皆さんにはご迷惑かも知れないがやってみたい。本書の論点は多岐にわたるが、この紹介文では、まず著者の主張の基調と思われるところをほぼそのまま紹介し、その後、感想を述べたいzzz。
1.本書の主張の紹介
本書のキーワードは 利子率 蒐集(しゅうしゅう) 『中心/周辺(フロンティア)』 近代国家の消滅 閉じた帝国と地域政府 である
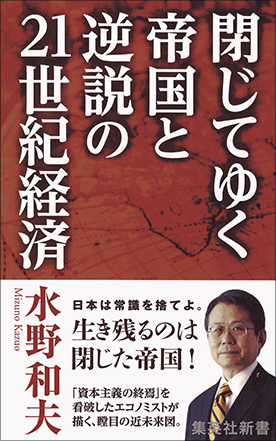
真の問い
イギリスのEU離脱、トランプ当選など世界は「閉じてゆく」プロセスに突入した。しかし、国民国家への揺り戻しの延長線上に「歴史の危機」を乗り越える解決策はないのではないか? それが本書の問いかけ。なぜなら、国民国家の基礎である500年続いた近代(主権国家)システムそのものが、800年の資本主義の歴史とともに終わりを迎えつつあるから。国民国家システムでは現在の危機を乗り越えられない。向かい合うべき真の問いは、「もはや国民国家を維持することはできない。ではどうするか」である。
閉じた帝国
著者は、「資本主義は100年くらいのタームで終焉を迎える」とするが、「それに代わるポスト近代はどのようなものか?」という問いにはこれまで答えなかった。最初に本書のテーマが述べられる。
「資本主義の終焉」という「歴史の危機」を乗り越えるために必要なのはどんなシステムなのか。・・・、このあと世界が100年近くかけて移行していくと私が考えるのは、「閉じた帝国」が複数並び立つという世界システムです。
では、その「閉じた帝国」とは何なのか、なぜそのようなシステムが生まれてくるのか。そうした問いに本書全体を通して答えていこうと思います。
「蒐集」の歴史の終わり
著者は、これまでと同様「長い16世紀」(1450~1650)と「長い21世紀」(1970~)との比較という手法で現在を捉える。5000年の金利の歴史のなかで長期間2%を切ったのは、中世から近代への移行期、1611~1621年のイタリア・ジェノヴァのみ。これが「長い16世紀」、歴史が動くサインであった。現在の人類最長の低金利は「長い21世紀」という歴史の転換期のサイン。1973年オイルショックが「長い21世紀」の始まり。10年国債の金利は1997年以来20年間2%を切ったまま。利子率(ほぼ利潤率)が下がったままということは、投資が意味を持たず、資本が増殖できなくなったということ。
資本主義が他ならぬ西欧で生まれ発展したのは、西欧には「蒐集」という概念があるからで、「蒐集」で維持されてきたのが西欧文明。フロンティアが完全に消滅し「蒐集」が不可能になった今、西欧文明と資本主義は歴史上もっとも困難な危機にさらされている。「長い16世紀」に起きた大転換は、「陸」の中世封建システム(イタリア、スペイン)から「海」の近代システム(オランダ、イギリス)への転換(「空間革命」)。
21世紀の超低金利は「実物投資空間」からの資本の蒐集が不可能になったことを示し、5000年続いた「蒐集」の歴史の終わりを示す。
国民国家では危機は解決しない
資本主義は成長出来ず、金融バブルとその破綻の繰り返し。バブルが弾けると、企業や金持ちが公的資金(国民からの税)で救われる。一方、賃金は下げられ解雇が増える。格差は益々増大中。格差が広がり中産階級が存在しなくなると、民主主義も成立しない。子どもたちも親の勝敗で教育の機会均等を奪われる。近代の教育は大失敗。資本主義の危機は、民主主義の危機でもある。
民主主義の必要条件は中産階級の存在であるのに国家は国民と離婚しグローバル化した資本と結婚している。資本主義が民主主義を破壊しているなか、私たちは民主主義をとるか資本主義をとるかという二者択一を迫られている。
資本の下僕と化した国民国家の枠組みでは、グローバル資本主義の暴走、それが生んだグローバル・ジハードを食い止めることは出来ない。
より遠く、より速く、より合理的に
近代資本主義の本質は17世紀科学革命で生まれた「合理性」と、産業革命(動力革命)で実現した「より遠く、より速く」。つまり「より遠く、より速く、より合理的に」の3つ。そして技術進歩教(社会のあらゆる問題は技術で解決できる)と成長教(成長がすべてを解決する)が批判される。
成長教・新自由主義の信徒は、日本では政府や日銀。リーマンショックや福島第一原発事故は金融工学や原子力工学の魔術性をあらわにした。それでも、成長教の信奉者が最後にすがる砦が「技術の魔術性」、技術革新。しかし、技術革新の時代はとっくに過ぎている。
なぜ「閉じた帝国」の分立なのか
テロリズムとゼロ金利の常態化は国民国家と資本主義からなる近代システムが機能不全に陥っている証拠。そのなか、1990年代登場したアメリカ金融・資本帝国、EU帝国を例として著者の「構想」が語られる。アメリカは連邦国家であり、従属的な国々を持つ。EUは「欧州連合」という地域共同体。
資本主義が終焉を迎えても、既にグローバル化した企業の経済活動を国民国家のサイズに一気に縮小することはできない。その一方、企業間の相互作用のマイナスの方が大きいため、地球規模の経済単位は大きすぎる。
「経済単位と政治単位が一致するのが秩序安定にとって最適なので、食糧、エネルギー、工業製品(生産能力)がその地域でそろう「地域帝国」のサイズの単位が、21世紀の経済単位としては最大となる可能性が高い」
「「長い21世紀」という混乱期を経て、世界は複数の「閉じた帝国」が分立し、その帝国の中でいくつかの「定常経済圏」が成立する。この理想に近づくことができた帝国こそがうまく生き延びていく。」
「地域帝国」と地域政府の2層システム
著者は、「閉じてゆく帝国」としてアメリカとEUに加え、ロシア、中国、中東の帝国化をあげる。これからは、複数の「閉じた陸の帝国」同士が必要最小限の条約を締結して、相互依存関係を形成する。
地域帝国のサブシステムとして国民国家よりさらに小さい単位(地域政府)が大半の企業の活動範囲となっていく。つまり、一方では、EUのように「閉じた陸の帝国」を単位として、安全保障や外交、環境問題への対応など、一国単位の主権で行うのが難しい事柄を帝国のような大きい単位の共同体で対応する。必要な食糧・エネルギーの自給も帝国単位でまかなえるとよい。他方で、人々の生活や企業活動は国家より小さな地方が単位。そこに「閉じた経済圏」をつくれば、その経済圏の中心都市に集まった資金は同じ経済圏に還流する。グローバル資本の収奪を防ぐためには、経済圏を「閉じる」方向に舵を切る必要がある。
主権国家(国民国家)は中途半端なサイズ。国際的な政治経済単位としては小さすぎるし、人々の生活単位としては大きすぎる。
EUを評価
これらの「帝国」のなかで著者はEUにポスト近代の可能性を強く見て評価する。なぜか? EUが何よりも経済圏を「閉じる」ことで近代の危機に対応していること。具体的には暴走する資本に歯止めをかけ債務危機の再発を防ごうと、金融取引税や金融行政の統合策「銀行同盟」などの新しい試み、EU委員会によるアップルへの追徴課税判断を行っていること。EU帝国は「陸の国」がほとんどなので、「実物投資空間」を基盤にしており、ウォール街に世界中から金を集める「電子・金融空間」(ITと金融自由化の結合でつくられる空間)を基盤とするアメリカ帝国と違い、利潤は働く人々に還元される。
日本の誤りとこれからについて
日本とドイツに、定常状態へ移行するための条件がもっともそろっている。理由は、低金利が世界でいちばん早くから続いているから。だが、日本の選んだ道は誤り。
日独の分岐点。日本はアメリカ金融・資本帝国に従属していった。一方、ドイツはアメリカに反旗を翻しEU帝国形成を目指した。日本も中国を除いた日本近隣の地域の地域帝国のひとつとなっていくべき。 「ゆっくり」とアジアの「地域帝国」化に取り組むという決断が必要。現在の東アジアで「地域帝国」の構築はありえないが、100年単位で考えれば、(東)アジアも大きく変容する。そのときに備えて日本ならではの「地域帝国」のビジョンをつくっておくことが重要。
より近く、よりゆっくり、より寛容に
但し日本が定常状態に移行するには3つのハードルがある。
1.財政の均衡 普通国債をこれ以上増やさないこと 毎年の国債発行をゼロとすること
2.エネルギーの自給 再生可能エネルギーのかたちで実現すること
3.「地方政府」を視野に入れた地方分権 日本を5つか6つの経済圏に分け、それぞれを極力「閉じた空間」にすること
「より遠く、より速く、より合理的に」(資本主義)を反転させ「より近く、よりゆっくり、より寛容に」とする。
①より近く グローバル化ではなくローカル化。株式会社は現金配当をやめてサービス配当に切り替える。利益は最小化で十分。そうすれば「遠い」株主は寄ってこない。地域住民が株主になり、会社がより身近になる。
②よりゆっくり 短期の成果を求めず、手間暇をかけて物事とつきあう態度。社会に「ゆっくり」出られるように教育制度を改める。教育ではリベラル・アーツを重視。「歴史の危機」においてこそ、リベラル・アーツが重要。
③より寛容に ローマ教会とルターの間を取り持つことに腐心したエラスムスが手本。キリスト教とイスラム教の関係を「合理性」で解くことはできない。
最後に著者は、ケインズのケンブリッジ知性主義=真と愛・美をあげる。近代が捨てた「愛・美・真」を人類史上初めて追求出来るのは、金利ゼロを実現し資本の希少性を解消した日本とドイツだけ。
2.本書を読んでの感想と評価
資本主義ではない「市場経済」
著者は多くの著書を新書のかたちで提供し、経済学の知識も難しいことは要求しない。とてもありがたい。
著者は本書で初めて資本主義ではない「市場経済」を提起する。定常状態という条件下ではあれ市場経済があるということは「資本主義の終焉」とは言えないのではという疑問も湧く。だが、資本とは増殖を続けることにその本質があるのだから、増殖しない「資本」の下の市場経済が実現できるならそれは、「資本主義の終焉」と言って良いだろう。
主権国家の消滅と中世的な「閉じた帝国」
本書の本題。果たして近代主権国家が消滅し、中世的な「閉じた帝国」群と地域政府という2層構造が、著者の構想のように実現するのか。著者は様々な「閉じてゆく」兆候を示す。だが、この2層構造は著者の展望である。
EUについて。私は、戦争の根源としての近代主権国家をどう「消滅」させるかということを、学生時代以来考えてきた。そこで、第2次大戦後のEUは、近代国家を相対化し、少なくともEU内での戦争を防ぐという面から評価してきた。著者は近代国家は「人類史上最大の誤り」とする。そしてEUを経済圏、政治的共同体として適度な大きさとして評価する。
近代主権国家システムは悲惨な戦争の歴史であった。従ってこのシステムが過渡的なことはごく自然に思える。それ以前の中世の帝国が併存する世界では、近代ほど戦争はなかった。特に、ヨーロッパを除けば戦争は少ない。理由は、それぞれの経済圏が閉じていて、交易や利害関係が限られていたことにある。「閉じた帝国」システムでは衝突(戦争)を避けることが出来るのは確か。
本書のパラドックス
私がいちばん感じたのは本書のパラドックスである。パラドックスは本書から自ずと分かる。近代の教育は大失敗。中産階級は先進国では没落し、新興国では生じない。民主主義は世界中で崩壊する。だとすると、誰が著者が説く、「閉じた帝国」の構想を実現するのか? 政治指導者の質は劣化し、資本家は終末期更に強欲になる、更には、食糧・資源争奪戦争が激化する可能性も大きいとされる。ケンブリッジ知性主義の「真」を得られるのは、富んだ親の子息のみ。99%の没落した人たちは、ろくな教育も受けられず、知とは無縁。著者は「健全な中間層がいなければ、「歴史における危機」を乗り越えられないのが歴史の教訓なのです。」(『世界経済の大潮流』)と言う。
そして、この中間層の消滅を本書で述べる。抑圧された人たちには指導者はいない。著者はリベラル・アーツを学んだ人が国の方向性を考える資格があるとする。だが、官僚や政治家が自ら世の中を変えることはない。富んだ親の子息のケンブリッジ知性主義に指導者を求めることは自己矛盾である。著者は自分の構想を実現する主体を示すことができない。
結局、私たちは、99%の没落した人たちに希望を見出すしかないのだろうか。低賃金、低年金のなか、消費者は最低限しかものを買わない。それは「資本主義の終焉」の役には立つだろう。しかしそうしたことは99%の人たちの意識にはない。小さな「閉じた空間」に生きる知識人と99%の人たちの間には「断絶」がある。
99%の没落した人たちは、劣悪な労働条件、低賃金、低年金(無年金)、社会保障の不全のなか、ランダムで様々な叛乱を繰り返すだろう。そのなかから、何が生み出されるか、それは誰にもわからないと言うしかない。
「(私に)2150年の世界がどうなるか分かるはずがありません」と著者は正直に言う。その通りだと思う。
「快癒の希望はないかもしれない」が
本書のあとがきには鈴木忠志の演劇、とりわけ、『世界の果てからこんにちわ』がでてきて、「日本が、父ちゃん、お亡くなりに」という台詞が出てくる。
「世界あるいは地球全体が病院である以上、快癒の希望はないかもしれない。しかし、いったい人間はどういう精神上の病気にかかっているかを解明することは、それが努力として虚しいことになるとしても、やはり現代を芸術家(創造者)として生きる人間に課せられた責務だと信じている」(『リア王』の演出ノート「世界は病院である」)
わたしは「芸術家(創造者)」のところを経済学者に置き換え、「快癒の希望はないかもしれない」が、資本主義社会の矛盾はどこにあるかを解明することが、わたしの責務だと考えるようになりました。(『株式会社の終焉』)
これを読むと、著者は変革主体の「不在」、そこでの知識人としての自分という立ち位置を自覚していると思える。新書で本を書くということは、それを踏まえた著者からのメッセージとも考えられる。
ひとりの教育に関わる者として、学童保育で子どもたちと遊びながら、子どもたちを待ちうけている世の中を考えると気が重くなるが、子どもたちに少しでも開かれた空間を与えたい。「快癒の希望はないかもしれない」が、一人の人間として出来ることをささやかにでも出来ればと思う。
皆さんはどのような感想を持たれるだろうか。
ふくしま・はじめ
1945年兵庫県生まれ。1971年東京大学教養学部基礎科学科卒業。小平錦城高校教員を務める。「教師は生徒から学ぶ」がモットー。私立国本学園理科教育アドバイザーに就く。創作科学読み物『光の探検』で1984年度東レ理科教育賞受賞。著書に『物理のABC』『相対論のABC』『電磁気学のABC』『パズル・物理のふしぎ入門』(いずれも講談社ブルーバックス)など。
この一冊
- 『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』狭山市立水富小学校学童保育指導員/福島 肇
- 『「教育」という過ち』前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子
