この一冊
『ものがたり戦後史――「歴史総合」入門講義』(富田武著/ちくま新書/2022年2月/1034円)
『抑留を生きる力――シベリア捕虜の内面世界』(富田武著/朝日新聞出版/2022年6月/1760円)
大きな物語と小さな物語の〈はざま〉にあるもの
記憶を紡ぎ、記録するということ
本誌編集委員 米田 祐介
「行方をば知らず無月のシベリアを」。ぼくの祖父米田一穂の句である。「新天地でたくましく生き生きとした俳句を作りたい」。俳人であった一穂は、ただその一心で青森県巴蘭甲地開拓団の一員として渡満する。だが、1945年5月、一穂は、36歳という年齢にもかかわらず陸軍の満州部隊に招集され、わずか一ヶ月間軍隊の訓練を受けただけで戦場にかり出された。終戦三ヶ月前のことである。
1945年8月9日未明、ソ連軍が侵攻。追われ、山野を彷徨うも捕まった。一方、一穂の家族もソ連軍から逃げる途中、幼い次男紘二は妻の背中で死亡、享年2歳。そのまま路傍に埋められた。長女教子もハルピンの避難所にて「内地のもちが食べたい」といって衰弱してはかなくも逝った。妻のとっておきの反物で作ってやった着物を着た姿で、麻袋へ入れられて今にも埋められようとしているとき、ソ連軍が来た。そのため教子は取り残され、土に埋められることなく避難所の空き地に捨てられたという。享年4歳。そして一穂は、9月18日、ソ連軍に拉致されイルクーツク第一捕虜収容所に収容されることとなる。酷寒、栄養失調、発疹チフス、重労働、そして帰国の目処が立たなくなった絶望。
なぜに、ぼくの祖父一穂は収容され辛苦をなめ、叔母にあたる教子さんにも、叔父にあたる紘二さんにも、もう、会えないのだろう。と同時に、けれどもなぜに、祖父は生き延びることができたのだろう。巴蘭甲地開拓団の渡満者は338名、帰還者167名、未帰還者18名である。これを見ても敗戦の悲惨な様子がわかる。引き上げて母村の駅に到着した時は、何れも泣くのみであったという。
こうした、一個人の、一家族の、一地域の、小さな物語。けれどもその切実な小さな物語は、大きな歴史や時代という物語のなかでどのような位置にあるのだろうか。そのような問いに対し、富田武さんの著作は広い視野から応え、陸続する〈生〉という出来事に像を結んでくれる。それはとりもなおおさず、大きな物語と小さな物語の〈はざま〉にある問いを立ち上げると同時に、「歴史総合」という営みの深淵にせまる地図を提供せんとするものである。以下、近刊二冊の読書エッセイを綴ってみたい。
* * *
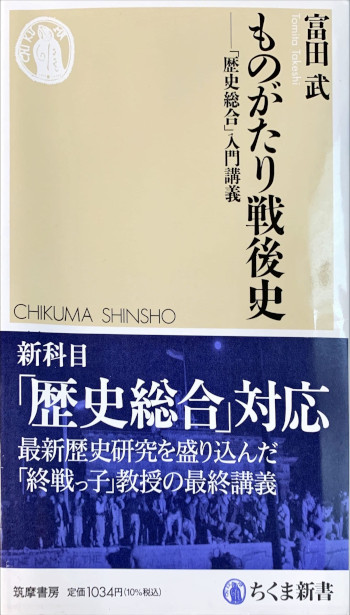
『ものがたり戦後史――「歴史総合」入門講義』(富田武著/ちくま新書/2022年2月/1034円)
「筆者は三月一〇日の東京大空襲以降、福島県田村群に『胎児疎開』中だった」。『ものがたり戦後史――「歴史総合」入門講義』(ちくま新書、2022年2月10日)のコラムからの一文だ。富田さんは、1945年生まれの「終戦っ子」。「戦後○○年」とともに年齢を数えられる。まさに富田さんの〈生〉の歩みとは、戦後史そのものであり、タイトルに「ものがたり」が付される所以であろう。本書は、大きな物語としての本論15講を収め、各講の合間に綴られる小さな物語としてのコラム15本は読み手の胸をうつとともに、豊かな年表や図版は理解をたすけるものとなっている。
さて、2022年4月から高校社会科科目が改編され、「歴史総合」が始まった。「本書は、高校で担当する先生方のために、さらに授業開始後は知識欲旺盛で、問題意識のある高一も念頭に、参考書として執筆したもの」であるとともに大学生にも社会人にも興味深い「戦後史再入門」となっている。論旨も明解であり、戦後政治史・経済史を立体的に編み上げたいわば「戦後総合史」だ。旧来、戦後史の柱といえば冷戦史であったことはいうまでもなく、ことに日米関係を軸に叙述されがちであった。だが、ロシア・ソ連史を専門とする富田さんの息遣いは、たえず米ソ、中ソ、独ソはもとより国際社会とソ連の関係、換言すれば、「その時」ソ連はどう動いたかが通奏低音となっており、日ソ関係へのまなざしは本書の白眉だ。
それはとりもなおさず、現在進行中のウクライナ情勢を歴史的文脈において考察するにアクチュアルな光を投げかけるとともに、「過去に眼を閉ざす者は、現在に盲目である」(ヴァイツゼッカー)ということを改めて認識させる。
ところで、ロシアのウクライナ侵攻をソ連の対日参戦と重ねあわせて、現在の報道に胸しめつけられているのはぼくだけだろうか。否、であろう。郷里青森県の叔父はウクライナ市民の惨状に涙していたという。8月9日のソ連侵攻、自らの避難体験、祖父一穂や逝った家族の記憶が回帰したに違いない。戦後は終わらないし、終わらせてはいけない。時代はめぐり抑留体験をもつ多くの方が鬼籍に入られたが、きっと日本全国に、いや南樺太や朝鮮半島ふくめ世界各地に〈痛み〉を感じずにはいられない「その時」を知る方々がいるはずだ。こうした小さな物語と大きな物語の〈はざま〉にあるものを想わずして、来るべき「歴史総合」とは何であろう。
ぼくは、富田さんの同書「あとがき」を読んでいてページをめくる手が止まった。「筆者は母や祖母から戦争の話を聞いていた(祖母の兄の一人は1945年7月にレイテで自決し、もう一人は8月にシベリアへ送られ、その9月に自分が生まれた)。本書は、筆者の教員人生の『最終講義』である」。
一個人の、一家族の、一地域の、小さな物語。だから、もとよりぼくが共感することすらおこがましい。けれども、こぶしを握りしめずにはいられない。富田さんその人が「胎児疎開」中に、ご家族はシベリアに送られた。この地上に生を受けたときは、酷寒のシベリアにいた。他方、いまも続くウクライナでの悲劇。BBCから流れる報道からは、お腹の子どもを必死で守ろうとする妊婦さんが、爆撃によってはかなくも逝った。誰かの大切な〈いのち〉が二つ同時に露と消えた。名も知れぬその胎児はどのような物語をおくっただろうか。〈いのち〉の係留点は、深く、深く、傷つけられ、いまなお傷ついている。
地上に生をうけた者の使命とは何か。時代は違えど、そうした〈痛み〉が富田さんをして、執筆にかりたてていると思わずにはいられない。武器という鉄の“重量”からの解放を求めて。ひるがえって、大きな戦後史から、もっとシベリアの方へ。大きな物語と小さな物語の「歴史」を「総合」してみたい。戦後○○年とは、とりもなおさず、抑留○○年である。
* * *
「『日本海が見えるぞ!』とだれかが叫ぶ。『日本海だ!』えっ、みなが立ち上がる。『だが、……』と一人がいう。『今ごろ日本海というのは、おかしいじゃないか。出発してから何日たったと思うんだ』そして、やがて海のような水面をもつそれは、バイカル湖に違いない、という者があり、まさしくその通りだった。まだ九月末というのに、湖畔に密生する針葉樹の群はすでに雪をつけ、湖面のさざなみも凍てついたように動かなかった」(伊藤登志夫『白きアンガラ河』講談社学術文庫、1985年)。
1945年8月、ソ連による対日参戦の結果、約60万人の日本軍将兵及び一部文民がソ連・モンゴルに連行され、数年間、長くは11年間、日ソ国交回復まで各地の収容所で強制労働に就かされた。死者約6万人。“暗い冬”(1945年10月から1946年4月の「最初の冬」)に約8割の方が亡くなった。そして蝋燭の火が消えるように静かに生命力を絶やす彼らが、老人ではなく20代、30代の青壮年だった点に特異性がある。きびしい冬がすぎ、陽ざしがぬくみ始めると郷愁はいっそう深いものになってゆく。
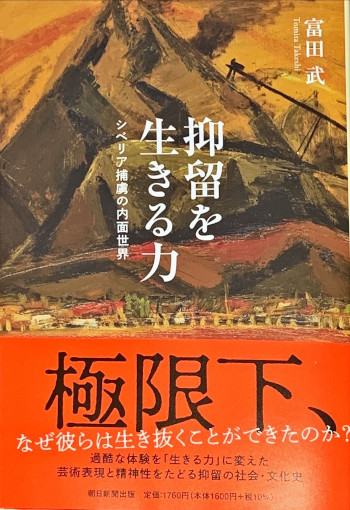
『抑留を生きる力――シベリア捕虜の内面世界』(富田武著/朝日新聞出版/2022.6.25/1760円)
“シベリア抑留”とは何だったのか。イルクーツク地区での抑留体験者である伊藤登志夫さんは言った。「ある人は、簡単に『捕虜収容所さ』、『強制労働の場さ』と言い捨てることがあります」(伊藤、上掲書)。だが、そうだろうか。もとよりソ連が、国民経済復興のための労働力とし自国に拘束=抑留したことは、ハーグ陸戦法規、ジュネーブ条約、そしてポツダム宣言に対する明らかなる違反である(このことは、富田武『ものがたり戦後史』第1~5講、制度・政策面から緻密に描いた『シベリア抑留――スターリン独裁下、「収容所群島」の実像』中公新書、2019年3版等に詳しい)。
だが、それだけのことだったのだろうか。大きな物語の一局面に還元されるだけの「悲劇」だったのか。もとより「美談」は禁じ手なのかもしれない。いわんやぼくにそれを語る資格はない。しかるに、である。先に「ページをめくる手が止まった」と書いた。だが折しもその頃、富田さんの筆は動いていた。止まってはいなかった。そのペンを握る手も、大地を踏みしめる足も。冒頭、祖父はなぜ生き延びられたのかとも問うた。はからずも、まさにそれに応えるような形で抑留体験者の内面に光をあてた『抑留を生きる力――シベリア捕虜の内面世界』(朝日新聞出版、2022年6月25日)がこのほど上梓されたのである。
富田さんは言う。「それに耐え抜き、生き抜いた強さはどこから生まれたのかがもっと語られてよい。苦難の体験を『生きる力』に変えたことを、後世にメッセージとして伝える著作が必要だというのが本書執筆の動機である」。2010年末、富田さんは「シベリア抑留研究会」を発足させ10年余り、旧ソ連と日本の公文書を発掘しながら読み解き、そこから構成した抑留の見取図に、膨大な日本人捕虜の回想記から得た情報をはめ込む作業を重ねてきた。しかし、文書を読むだけでは不十分で、抑留体験者からの聴き取りを行い、抑留現地(収容所跡地や埋葬地)を訪ね、旧ソ連の研究者、墓参協力者、古老にも会って抑留の実像をたえず想像、確認してきた。「フィールド・ワークもしなければ抑留問題は分からない」というのが富田さんの信条だ。
本書でも触れられているが、あるいは戦死し、抑留死した戦友に対する(自分が生き残ったという)罪悪感は生涯にわたって残り続ける。抑留体験を語らない方も多くいただろう。けれどもまた、家族には語らなくとも戦友、抑留仲間には胸襟を開いた方が少なからずいたという。それを個人史に埋没させてはいなけない。
シベリア抑留というこのいわば「異文化体験」から捕虜・抑留者が何を得たのか、また日本社会に何をもたらしたかは、実のところほとんど研究されてはいない。個人の体験という小さな物語を抑留史の文脈という大きな物語のなかに位置づけ、そこから、ぼくらは〈何か〉を学ばなくてはならないはずだ。信頼を築いたうえでの地道な聴き取りと、ときにロシア語から個人や集団の回想記を訳出し、史実との整合にも細心の注意を払った富田さんの息遣いに、身の引き締まる思いでいる。
本書は、収容所における広義の文化活動、帰還後の慰霊・墓参、残留者や未帰還者の一時・永住帰国を素材としながら、抑留を生き抜いた彼らの内面世界に踏み込もうとする試みである。いわば、「抑留の社会・文化史」であり、新たなる試みだ。彼らが残した絵画、音楽や演劇、俳句や短歌にもその内面が表現されているはずであり、そうした活動が収容所生活の不可欠の一部をなしたのである。換言すれば、そうであればこそ極限下、そのときの〈いま〉を生き延びることができ、それでも人生にYESと言えたのかもしれない。
本書に収められている珠玉のような一つひとつの小さな物語は星座のように配置され煌めいている。もしかしたら、人生に意味があるかと問うてはいけないのかもしれない。フランクルが言うように、ぼくらは人生から問いかけられる存在であり、その都度の〈いま〉がつきつける課題にたえず応答し続ける存在者だ。本書に綴られている魂のことばたちは、21世紀の〈いま〉という暗き時代を明るく照らす蝋燭となっており、富田さんはその燭台を用意してくれた。
紐解けば、祖父一穂はイルクーツク第一捕虜収容所に収容されている間も作句を続けていたと紹介がある。「はるかなる除夜の子の年数へけり」。収容所内では俳句会を起こし、作った俳句は軍隊手帖の切れ端に書き、紙縒にして服の縫い目にはさんで持ち帰ったという。ほんの少し〈何か〉がわかったような気がした。
* * *
ところで、このような文化活動を可能にしたものは何か。それは“シベリア民主運動”だ。ぼくらは戦後史においては日本国内でアメリカ占領軍が“解放者”のように振舞ったことは大きな歴史として知っている。だが、時あたかも同じ頃、『日本新聞』を通じてソ連はたしかに封建的旧軍隊からの“解放者”としての役割を果たしつつあったのだ。そしてこの新聞が、その後のシベリア民主運動を指導し、数年間にわたり全土の日本人捕虜の生活と運命に、大きな力を振るうこととなる。このことは、「歴史総合」という意味でも特筆すべきことであろう(ここで詳述することはできないが、のちに民主運動初期の指導者たちは、一転してブルジョア民主主義者とされ摘発闘争の”見本”として反動分子のレッテルを張られることとなる。いわゆる「つるし上げ」だ。そこには、冷戦の激化という背景があった。東西の緊張が、日本人をソ連側に引き入れようとする思想教育の強化となってあらわれても不思議ではないだろう。もはやソ連の意図を超えて、より以上に「急進化」している傾向すらある。ともあれ「歴史総合」という意味で興味深い点のみ指摘するにとどめたい)。
そうとすれば、シベリアでの民主運動はどの程度に、どのような仕方でそこを通りすぎた人々の内面に痕跡を残しているのだろうか。イルクーツク地区の抑留体験者である伊藤登志夫さんの『白きアンガラ河』(前掲)からことばをひろってみたい。何よりの成果は、「兵隊たちが無気力から脱し、生きるための活力をよみがえらせるきっかけとなったことだろう。気がつくと“暗い冬”はいつか過ぎ、戸外には暖かな日ざしが溢れていた。日々の作業や食物にも馴れるにつれて“死”はどうやらぼくらから遠ざかりつつあるようだった」。とりわけ内面にもっとも肯定的な印象を残しているのは、入ソまもなくはじまった兵隊の権力掌握、そしてサークルや麻雀、劇団とまんとう作りなど素朴で初々しい初期の民主主義だ。それがもたらした解放感と、成果としての文化活動や生活改善の実感であり、それに前後した軍国主義や急進的マルクス主義は、ほとんどいうに足りる印象を残してはいないという。最後に、現代の民主主義を考えるうえでも示唆に富むことばをひきたい。
「そうした大衆ひとりびとりの中に“体験”として染みこんでいった認識(いわば“思想の原形”ともいえるもの)は、たとい自覚的な論理の言葉として他に伝えられなくても、その日常生活に何ほどかの変革を、そしてその行動範囲内の他の人々に何ほどかの影響を与えずにやまない。それらの人間のささやかな変革が、量として増大しつづけることこそ“思想運動”というに価するものであり、またこうした表面には見えない思想の重みが、日本の民主運動を底から支えている、と言いうるのではないだろうか」。
やがて、ぼくらは揺れるタラップを踏みしめながら、一列になって甲板へのぼって行った。
まいた・ゆうすけ
1980年青森県生まれ。本誌編集委員。東洋大学・東京電機大学・湘南医療大学、県立高校ほか非常勤講師。著書に『歴史知と近代の光景』(共著、社会評論社、2014年)、『日本海沿いの町 直江津往還――文学と近代からみた頸城野』(共著、同、2013年)、『現代文明の哲学的考察』(共著、同、2010年)、『マルクスの構想力――疎外論の射程』(共著、同、2010年)がある。
この一冊
- 目からうろこの経済学、低成長下の策を解明IT専門学校講師・蒲生 猛
- 大きな物語と小さな物語の〈はざま〉にあるもの本誌編集委員・米田 祐介
