この一冊
『日本会議の正体』(青木理 著 平凡社新書、2016.7)
民主主義死滅への危機=日本会議の暴走
大学非常勤講師 須永 守
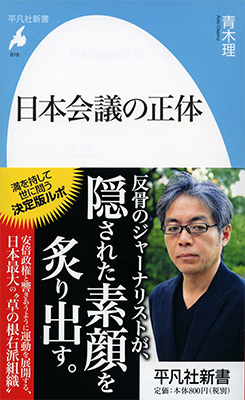
◆ 民主主義を死滅させるウィルス
本書のタイトルでもある「日本会議の正体」について、著者は結論として以下のように断言する。
「私なりの結論を一言でいえば、戦後日本の民主主義体制を死滅に追い込みかねない悪性ウィルスのようなものではないかと思っている」(245頁)
その悪性ウィルスが身体全体に広がりはじめ、ヘイトスピーチに象徴されるような低質な亜種ウィルスが拡散し、ついには脳髄=政権までもが蝕まれてしまった状況こそが日本社会の現状であると危機感を募らせる。その現状認識には全く同感であり、本書を読み進めながらその病巣の根深さにあらためて背筋が凍る思いをさせられた。
復古的かつ国粋主義的な目標を掲げ、安倍政権の中枢にまで強い影響力を及ぼす日本会議という存在に注目した書籍がこの3ヶ月ほどで立て続けに出版された。その中における本書の最大の特徴こそ、関係者への直接取材やインタビューを積み重ねることによって、その実像を描き出そうと試みた姿勢であることは間違いない。著者本人が告白しているとおり、組織周辺に漂う秘密主義と批判的視線や見解に対する警戒感、敵対意識があるなかで、これほど突っ込んだ内容の取材が数多く実現できただけでもさすがというべきであり、まさにジャーナリストの執念を感じさせる一冊である。それだけに、集録された証言の端々から、そして言葉にならない行間から、日本会議というヴェールに包まれた組織の生々しい実像が次々と浮き彫りにされ、まさに現在進行形の戦後民主主義の危機的状況を読者に痛感させるのである。
本書はまず「日本会議の現在」に注目し、1997年に2つの有力な右派団体が合流する形で結成された日本会議が、宗教右派からの資金面も含めた絶大なる下支えを受けながら、地方議会まで浸透している現状を明らかにしている。そこには学界、財界、宗教界からの錚々たる面々が役員に名を連ねる日本会議の右派ロビー団体としての影響力の淵源がいずこにあるのかを明確に示しているといえる。また、その日本会議の活動に呼応して中央政界でその政策実現に尽力する日本会議国会議員懇談会に第3次安倍内閣の閣僚の65%が所属し、首相側近である官邸スタッフほぼ全員が所属している現状は、決して看過できるものではない。
◆ 左派運動への対抗が生みだした「源流」
そして、そのような日本会議の現状に至る源流が明らかにされる。それが、全国の大学キャンパスが新左翼系セクトの学生たちに席巻されていた1966年、長崎大学教養学部で起きた右派学生による自治会選挙での勝利であった。その活動を主導したメンバーがやがて全国の右派学生組織を結成し、それを背後で支えた「生長の家」の方針転換を経験しながらも、現在の日本会議中枢メンバーに至る経緯は本書に譲るが、何より再確認されるべきは当時の左派運動との関係性である。それまで組織運動をするといった発想のなかった右派学生が、左派学生との対立の中で「ビラを撒こう」、「オルグしよう」といった組織化を学び実践するようになったと、当時を知る元「一水会」代表の鈴木邦男は証言している。また、右派学生運動に参加したメンバーの、現状に対する以下のような証言は両者の関係性を如実に物語っているように感じられてならない。
「われわれは同じことをただやってきただけで、逆に全共闘の運動などがなくなっただけなんじゃないでしょうか。むかし(運動を)やっていた人たちが、左でやっていた人たちの声が、すっかり小さくなってしまった。(中略)われわれはわれわれのやりたいことを50年やってきた。でも、右の主張に対するアンチテーゼがいつの間にかなくなってしまった」(241頁)
これらの証言を字義どおり解釈するならば、そもそも左派運動への対抗意識から、左派運動の手法を学び真似することから組織体制を整えていった右派運動が、左派運動の退潮によって注目を集めるようになり、結果的に肥大化していったとさえいえるのではないだろうか。そして、その一つの到達点こそが日本会議の現状であり、日本社会の現状であるとするならば、もはやその源流の源流(おそらく両者共にその評価を拒むであろうが)とさえいうべき左派運動は、現状を座視するわけにはいかない。
図らずも筆者は、日本会議が結成された遠因は1990年を前後した冷戦構造の崩壊と左派勢力の後退にあり、「反共」という最大の結集軸を失った右派勢力が再結集の必要に迫られ、1997年の右派2団体の合流に至ったのではないかとの見解を示している。その結果、新たな組織=日本会議の掲げる結集軸は「反共」ではなく、一種の「原点回帰」として①皇室の尊崇、②憲法改正、③国防の充実、④愛国教育の推進、⑤復古的な家族観の重視という5つの柱に集約された。それはまさに、失われた「反共」に代わる新たな結集軸として、「戦後民主主義」そのものが標的とされるに至ったといっても過言ではあるまい。
そして、以上のような筆者の推測が正しいとすれば、「反共」という最大の結集軸を喪失し、暴走をはじめた日本会議が次の標的と定めた「戦後民主主義」を守るためにも、左派勢力の再生・再建が強く求められるということになる。
◆「抗毒素」としての左派再生を求む
しかしながら、左派勢力の再生・再建が容易ではないことは言うまでもないし、単なる懐古主義や先祖返りに矮小化されてしまったのでは目も当てられない。では、どうすれば良いのだろうか。冒頭に引用した「日本会議の正体」を「戦後日本の民主主義体制を死滅に追い込みかねない悪性ウィルス」に例えた筆者の言葉を反芻しながら、一人の劇作家の言葉を思い出した。敗戦後、戦争協力に至った自身の過去と対峙しながら、左派でも右派でもない「第三の道」を求め続けた劇作家三好十郎は、真の知識人のあるべき姿として社会の「抗毒素」となることを提起していたのである。
「真の知識人とはたえずノイローゼにおびやかされつつもどこへも脱出せず、それに耐えて病的なノイローゼにはならず、自分の属している社会全体を、どんな種類の絶対主義にも渡さぬための抗毒素として存続しつづける者のことだ」(「知識人とノイローゼ」、『読売新聞』1954年11月11日)
日本社会全体が悪性ウィルスに蝕まれつつある今だからこそ、三好が求めた抗毒素としての知識人一人一人の役割だけにとどまらない、より大きな効能を発揮し得る抗毒素として左派勢力の再生・再建が求められるのではないだろうか。
最後に、本書は日本会議分析の嚆矢ともいうべき菅野完『日本会議の研究』(扶桑社、2016)や安倍政権と日本会議の一体性を明らかにした山崎雅弘『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社、2016)、日本会議の地方における草の根的な活動実態にせまった上杉聰『日本会議とは何か』(合同出版、2016)などとも補完的であり、併せての一読をおすすめしたい。
すなが・まもる
1976年生まれ。複数の大学で非常勤講師をつとめる。専門は日本近・現代思想史。東京都練馬区在住。
この一冊
- 『なぜヨーロッパで資本主義が生まれたのか』ベーシックインカム・実現を探る会代表/白崎 一裕
- 『日本会議の正体』大学非常勤講師/須永 守
