連載●池明観日記─第25回
韓国の現代史とは何か―終末に向けての政治ノート
池 明観 (チ・ミョンクヮン)
》「東洋平和」における韓国《
この民族は朱子学的儒教のせいであろうか、思想とかイデオロギーとかに固執しがちである。しかし、近代以降何度も転向を経験したといえるかもしれない。植民地時代があったし、終戦後は南における米軍占領下における性急な左傾化、しかししばらくしては南の体制とイデオロギーへと回帰したのであった。こうしてこれまでいろいろな生活原則が放棄されたといおうか。そしていまはこれまでのすべてのイデオロギーが消滅した時代に直面しているともいおうか。そのすべてを超えるヒューマニズムへと復帰せねばならないといえるかもしれない。

私は創世記11章のバベルの塔、「全地の言葉を乱された」という言語の起源といえる歴史、その神話を思い出す。その後近代に至っては国家主義の台頭とともに各国の言語がほとんど神聖視されたといおうか、標準語として確定されたのであった。そこで国家の中心的な言語ではない地方語ともいうべき言語は消滅の運命をたどった。そして国語は尊重され、それを美しく保とうとしてきた。それに文学はなんと大きな役割を果たしてきたことか。そのたのために文学者たちは民衆の尊敬をかちえた。日本統治下われわれがハングルを守ろうとして血のにじむような努力をしてきたことを思い出さざるをえない。
今日に至ってわれわれは英語と世界各国の国語という問題を深く考えざるをえなくなったのではなかろうかと思われる。ヨーロッパにはラテン語の時代があった。それは宗教の言葉として生きのびてきたが、いまではカトリック教会においてすら放棄されつつあるように見える。ラテン語は宗教的言語として残り、一般的にはただ書かれた言語に過ぎなかった。その後のヨーロッパではフランス語が国家間の外交的用語であった。同じような現象として、東アジアにおいては各国国民が日常的に出会うということはほとんどなく、漢字のように主に書かれた言語が知識人の間に通用したといえるであろう。しかし今は外交関係においても英語が支配的になっている。そこで英語は各国の人々が日常的な出会いに使われる言葉であり、これからは地球化した今日の世界において、バベルの塔において言語は分裂して以来、はじめて人類の言葉を一つにしつつあるように思える。
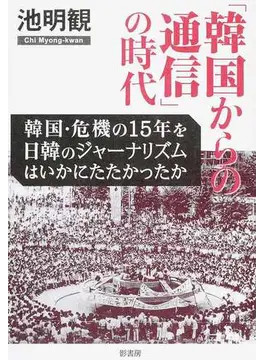
『「韓国からの通信」の時代』(影書房、2017年)
各国の国語が地方語になる時代となればそこの言語はだんだんと衰退していくのではなかろうか。コンピュータの日常化によって各国固有の国語は衰退していくのか。単一言語へと長い旅がはじまっているのかもしれない。ここにおいて各国固有の国語による文化、特に文章とそれによる文学も衰退の道をたどるようになるのか。そこにまた印刷文化も衰退していくのか。必要がなくなれば衰退していく運命を言語も避けることができないのではないか。アイヌ語、先住アメリカ人の諸言語などすでに多くの言語がほとんど跡形もなく消えていったではないか。
ナショナリズムの衰退による国家的な近代言語の衰退という現象は避けられないように見える。私も朴景利(パク・キョンリ)、趙廷来(チョ・ジョンネ)の小説を読みながら、韓国南部東西の地方語を読み下すのにどれほど苦しんだか知れない。時には理解することができないので放棄しなければならなかった。このような地方語の衰退とそれからは国語そのものの地方語化と衰退がやってくるのであろうか。アメリカに留学してきた学生たちの間では英語を日常的に使いながら自国語は土俗語のようになりつつあるのではなかろうか。アメリカで生まれ育った子どもたちにおいてはすでに母国語は使用しない言葉になっているではないか。このような言語的変遷をわれわれは当然のように受けいれねばなるまい。その中で私が「政治日記」のようなものを出版しようとすることは、間もなく消えてなくなることを知りながらもあえてなすエレジーへの感傷といおうか。元々人間の行為とはアレントがいったように一回的なものであり、すぐ消えてなくなるものではないか。
キェルケゴールが神との関係で一回性の言語にも永遠性を与えようとしたことが思い出される。過去は現在に流れいり、未来は現在においてはらまれるのであるから、過去、現在、未来が現在において一つの連なり、神と結びつくのであるから現在は永遠性を帯びるものと彼は考えようとしたのではないか。しかしそれは消えていく現在が抱えている虚無と葛藤に身もだえしたことではなかろうか。それで現在に意味を与える実在という言葉を哲学は編み出したのではなかったか。(2013年7月11日)
アメリカで2009年にヒットしたというロック・オペラ「異邦人として生きること」(Passing Stranger)というビデオを見た。英語が聞き取れないので詳しい内容は知らないが、1970年にロサンゼルスに暮らしていた黒人青年がヨーロッパに向かったが、さすらいの果てにアメリカに戻ってくる話である。そこで終わりには、「イッツ オーライ」(It's all right)を何度も繰り返す合唱で終わる。われわれは日本統治時代においてフィナーレを悲劇で終わるわが国の小説をたたえながら、ハッピーエンドで終わるアメリカの映画を浅はかな楽天主義だとかいってあざ笑ったことか。しかし今はわれわれもハッピーエンドを楽しんでいる。アメリカの黒人たちがハッピーエンドで終わるような歴史をいつから受けいれるようになっただろうかと考えざるを得なかった。1960年代の人権運動によってアメリカにおける彼らの人生を受けいれるようになったのだろうか。そのような彼らの思想的な反転はアメリカの文化に活力をもたらしてくれたのであろう。どうしてかわれわれの在中、在日の同胞の歴史からはまだ「イッツ オーライ」という肯定の叫び声が聞こえてこないような気がしてならない。
北東アジアの問題をまた考えるようになる。ヨーロッパに比べると主にただ日中韓、3カ国の問題であるだけなのになぜこのように難しいのだろうか。ヨーロッパではあの数多くの民族、数多くの部族が長い間葛藤してきたがわれわれ東アジア人たちの場合は中国内における葛藤が主で、日中韓の間では蒙古、契丹、清などの塞外民族との葛藤、壬辰倭乱(文禄・慶長の役)における対立があった程度ではなかったか。しかし今日においては北東アジアの政治状況は統合の問題になるとヨーロッパに比べてずうっと困難で後進的であると思わざるを得ない。国家連合における北東アジアの後進性とでもいおうか。
古い中国の大中国構想がまだ生きているような気がしてならない。朴槿恵がこの度中国に行って丁寧なもてなしを受けたと、韓国の新聞が騒ぎ立てているのに、中国は去る7月9日北京にある中国偉人蝋像館で金正日の蜜蝋贈呈式を行ったというではないか。北側の人士を招待しては「偉大な領導者金正日同志蜜蝋式」というプラカードを掲げて行事を行ったというのである。そして金正恩が秋に北京を訪問するようになるであろうと韓国の新聞は騒ぎ立てている。中国の伝統的な対朝鮮半島政治手法であるといわざるを得ない。
中国の大国としての周辺国家支配の手法というものはいつもそのようなものであった。北東アジアにおいては宗教的支配秩序は存在しなかった。中国の影響下にありながら、朝鮮半島では心の中では彼らに対する軽蔑の心を育んでいたようである。日本に対してもそのようであった。そのためにこの国民はこの二つの国に挟まれてねじれた国際感覚を持たされたといえよう。朴槿恵に手厚いもてなしをしたかと思うと、その翌日には金正日の蜜蝋像云々という二重外交であり、北東アジアの未来に対する倫理感覚とか歴史感覚とかは中国にはない。真の友好のために、北東アジアも新しい関係のほうに向けて三国の関係を構築しなければならないという姿勢はそこにはないと思えてならない。日本を新しい北東アジアに向けて国民を説得するしようという理念的姿勢など中国はもっていない。韓国が北東アジア三国の間において平和の架け橋の役割をなすなどはまだまだはるか遠い話のように思われる。こうして三国の関係は歴史の方向に反していまだに逆転しているように見えてならない。このように新しい歴史的情勢に今度も主体的に対応できないのではないかと思われる。
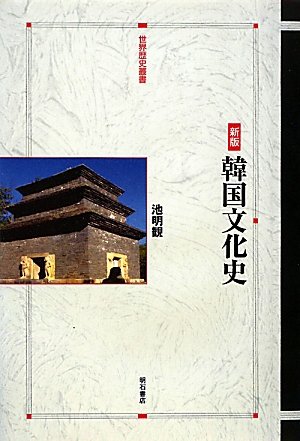
『韓国文化史 新版』(明石書店、2011年)
それで私は知識人の脱政治化というのを考えるのである。北東アジアの国民はいかに優れているといえようか。北東アジアの知識人はかつて国家の力が脆弱で、外国侵略におびえている時、とても民族主義的な発想で抵抗せざるをえなかった。しかし今の政治勢力の下では脱政治化の道を選択して、アジア市民の連帯を掲げ政治を超えたヒューマニティーを求めねばなるまい。古い民族主義の下で漂っている政治は放置しておくのだ。そのような政治に迎合するのは知的連帯がなすべきことではない。それにもかかわらずまたはそれを解体させるために知的な連帯は活性化されねばならないと思うのである。まず中国はそこまでいっていないといえるかもしれないが、日韓の市民は政治的に歴史上はじめて政治を超えているといえるのではないか。
そこで私はたとえば対日本の姿勢においてかつての日本統治下のことを前提とした反発の姿勢を超えてこれからの未来に向けて正義の姿勢を強調するのである。今や日本のあのような政治的姿勢をかえって憐れみの目で眺める。東アジア三国の平和の時代に向けて国民の力を集中し、互いに対話を交わし、協力する姿勢を打ち立てなければならないと思うのである。危機であれば危機であるほどこのような知識人の連帯が求められるのではかなろうか。あのような政治的姿勢を遠くから眺めながら、われわれは平和のメッセージを交わしあうのである。これがEUを可能にしたヨーロッパの知識人の姿勢ではなかっただろうか。これを今日における北東アジアの知識人の姿勢として確立していかなければなるまい。あの騒々しい政治に目をやりながらも、われわれは別に国民を説得し、新しい交流のモデルを提示しなければならないのではなかろうかと思うのである。
それがゆくゆくは国益にも符合することとなるのではなかろうか。特に北東アジア両大国の間で韓国が主体的に生きていくということとはそのようなことではなかろうか。そのような意味においても朝鮮半島における平和の思想は絶対的なものであり、それは超政治的に考えることであるとはいえないか。近代国家主義の恐ろしい係累からは抜け出してみたいものである。このような意味での東洋平和論というのは両大国に挟まれていたこの国民の歴史的思考、特に近代以降の思想ではなかったかと思うのである。(2013年7月14日)
「出エジプト記」第34章第12節において「あなたが行く国に住んでいる者と、契約を結ばないように、気をつけねばならない」とイスラエル民族に対する選民の思想が現れる。ここにおける神の啓示は具体的な対象をもつものであった、それは万民に対する道徳法則のような一般啓示とは異なるものである。特殊啓示はその時代にはイスラエル民族に与えられた。そのような特殊啓示は歴史の場が異なってくればどの民族にも臨んでくるものといえよう。今日の歴史における選民とは、人とは異なる苦難を背負って謙遜な姿勢で歩みを続けながら、あえて犠牲のいけにえになるという今日この時点のおいての民族のことであろう。
またこういうことも考えられる。「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」(マタイ5章44節)という言葉を今日互いに張り合っている現場に向かって諭す言葉であるとのみ解釈していいのだろうかと思った。アメリカに来て間もない時のことであるが、妻が芝生に混じっている雑草を抜き取っていると、隣の白人のおばあさんが通りかかり、近寄ってきて外国生活は難しいでしょう、どんなことでもいいから助けてあげるからいつでも話に来てねといわれた。またある日私がスーパーに行って帰りに高級老人ホームの前を通っていると、ある白人の男が私に近寄ってきては、明日はこの老人ホームのホームカミングだから、誰も負担なしにお昼を一緒にするのだから参加してほしいというのであった。その老人ホームが異国人を歓迎するというのであったであろう。白人のみがはいってくるところというよりは異国人が混じってくることがかえって望ましいと思うのであろう。
アメリカの白人がこのような開放的な姿勢をもつということはどこから来たのであろうか。1861年に始まった南北戦争。それから1世紀半でこのように成長したということではなかろうか。その姿勢が今日におけるアメリカの世界に対する姿勢に適用されるとすれば、われわれはやはりアメリカの先駆性を認めざるをえないのではないか。人は皆歴史とともに変化しながら、生きていくといわねばならない。ここで英語が世界語にならざるをえないようになり、急速に世界に広まっていくのではなかろうか。いまだに白人主義が時には問題になるといわざるをえない状況が続いているとはいっても。(2013年7月27日)
スタンダールの『赤と黒』(1830年)を読んだ。悲恋の物語であるといわなければならないが、今日のわれわれの感覚からはほど遠い小説であるといえよう。フランス革命そしてナポレオン戦争の時代を経てもフランスはこのような貴族社会であったのか。それだからフランス革命の時代は一世紀以上も続かざるをえなかったといえよう。韓国においても朴正熙の時代が今日までも続いているといえようが。
スタンダールの時代においてもフランスではこのように腐敗が蔓延っていたというのであろうか。韓国がアジアにおいてもっとも腐敗のはなはだしい国であるという。収賄の横行というのであろうか。1960年代であっただろうか、その頃は区役所で戸籍謄本を取るときも、海外旅行のための身分証明書を取るときも賄賂の金額が決まっていたようであった。身元証明の場合は10万ウォンが通り相場だったと記憶しているが、ニューヨークのユニオンに行くとき、腐敗と戦わねばと力んでそれを拒否していたことが思い出される。最後は警察の担当官が私たちの生活補助費ではなかいという言葉に妥協したというつらい経験をした。これは歴史の進歩という過程にあった一つのエピソードであるといえようか。官公吏の清廉潔白さと社会発展との関係といおうか。経済でいえばいまは韓国は世界十大国の中に入るとかいわれながらもである。(2013年7月30日)
》趙廷来先生に《
趙廷来先生! 先生の作品『太白山脈』をみな読み終えました。力に余る読書でありました。1985年から89年までにわたって執筆された大作だということですね。1946年の大邱10・1暴動事件から始まって1948年の済州島の4・3事件と5・10国会議員選挙反対闘争などを経ながら、1950年の6・25に続く「民衆勢力」の闘争において民族勢力が敗北していった過程を生々しく描いたといいますね。終わりの第10章の38節が「休戦線に変わった38度線」というものです。
こうして話題を残して海外にも翻訳紹介され、また法廷闘争にまで持ち込まれた大作だと知られています。朴景利先生は『土地』という作品で主として日本の統治下の時代を描いたとすれば、先生は解放後特に左右の対立と葛藤そして国土分断の時代を描いたということになりますね。韓国の現代史を先生はどのように描いたのでしょうか。先生の韓国史に対する歴史意識を深く掘り下げてみたいのですが、それはやはり私の能力を超える作業のように思われます。作品構成と文章表現においては私は朴景利先生の『土地』のほうを取りたいと思うのですが。
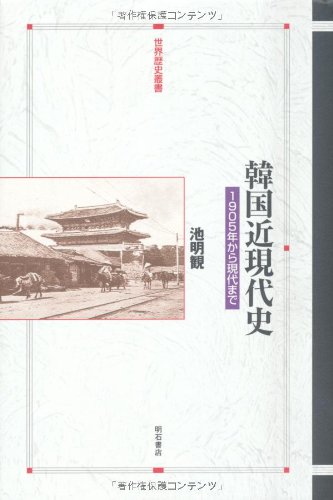
『韓国近現代史ー1905年から現代』(明石書店、2010年)
先生の歴史観については多少問題を提起したいと思います。とりわけ南または北から追放された人々の歴史意識を中心にしてです。先生は北から南下したキリスト教の牧師と南北青年会などを告発しましたが、これからはわれわれは北に行った人々、南に来た人々に対して総合的な評価をしなければならないのではないかと私は思います。北にある金日成総合大学で私は南から北を選んでやって来て大変な挫折感を反芻している教授と学生たちをみてどれほど多くの悲しみを味わったか知りません。そこには李泰俊(イ・テジュン)も金史良(キム・サリャン)も李康国(イ・ガンクク)もいましたが。そして今ではその名前を思い出せない多くの人々がいました。それに比べれば南下した人々は李承晩時代にあまりにも安易に韓国の地で相応の位置を占めたといいましょうか。いうまでもなく多くの人々は6・25後には南において権力を求める南出身の勢力によって追放されるようになりますが、そして南の地は主に嶺南と湖南とが政治的に角逐、争う地となるのではありませんか。
そのような状況に対して先生はこの小説の終わりにおいて北において粛清されてそれこそ死に追いやられてしまう南出身の共産主義者たちに対して奇異な歴史的解釈を下して北に生き残った権力を擁護しただけではありませんか。一言で言えない北の6・25における失敗に対して誰が責任を負うべきか。それは北に行った南側の共産主義者ではないか。それで北の勢力は南から来た共産主義者たちに苛酷な懲戒を加えるほかはなかったといわれたのではないでしょうか。そこで彼らは死を逃れることができなかった。政治の偽善と残忍を糾弾しながら人生無常を嘆くことなどなしに、それは「歴史的選択」であったと弁護しようとされたのではありませんか。それで彼らは6・25の南側の失敗の責任を負って懸命に死の道を選択したとでもいうのでしょうか。これはあまりにも安易な歴史的解釈ではなかろうかと私は思いました。
そのような安逸な歴史的解釈ではなく、南北がともに政治という悪霊に捕らわれて歴史的残忍の罪を犯してしまう現代の悲劇を展望する文学的立場などは不可能なものであったのでしょうか。この作品の最後に至って智異山闘争を続けてきた幹部朴トゥビョンが呟く言葉「正義の歴史のために新しく始める戦い」という言葉がありますが、「正義の歴史」とは古い政治体制を夢見ることによって可能であるのではなく、新しい国民の時代、すなわち国民の民主主義的な理性が歴史に関与し、歴史を決定する可能性が開かれる時代が来てこそ可能なものではないでしょうか。それが完全に花咲くようになるということは歴史の進歩、歴史の理想といわねばならないし、永遠の「イデー」ともいうべきであると私は思うのです。
少なくとも一つのことだけは強調しておきたいと思います。南北の政治とそれから追放された人々を一緒に見る視点、そこに現れてくるはずと思われる人間的な歴史観をわれわれはいつになったら紡ぎ出すことができるでしょうか。極限的な対立ではなく、喜んで席を共にして現実的に可能なことに合意することのできる理性的な姿勢とでもいいましょうか。少なくとも米ソの占領とその政治的利害関係に加担して踊るということのない姿勢ですね。
しかしわが国に関係することではあっても国際問題であるというのですから国粋主義的民族主義とでもいうような立場で解釈できるという幻想は許されないものではないでしょうか。「民族勢力と反民族勢力」という図式的な区別は危険なものではないでしょうか。歴史体験の差によって、これからいつかはやってくるい違いない南北統一を現実的に追求しようとするとき、私は単純な政治勢力の間における対立ではなく国民対立が起こってくるのではないかと恐れています。朝鮮朝の時の南北の差別と対立から、今日に見るような恐ろしい対立、そしてそのような様相を政治勢力の間においてのみ見るのではなく、国民全体においていわば民主主義的な平面においても見るようになるとすれば、どんなことになるだろうかと思うのです。
そして「人民の敵」「米帝の手先であり、李承晩徒党の走狗たち」という単純化されたものではなく、世界政治におけるアメリカという観点が今日においてはとても必要ではなかろうかと思います。6・25という朝鮮戦争に参加した私は米軍将兵とアメリカ顧問官に対して趙先生とはあまりに異なる体験をしたことを付け加える必要があるかもしれません。私自身の拙い自叙伝『境界線を超える旅』に少しばかりそのようなことを書き残したということも付け加えておきます。『太白山脈』という作品に対して全面的に論じることは老齢の私にとってはかなわぬことではないかと思います。ここに比較的短い文章をいくつか並べて考えてみましょう。主にアメリカに関する文章です。
「アカの野郎たちを容赦なしに処断し根絶させることには結局西春(ソチョン、北から南下した反共勢力である西北青年会のこと)の外には信用できませんよ」(第1巻、順川から)
「アカの思想でいえば北は桃で南は西瓜ですよ。南でも全羅道と慶尚道は大変な特製西瓜ですよ」(第2巻、北出身の警官の話)
「黄金万能を掲げた彼らの覇権主義を敬遠し、スポーツに熱狂する彼らの単純な行動性を軽蔑しながら警戒した」(第3巻、無教会主義者ソミニョンのこと)
「彼らは帝国主義の暴力と奸悪性を先頭にしたわが民族の生活を破壊する自主性を強奪した」(第4巻、智異山ゲリラ指導者・廉サンジンの見方)
「アメリカは結局巨大な火力を動員して一民族が自らのために行こうとする道を自分たちの利益のために遮り、八つ切りにし、挫折させていた」(第5巻、米軍の仁川上陸について)
「インディアンの立場で見れば、彼らは間違いなしに侵略者でありながら虐殺者たちであって、黒人の立場から見れば彼らはまた確実に生命を奪う強盗であり、搾取者であり、真の意味において彼らはまた許すことのできない種族殺害犯であり、人間加虐犯どもであった。そのような彼らには韓半島という狭い土地は彼らの国家的自慢心を、その地に住む黄色の人々とは人種的優越感を充足させるのにまたとない舞台とならざるをえなかった」(第7巻、韓半島に対して)
「やはり韓半島において使いものといえるにはただ一種類だけだよ。女の性器を他にしてはあまりに未開で野蛮的で味気がない」(第7巻、米軍特務の話)
「そのような李光洙という者の亡霊が日本野郎たちではない米国野郎たちを通してまた現れるのを金ボムは耐えられなかった」(第7巻、このように「日本野郎」が教えてくれたという。作家は1945年8月から1953年8月までを「民族自主国家樹立のための努力時代」とし、その後を「民族統一推進の時代」と規定。そこでは民族主義という言葉は使われていない)
「アジア人は米国人と同等ではない。アジア人は人間ではなく人間以下の存在だ」(第7巻、このような教育を受けたとイギリス軍人が指摘)
「敵と民間人を区別することのない彼らの無差別爆撃はそれこそ自分達の利益を確保するためには手段方法を選ばない帝国主義的残虐であり悪辣さであった。ただ彼らの無慈悲な焦土化作戦に拍手を送っている人間どもはすでにソウルを離れた李承晩政権を取りまいて、得をしている親日反民族勢力の者たちと新しく起こってきている機会主義者たちだけであった」(第8巻、居昌事件について叙述した後、釜山に上陸した人々に対して)
「爆弾を運んできてははき出せば出すほど景気がよくなるというのだからヤンキーたちは浮かれているよ。戦争がいつ終わるか誰も知らないのです」(第8巻、そのような戦争観、鼻高い連中が勝手に女たちを辱めたがっているという世態描写)
「君のお父ちゃん殺したのは、鼻高の米国野郎たちだよ。米国野郎はわれらのかたき、お前がこれから大きくなってお父ちゃんのかたきを必ず取らねば」(第9巻、犠牲にされた鉱夫の母の言葉)
「130万が親日反民族勢力として固まっている反人民的反動政権を打ち倒すために人民の犠牲はあまりにも大きなものであった」(第7巻、登場人物・李ジスクの見解であるが、作者の見解なのか)
「その連中に米国がなかったなら、誰一人血を流すことなく、そいつらは皆処罰して人民解放を迎えたであろう。米軍は絶対に許すことのできない民族の敵であり、人民の敵であった。だから民族解放戦争やパルチザン闘争は即米国との戦いであった。パルチザンの中でその事実を知らないで死んで行った人は誰もいなかった」(第9巻、このような見解は政府軍である国軍の中でも良心のある人であればもたざるをえなかったといって、つぎのように国軍将校・沈ゼモの見解を伝える)
「米軍のやっているころを考えてみると、米軍が敵のように思われ、そちらの方に銃口を向けたくなる時が、一、二度ではないのですよ」(第9巻)
「100日にわたる軍討伐隊の冬期攻勢の間、全南北と慶南そして智異山では1万8000余名のパルチザンたちが死んで行った」(第10巻、1952年の年始め冬)
「この時に6、7万名が死んで行きました」ということばも出てきます。そこで生き残った人々のことを頭に浮かべざるをえません。事態がどのようなものであったにしろ、彼は南の韓国の歴史のなかでは耐えられないという思いをしているだろうと思わざるをえません。この地において彼らの涙ぐましい哀歌は止まることがないであろうと思えてなりません。そして私が北を後にして南下の道を選んだ後、北の地においてもそのように死んで行ったであろう数多くの人々のことが忘れられないのです。政治とはそのように残酷なものかと改めて思います。
しかし歴史とは実際同じ内容で繰り返すことはないのではないでしょうか。私はいつも北にある金日成大学で出会ったその名も忘れてしまった南から北上してきた教授と学生たちのことを思い浮かべます。そして彼らの苦難と死、その受難を北の権力者勢力が不可避的に選択せざるをえなかった「歴史的選択」であるといって、その一生を共産革命に捧げる金ボムジュン少将の考え、そしてそれに同感せざるをえないと考えた今日の作家・趙廷来先生の歴史観に私は決して同意することができないのです。たとえ個人的には彼が善良であり、彼らに攻撃を加えた勢力が不正であったとしてもです。勝者と敗者の歴史がそのように安易に判断できないほどわれわれの知恵を超えているのかもしれないと嘆息をつきながらです。
やはり私は反動的なブルジョアジーの歴史観にとらわれているのでしょうか。先生は6・25を実に幼い身で体験したと思いますが、かすかな記憶でもお持ちでしょうか。私は先生よりは20年も歳を取った者として6・25の戦争に参加せざるをえませんでした。このような体験の相違はわれわれの意識の差を超えることのできないものとしたのではないでしょうか。これはわれわれが不可避的に担わなければならない歴史の作為ではないでしょうか。歴史経験の差異からくる歴史認識の差、そしてそこからくる歴史行為の差異というものは超えることのできない山のようにわれわれの前に立ちふさがっていると考えなければならないのでしょうか。これからやってくる歴史は先生においても私においてもまた違うものといわなればならないだろうという気がします。勿論アメリカも世界もそして韓国も先生が『太白山脈』において描いたような国と世界ではないのではないでしょうか。ああなんと驚くべき世界史なんでしょう。
それでもわれわれはこの地において共に生きて行かざるをえません。だから、われわれはそれこそ民主主義という原理に沿って寛容な姿勢で対話しながら日々を過ごしつつ、いったん多数であればこれを黙して受け入れるのだとでもいいましょうか。なんとか与と野が共に対話できなければと思いながら。これが長い我執の歴史を超え、われわれが妥協することに決めた見窄らしい知恵とでもいいましょうか。過ぎ去った歴史に対する哀歌を共に歌うことにしながらです。歴史は常にわれわれの判断を超えて進むものであると、今日も謙遜の徳をたたえざるをえないではないかと思います。このような老年の無気力をお許し下さいとお願いしながら整わない一文をおささげいたします。(2013年9月8日)
池明観さん逝去
本誌に連載中の「池明観日記―終末に向けての政治ノート」の筆者、池明観さんが2022年1月1日、韓国京畿道南楊州市の病院で死去された。97歳。
池明観(チ・ミョンクワン)
1924年平安北道定州(現北朝鮮)生まれ。ソウル大学で宗教哲学を専攻。朴正煕政権下で言論面から独裁に抵抗した月刊誌『思想界』編集主幹をつとめた。1972年来日。74年から東京女子大客員教授、その後同大現代文化学部教授をつとめるかたわら、『韓国からの通信』を執筆。93年に韓国に帰国し、翰林大学日本学研究所所長をつとめる。98年から金大中政権の下で韓日文化交流の礎を築く。主要著作『TK生の時代と「いま」―東アジアの平和と共存への道』(一葉社)、『韓国と韓国人―哲学者の歴史文化ノート』(アドニス書房)、『池明観自伝―境界線を超える旅』(岩波書店)、『韓国現代史―1905年から現代まで』『韓国文化史』(いずれも明石書店)、『「韓国からの通信」の時代―「危機の15年」を日韓のジャーナリズムはいかに戦ったか』(影書房)。2022年1月1日、死去。
