この一冊
『女性兵士という難問―ジェンダーから問う戦争・軍隊の社会学』(佐藤文香著/慶応義塾大学出版会/2640円/2022.7)
「軍隊とジェンダー」の歴史を追う
本誌編集委員 池田 祥子
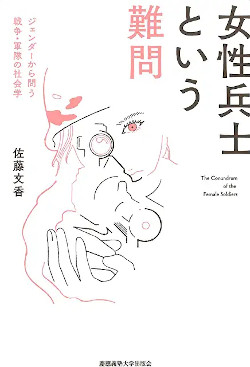
『女性兵士という難問―ジェンダーから問う戦争・軍隊の社会学』(佐藤文香著/慶応義塾大学出版会)
2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した!
ミサイルや無人ドローンが多用され、形態が明らかに変わった「戦争」、しかも、国連の常任理事国であるロシアがまずは手を出した「戦争」・・・それゆえ、長引く「戦争」に国連はこれまで以上にその無力さを晒している。
一方、対するウクライナは、かなりの物的人的被害を蒙りながらも、米英やEUの軍事的支援を受けつつ、「抗戦」の構えを崩していない。さらに、「欧州でも極めて高い割合」と言われるウクライナの「22%の女性兵士」の活躍までもが報道されている(「朝日新聞」2022.9.21)。
この戦争が今後どのように展開されるのか、「核戦争」が現実化するのか・・・今は予断を許されないが、ともあれ、「21世紀の国家・戦争・軍隊」がどのようなものになるのか、核拡大でなく核軍縮へ戻れるのか、さらには「軍縮」「武装放棄」そのものが課題になりうるのか・・・他人事でなく、真摯に問われているのは事実であろう。
今回紹介する文献は、「軍隊に関わる女性」―とりわけ「女性兵士」をめぐるフェミニストの対応や、国・軍の政策の変遷を「ジェンダー」的視点から研究された世界的な業績をフォローしたものである。
著者のジェンダー的立場
著者が「軍事組織とジェンダー」という博士論文を書いていた頃(2000年当初)、日本のフェミニストたちは、「軍隊に女性が増えることは女性の軍事化を招くだけだ」と考える「悲観主義者」の立場が大半だったという。
実際にも、「日本のフェミニズムの一角に女性兵士論が登場したことは遺憾だ」と書かれたり、女性学の雑誌で、「著者の論文が掲載されるならば自分は編集者を辞任する」と言った人もいたり、さらには、査読者から「自衛隊を軍隊として扱うような著者が将来論壇に出て行くことを憂慮する」と告げられたりしたという(p.2)。
これらのことは、日本が、憲法9条を掲げながら「警察予備隊」「保安隊」そして「自衛隊」という名前で、巧妙に「軍事組織」を拡大してきたアメリカおよびそれに従順な自民党政治への不信・批判が根底にあり、「自衛隊」をどこまでも「正規の軍隊」として認知してはならない、という警戒感もあってのことだろうとは思う。
また、軍隊の徴兵制が志願制に切り換わった1970年代以降のアメリカで、リベラル・フェミニストとして代表的だったベティ・フリーダンを初めとした、「女性が(軍隊に)増えれば、軍隊はよりよいものになる」と考える楽観主義への批判、抵抗もあったと思われる。
しかし、著者は、1970年、さらには1990年の湾岸戦争以降に顕著になる「軍事社会学」や「国際関係論」の女性兵士・軍隊・ジェンダーに関わる幾多の諸研究を参考にしながら、「軍隊と女性兵士とジェンダー」をテーマに研究を続けてきている。そして、「男性性と女性性をどのように構築することで軍隊は成り立っているのか、戦争によってジェンダー秩序がどう変容したり再生産したりするのかという多様なやり方を解明しよう」とする幾多のフェミニストの研究を紹介しつつ、自らもそれに関わっている。本書は、その一つの成果であろう。
軍隊(軍事組織)が、たとえ男性だけに限られていたとしても、そこでの「男性性」は、社会の女性性との交感、あるいはその「支え」があって初めて成り立つものである。
「軍事主義を根づかせるには、兵士の男性性以上のものが必要になる。少年を男に変えるには母の献身的な女性性が必要だ。兵士の男らしさを支えるためには妻や恋人の、あるいは性的サービスを提供する売春婦の女性性が必要だ」と。(シンシア・エンローの著作から)(p.16—17)
戦時性暴力とジェンダー
いま一つ、本書では、戦争に「つきもの」としての性暴力についての、フェミニスト軍事社会学者ルート・ザイフェルトの「ジェンダーに絡む分析」が紹介されている。「戦時性暴力批判」や「戦時の性奴隷」批判を運動として展開してきた日本の多くのフェミニストにとって、あまりにも「理屈」や「分析」に偏していると難じられるかもしれないが、男性性/女性性との絡みや「性暴力と女性嫌悪」との関連など、十分に参考になるだろう。
① 性暴力は戦争の「規則」の一部である。征服した領土で、勝者が女性にふるう性暴力はつねに容認されてきた。
② 性暴力は男性のコミュニケーションの要素である。それは、敵対する男性にシンボリックな屈辱を与え、「自分たちの女」を守れない無能者として、彼らの男性性を傷つける。
③ 性暴力は軍隊が兵士に与える男性性、あるいは戦争による男性性の高まりによって起こる。軍隊は「真の男」を必要とし、「真の男」であることは女性的と思われている性質を抑圧できることを意味するため、個々の兵士がレイプを拒むことは難しくなる。
④ 性暴力は敵の文化を破壊する方法である。女性は文化と民族の再生産者と見做されるため、強制的に妊娠させたり生殖不能にしたりすることでその生物学的基盤を破壊しようとする。
⑤ 性暴力は文化に根ざした女性嫌悪が危機の時に姿をあらわしたものである。女性は「敵」だからというより、憎悪の対象としてレイプされるのである(p.18)
つまり、「勇敢な戦士」になるためには、「肥沃な女性身体」として想起される「わが国」を守るために、その「純潔で従順な」女性を守りつつ逆に鼓舞され励まされ、ますます「真の男」としての兵士になっていく。その「真の男」とは、自らの内にある女性性の絶えざる抑圧であり、こうして内なる「女性蔑視」をさらに膨らましていくことになる。したがって、「戦時」の性暴力は、「戦時」のみの特殊な行為というより、平時の社会における男性性と女性性の絡み合いと無関係ではなく、まさしく接合的である、と。
自衛隊におけるジェンダー
このタイトルは本書の第Ⅲ部に当たる。因みに第Ⅳ部は「米軍におけるジェンダー」となっていて、そこでは「軍隊の女性会議」(バージニア州アーリントンの女性軍人記念館にて。2011年10月27~29日)や、「女性・平和・安全保障」会議(ロードアイランド州ニューポートの海軍戦争大学にて。2012年3月29~30日)の二つの会議に出席しての報告や、また当然ながら、アメリカを中心とした研究者の文献に依拠して書かれている。
その意味では。この第Ⅲ部は、著者の独自の研究領野でもあり、数少ない日本の自衛隊研究でもある。今回、特にスポットを当てて紹介しておきたい。
(1) 再出発の時代(1950-60年代前半):旧軍とは違います
戦後の日本国憲法の制定、とりわけ第9条の規定。にもかかわらず、戦中から顕著になっていたアメリカとソ連との「冷戦」、中国共産党の台頭、そして50年6月に勃発した朝鮮戦争。・・・ここで戦後のアメリカが手の平を返したように、日本を「アメリカの従順な、したがって従属的な(政治的・軍事的)同盟国」と位置づけなおしたことは周知の歴史的事実である。
1950年8月10日 ポツダム政令「警察予備隊令」
1951年 サンフランシスコ平和条約締結、日米安全保障条約締結
1952年 保安隊に。
1954年 自衛隊に。
最初の「警察予備隊」は、もちろん「戦闘を禁じられた小さな駆け出しの組織」(p.100)であったが、「制服を着た男性だけで構成されていた」。ただ、ごく少数の女性が、「一般職員」として「看護職域」で働いていた。もちろん「制服を着ることはなかった」
「保安隊」になると、「看護職の女性たちはより組織に統合され、制服を着用するようになった」
さらに、「自衛隊をつくり出そうとしていた男性の役人たちは「女らしい」軍隊看護婦として女性を包摂しようとしたようだ。第二次世界大戦でも看護婦が数多く活躍したという事実によって、政府と軍計画者およびその支持者は彼女たちを自衛隊に抵抗なく迎え入れた」(p.100)
こうして、「戦後の軍事組織が女性を公式に組織のなかに統合するという戦略は、たんに看護職を充填するという以上に、旧軍との連続性をカモフラージュし、軍事主義的な旧軍とは異なっているという印象を与えるのに役立ったのである」(p.101)
(2) 絆固めの時代(1960年代後半~70年代):あなたたちとともに
日本では60年安保闘争の後、高度経済成長期を迎える。また戦後生まれの子どもたちが大学に押し寄せ、世界的にもスチューデントパワーが全開、日本では全国的な「全共闘運動」が展開された。この当時は、左翼・新左翼でもレーニンの暴力革命論がなお支持されており、「ゲバルトローザ」と名づけられた女性闘士もいたほどである。
1967年、陸上自衛隊の一般支援職に女性が活用され、翌68年、アメリカの陸軍女性部隊(WAC)をモデルとした「婦人自衛官制度」(WAC)が発足する(なお、呼称は2003年「女性自衛官」に変更される)。
1965年から66年まで防衛庁長官官房長だった海原治は、たまたま視察した埼玉県のある補給廠で、「物を整理している」男性自衛官を見かけ、「大の男」がですよ!と仰天している。「大の男は表で機関銃を担いで走り回る。婦人が整理をする。そういうふうになるべきだと、そこで思ったんですよ」と、回顧している(p.102)。
また当時、アメリカの陸軍女性部隊(WAC)をリーダーとした韓国、ベトナム、日本などの女性士官の教育や訓練も行われているが、陸上自衛隊の婦人自衛官教育隊の初代隊長だった前田米子は、次のような「服務指導上の方針」を掲げ強調したと言う。
「優しく、麗しく、つつましく、心の笑みを忘れずに」(p.104)
これらの「女性性」の強調は、「自衛隊に女性を入れることに対する男性自衛官からの拒否反応や親たちの懸念に応えたものであった。この方針は、「強く、明るく、麗しく」と変更されて現在も引き継がれている」(同上)
以上のような、「異性愛的な女らしさ」の強調は、一方で危惧される「軍隊は女性を〝マニッシュ”にしてしまうのではないか」という風評や「恐怖」への緩和でもあったのであろう(同上)。
一方、この高度経済成長の時代、若い男性(しかも「有能な人材」から)は民間市場で「引っ張りだこ」、「自衛隊は適任者の若者を惹きつけるのに苦労した」という。したがって、「かき集めた」隊員は、「犯罪に手を染めたり、借金まみれになったり、部下を殴ったり」の「問題行動も多く、辞職率も非常に高かった」という。
そこで「発見」されたのが「女性」という「有能な人材プール」だった、という訳である(p.105)。
さらに、「婦人自衛官」に抵抗を示す部下たちに、ある陸上幕僚監部の男性は、次のようなことまで強調していたという。
「退役後の女性は国家安全保障の必要性を理解し、また、自衛隊の次世代を育成する「健全な」母になるだろう」(同上)
そして、1970年、防衛庁は初めての『防衛白書』を刊行する。そして、そこには「自衛官は一般の市民と同質の存在であり、制服を着た市民である」と(わざわざ!)記述されている。
この『白書』に見る、自衛隊の「軍事的イメージ」の脱色・緩和姿勢は、当時の「自衛官募集ポスター」にも顕著である。
1973年ポスターは、一人の自衛官と、女性・男性の友人が肩を組み合った「若者群像」である。添えられたコピーは、「我ら、青春期生!人間、仲間、友情、昨日、今日、明日、新鮮な心のふれあいが大切な時です」。
1976年ポスターは、制服を脱いだ2人の男性が腕相撲をしている図である。周りを、制服姿の女性自衛官(4人)、男性自衛官(3人)が取り囲み、笑顔で応援している。コピーは「友情が芽生え、信頼が生まれる」。
さらに、アメリカから日本に施政権が移された(日本復帰)沖縄に、1972年、早々と女性自衛官が沖縄の広報部門に配置されている。
いずれにしても、自衛隊から限りなく「軍事色」を脱色し、「市民」と仲良く友情を育む「ジエイタイ」というイメージづくりに、「女性の存在が不可欠であった」(p.107)ということである。
(3) 拡張の時代(1980年代―90年代):先進的組織
この時代は、いわゆる「バブル期」に当たる。前の時期にも増して、国内の労働市場が好況で、自衛隊の男性隊員の不足は続いていた。そのため、1960年代末に始まる「婦人自衛官制度」はその後も活用を続ける。1991年の女性自衛官数は8040人、3.4%である。相対的には「依然低い数値」ではあるが、「86年の4233人、1.7%からは二倍程度の増大である」(p.108)
ところで、この時代を大きく動かしたものに、一つは1982年から87年まで首相を務めた中曽根康弘の登場がある。「戦後政治の総決算!」を謳った彼は、「共産主義から<自由世界>を守ると公言し、防衛費のGNP1%枠の撤廃やアメリカとの合同軍事訓練の開始などを通じて、日本の抑制的な安全保障政策からの舵を切った」(p.107)
いま一つは、国連で発効した「女性差別撤廃条約」(1985年)である。もともと「国際的なプレッシャー」には弱い日本政府は、この世界的な動向に応じて、1985年「男女雇用機会均等法」を制定し、翌年施行される。
後者の、自衛隊に関わる影響は大きかった。すぐさま「防衛改革委員会」が設置され、「女性の数を5000人」とし、さらに、以前は「男性化されていた仕事」―高射運用、航空管制など―に就く女性数を急速に増大させた。その結果、「女性に開かれた自衛隊の職の割合は39%から75%に到り、看護や人事、総務、会計、通信といった<伝統的な>女性職の枠を超えるようになった」(p.108)ということである。
もっとも、民間企業での「男女雇用機会均等法」の施行が、女性の「総合職」と「一般職」への分離・二重化などに顕著なように、それは未だ、「男女平等」「ジェンダー平等」を真に志向し実現するものとは言えないものであるのと同様、この自衛隊内での女性兵士の増大も、必ずしも「ジェンダー平等」を志向・施行するものではなかったようである。本書でも、カール・ウィーガンドのインタビュー調査からの結論が引用されている(p.108)。
「彼らの決定はジェンダー平等というよりも、主要な同盟国にとって日本のイメージを<近代的>で<民主的>なものにしたいという欲望に動機づけられたものである」と(同上)。
また、以上のような対外的な糊塗策は、女性自衛官を地元のミスコンテストに参加させ、その優勝者のイメージを利用する、という戦略にも連なる。具体的には、「ミス高知」となった女性自衛官などが、「ワインレッド作戦」として、1990年代を通して積極的に利用された(p.109)。
一方、女性差別撤廃条約を批准するに当たって、総理府職員は、防衛大学校を女性にも門戸を開くべきだと主張していた。しかし、防衛庁の抵抗は激しかった。
しかし、「世界第2位の経済大国」という「自負」もあり、世界からの「期待」も無碍にできなかったのであろう。1992年、防衛大学校に女性の入学が認められた(1学年480名のところ、女子は60名から始まった)。
さらに、ソ連崩壊による東西冷戦終結直後、クウェートを併合したイラクを相手の「湾岸戦争」が勃発し、日本は90億ドルもの財政支援を行ったものの、自衛隊の戦闘地域への派遣は思いとどまった。しかし、財政支援は評価も感謝もされず(?)、逆に「Show the Flag!」とけしかけられる始末だった。ここから、政府の外交政策の転換が諮られ、「国際平和協力法」制定の下、1992年、自衛隊はカンボジアの平和維持活動に参加することになった。
さらに、1994年、連立政権で内閣総理大臣になった村山富市(社会党党首)は、「自衛隊の合憲」を認め、また予期し得なかったこととはいえ、翌1995年、阪神・淡路大震災およびオウム真理教徒による地下鉄サリン事件の救助活動によって、「自衛隊への信頼感」が強められていく。ただ、この期における「防衛大学校や自衛隊への女性の包摂」は、見て来た通り「ジェンダー平等の原則」から駆動されたものというより、「国内外で最先端の組織という自衛隊のイメージづくりを助け、軍事的拡張をカモフラージュするのに役立っていくことになった」と著者は言う(p.111)。
(4) 「国際貢献」の時代(2000年代~):われら平和維持者
さて、この時代を大きく支えた法は、1999年制定された「男女共同参画基本法」である。日本のフェミニストたちも、「平等」ではなく「参画」という「政策的」な言葉への違和感を表明しながらも、基本的にはその法精神の具体化に希望を託した。
自衛隊にとっては、「ジェンダー統合」をさらに促進する重要な法となった。
2002年の国連東ティモール支援団に、女性自衛官がはじめてPKO要員として含まれ、それ以後、「女性隊員が国連PKO任務に参加することが常態となった」(p.112)
2004年から始まるイラク戦争に、日本は延べ約5500名の陸上自衛官を「非戦闘地域」と強弁するイラクのサマーワに送ったが、各部隊には女性自衛官も含まれていた。
国会では、憲法で禁止されている「自衛隊の海外派兵」をめぐって激しく議論されたが、「地元の子どもに折り紙を教える女性自衛官」「地元に溶け込む女性自衛官」などが強調された。
こうした自衛隊内部での「ジェンダー統合」と、女性自衛官を前面に出した「自衛隊の利他的かつ平和に貢献するイメージづくり」が効を奏したのか、2007年、防衛庁は「防衛省」に難なく格上げされた。さらに、一部の部隊に託児所を設置するなど、自衛隊内の「ワーク・ライフ・バランス」などの環境整備までも行われている(p.113)。
いま一つ、2000年に採択された「国連安全保障理事会決議1325号」は、「平和創造と紛争解決における女性の役割と経験を認識し、平和・安全保障に関連した活動への女性の参加を増大させ、ジェンダー視点を導入するよう加盟国に要求」している(p.114)。
このような「グローバルなジェンダー主流化の時代において、女性を包摂する軍隊独自の思惑をジェンダー平等と区別することはますます困難になっている」と著者は記す(p.114)。
しかも、2011年、3.11の東日本大震災直後の10万人もの自衛官の働きで、自衛官および自衛隊への好感度は増し、それに乗じたのであろう、2011年の年の瀬に、政府は「武器輸出三原則」の緩和の方針を発表し、安倍晋三首相の下で、防衛装備移転三原則へと転換された。
以上のように、昨今の日本の自衛隊は、表向き「女性と女性性を活用しながら、平和的な組織としての自衛隊イメージを国内外に定着させてきた」(p.162)。これに対して、著者は、「この戦略は日本に特異なものというよりも、冷戦後のポストナショナルな防衛の新たな出現を先取りするようなものである」と警鐘を鳴らしている。
ところで、2020年度の日本の軍事費は491億ドル(5兆3000億円)、世界で第9位、立派な「軍隊」である。さすがに核兵器の使用と研究は控えてきたようだが、F-15、イージス艦、ペトリオットミサイルなど最新兵器を備えている(p.97)。まさしく「カモフラージュされた軍隊」なのである。それ故に、日本の自衛隊のこれからにも眼が離せない。本書の著者、佐藤文香さんの今後の研究に期待する所、大である。
いけだ・さちこ
1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。元こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。
この一冊
- 仁侠と謀略フリー編集ライター・森 ひろし
- 「軍隊とジェンダー」の歴史を追う本誌編集委員・池田 祥子
