この二冊
『道徳教育と愛国心』(大森直樹著、岩波書店、2018年9月、2808円)
『くわしすぎる教育勅語』(高橋陽一著、太郎次郎社エディタス、2019年2月、2160円)
教科としての道徳批判のための必読書
出版ジャーナリスト 日高 有志
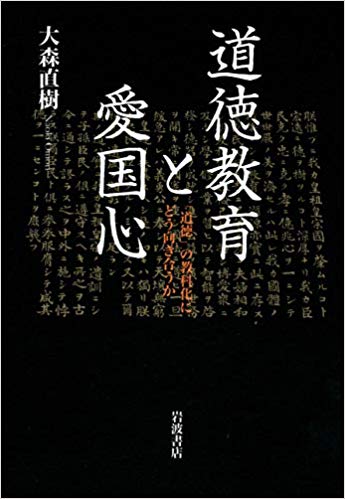
(大森直樹著、岩波書店、2018年9月、2808円)
はじめにお詫び。本来この欄は「この1冊」だが、今回は1冊にならず、2冊になってしまう。
21世紀の入口にさしかかるころから、戦後民間教育運動が力をもっていた時代には考えられないような「道徳」面での教育の荒廃がはじまった。1999年の国旗国歌法の制定、2003年の東京都教育委員会の10・23通達(都立校での入学式・卒業式、周年行事での日の丸掲揚・君が代斉唱の強制)、昨今の「特別の教科 道徳」の導入(小学校2018年、中学校2019年)……。道徳が教科になるということは、検定教科書が作られ、生徒一人ひとりの成績がつけられるようになる。つまり、道徳教育に対する国の関与が強まり、生徒に対する評価権を握った教師(教師は人事権を都道府県教育委員会に握られている)による道徳の押しつけが強まる。とどのつまりはお上による道徳の押しつけが、教育という装置を使って進むことを意味する。
さて、こうした「道徳」の押しつけは20世紀終わりころからとくに目立つようになったともみえるが、加速した部分だけを見るだけではどうも足りないようだ。そうした動向を、整理しながらよく見せてくれるのが、『道徳教育と愛国心』(大森直樹、岩波書店、2018年)だ。
まず、目次をとりあげておこう。第1章・道徳の教科化とは何か、第2章・戦前の道徳教育を見る、第3章・戦前の道徳教育は反省されたのか、第4章・復活した国定の道徳教育、第5章・国定による道徳教育はなぜ問題か、第6章・愛国心教育の制度的漸進、第7章・安倍政権下の24教育法と道徳教育、終章・「道徳」の教科化にどう向き合うか。
この本では、文科省が2017年までに作成した8つの学習指導要領をたどることによって戦後日本の道徳教育がどのように変遷したのかを跡づけている。同時に指導要領のなかで位置づけられた戦後の道徳教育が、いかに戦前の道徳教育の系譜を引きついでいるのかを明らかにする。
とりわけ、愛国心については、戦前の教育勅語などによる強要はいうまでもなく、戦後の指導要領のなかでも、1951年の「目標:民族的誇りをもち、郷土や国土を愛し、よりよくしようとする意欲をもつこと」にはじまり、2017年にも「我が国の国土と歴史に対する愛情を養う」「神話・伝承を手掛かりに、国の形成に関する考え方などに関心をもつこと」とされ、いわば一貫したテーマとして中心に位置づけられていることが明らかにされる。
敗戦と同時に教育勅語が廃止されたにもかかわらず、文部省は道徳教育、愛国心育成に対する関与を追求しつづけていた。そのためにぬけ道まで用意していたという。「誰が教育目標の決定をおこなったのかという視点から教育勅語と教育基本法の比較をおこなってみると、前者が君主の著作物として宣示され、後者が立法を通じて施行されたという、明瞭な差異が認められることとあわせて、つぎのことを指摘できる。それは、いずれにおいても、官僚による主導で教育目的の決定がおこなわれ、それが全国における教育のあり方を規定していくという、前者と後者をつなぐ連続性が認められることだ。国による教育目的の決定の継続であり、これが戦後教育改革の『ぬけ道』1となる」(国による教育目的の決定の継続)。このようにして作られたぬけ道がほかに2つ「国による教科目と教育課程構造の決定の継続」(ぬけ道2)、「国による教育課程の内容と授業時数の決定の継続」(ぬけ道3)、合計3つが作られたという。
ここでおもしろい指摘がある。戦後、指導要領のなかで文部省は、道徳教育に愛国心教育を書きつづけてきたが、1977年と89年にかぎっては指導要領のなかの社会科の目標から愛国心教育が削られた(269頁)。これは、当時の日教組による教育改革案づくりの運動の影響によるものだという。70年代は、算数・数学の水道方式をはじめ、国語、理科、社会など、戦後の民間教育運動の成果がもっとも花開いた時代であり、そうした成果を日教組が集約する役割をはたしていた。そのような運動の成果が指導要領にも一定の影響力を与えていたことがわかる。
さて、道徳教育の教科化にあたって、いじめ問題に対する処方箋のように語る政治家たちが多いが、はたして道徳教育でいじめが減少するのか。とってつけた理由のようにしか思えないのは私だけではないだろう。
むしろ本当の狙いは愛国心の強調・強要にあることが透けて見える。指導要領での一貫した愛国心教育の方針をみればよくわかる。この国の道徳教育の眼目は、家族や友だちを大切にしようというところではなく、この国を愛せ、国のために働け(死んでこい)というところにこそある。戦前・戦中にそれを露骨に表したものが教育勅語であり、それは敗戦で一度生命を絶たれたはずのものなのにいまだに生き返らせようとする政治家たちがいる。「教育勅語にはいいことも書いてある」といって家族や友人を大切にしようといっているというが、本当にいいと思っているのは、その後の「一旦緩急あれば」のほうなのだろうことは容易に想像できる。
▼ ▼ ▼

(高橋陽一著、太郎次郎社エディタス、2019年2月、2160円)
そこで、もう1冊を見てみよう。『くわしすぎる教育勅語』(高橋陽一、太郎次郎社エディタス)というタイトルが示すとおり、300字あまりの教育勅語を徹底的に解剖する。まずは教育勅語を逐語的に解説する第1部[精読]からはじまる。それぞれの文章の現代語訳にはじまり、文法的な解説、さらにその文章が生まれた歴史・思想・文化の背景を解説する。そこで明らかにされることは、「父母に孝に」ではじまり、まるで儒教道徳かのような装いをしつつも、そこに近代社会の価値観から国体思想までももちこんだキメラ(ライオンの頭、ヘビの尾、ヤギの胴をもつギリシア神話の怪獣)であることが明らかにされる。
次に第2部[始末]で教育勅語の始まりから終わりまで、第3部[考究]は教育勅語を考究するための資料集になっている。
第2部の一部を紹介しよう。教育勅語は、天皇が臣民に呼びかけるかたちの勅語、つまり天皇の著作として出されたが、本当の作者は、天皇ではない。臣下が起草したものを認めたものだ。勅語の起草者は、中村正直、井上毅(こわし)、元田永孚(ながざね)の3人がいた。ところが、3人は意気投合していたなどということはなく、元田が「明治維新以後の教育を『智識才芸』のみを尊重したものだと批判して、『仁義忠孝』という儒教流の徳目の重視を主張した」ことに対して井上が批判したことなどが明らかにされている。その後、国会開設に向けて両者は急接近する。そうして、「ただ儒教の道徳に戻るのではなく、西洋近代の道徳と会わせて語ることで、大日本帝国憲法の時代がスタート」する。じつに30回以上の書き直しを重ねて合作された。
悪名高い東京都教育委員会の10・23通達は、入学式・卒業式(周年行事)などの儀式での日の丸・君が代の掲揚・斉唱を強制するものだが、そうした学校行事の淵源はどこにあるか。これも明治のはじめに学校教育のなかにもちこまれたものだが、じつはキリスト教の教会儀式をとりいれたものだ。教育勅語にもちこまれた儀式がどうなっているか、この本をみてみよう。
「①職員と児童が『君が代』を合唱する。②職員と児童が『天皇陛下及皇后陛下の御影』つまり『御真影』に対して、深く頭を下げる『最敬礼』をおこなう。③学校長が教育勅語を読み上げる。④学校長が教育勅語について『誨告』(講話)する。⑤職員と児童が、その祝日にふさわしい『唱歌』を合唱する」
①⑤を賛美歌、③を聖書に置きかえれば、一度でもキリスト教の礼拝に参加したことがある人ならとても似ていることに気づくだろう。こうしたところにも、古くさい教えを近代的な装いにくるんだ「道徳」のばかばかしさが見えてくる。戦争中に小学生だった人に、当時、教育勅語の意味がよく分かっていたかを聞いたことがある。むずかしい言い回しで、その意味はよく分からなかったが、儀式のときに校長先生が大事そうに扱っていて、朗々と読む声で、たぶん、とても大事なことが書いてあるにちがいないと思っていた、ということだった。
ところで、「斯の道は、実に我か皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶に遵守すべき所、之を古今に通して謬らず、之を中外に施して悖らず」、天皇中心の道徳を「国の内外に適用しても間違いはない」としているところを読んでいてある思いに至った。
北朝鮮の国是である主体思想には「全世界の主体(チュチェ)化」というスローガンがある。全世界を北朝鮮化するというわけだ。悪趣味な誇大妄想としか思えないが、主体思想が誕生したころには、それくらいの意気込みはあったのだろう。そういえば、北朝鮮では、金正日のころから、「国体の護持」というスローガンも掲げていた! 主体思想も、朝鮮の権威主義的な王朝、スターリン主義、天皇制による専制などを重ねあわせたキメラのようなものだ。天皇制の影響がとんでもないところに飛び火しているのではないか。キメラがキメラを生みだす。民にとってははなはだ迷惑な「道徳」の押しつけにすぎない。
この国にも、「道徳」を押しつけたくてたまらず、いまだに教育勅語に未練たっぷりの政治家たちが多い。そうした政治家に騙されないためにも必読の2冊といえるだろう。
▼ ▼ ▼
最後に少し暴走ぎみの締めを書いておこう。それぞれは日教組の傘下にあったわけではないが、数学・数学、国語、理科、社会などの各教科・分野の民間教育運動が盛んにおこなわれ、それぞれの成果が教育の中身づくりに貢献していた時代は、それらをとりまとめる役割をになっていた日教組の運動も強く、文部省にも一定の影響力をもっていた。
昨今の日教組の組織率の低下など、運動の停滞は、草の根の教育活動の成果が検定教科書に吸いとられ、停滞していくのとほぼ軌を一にしている。私はたまたま少しまえに、数年間、アルバイトの仕事によって日教組で参与観察する機会をえたが、日教組にとって教育の中身づくりのうえで最も重要といえる全国教研にかつての面影はない。
たとえば、高大接続(高校と大学、高等教育の接続の意)の部会で、ある単組から文科省の大学改革を踏襲するような大学改革を自画自賛するレポートまで出ていた。かつての日教組なら、全国教研に上がってくる前に単組レベルではねられたようなものだろう。そういう中身(のない)のレポートが数あわせのように報告されている。
日教組の周年記念の本よりも、民間教育運動の歴史を総括し、次の時代を展望する本をつくるべきではという私の問いに、それは無理だというのが日教組幹部の答えだった。
日教組にその気がないなら、民間の有志の力でつくるしかないだろう。まずは、ここで紹介した2冊を読んで前に進もう。
子ども・若ものをふたたび戦場に送ってはならない。
ひだか・ゆうし
出版社勤務を経て、ジャーナリストとして活動。
この一冊
- 『アンダークラス─新たな下層階級の出現』労働問題研究者/姫井 正巳
- 『道徳教育と愛国心』『くわしすぎる教育勅語』出版ジャーナリスト/日高 有志
