特集●どこに向かうか2019
国交なき時代、細い糸で日本と中国を結んだ
男たちがいた
オーラルヒストリー南村志郎、『日中外交の黒衣六十年』を読む

ジャーナリスト・平安女学院大学客員教授 加藤 千洋
しばらく前のことだが、京都の街中の畳屋さんを何軒か訪ね歩いたことがある。お店の人に同じ質問をぶつけた。
「かれこれ半世紀ほど前のことですが、ひょっとして、おたくから畳を何枚か中国へ送り出したということはありませんでしたか」
いずれでも怪訝そうな顔をかえされただけで、これはダメだと早々に判断して取材は打ち切った。
新聞社を退職してから10年近く京都の私立大学で教員を続けており、こんな暇なことに時間を割く余裕も若干あるのだが、そもそものきっかけは本書『日中外交の黒衣六十年』の主人公、南村志郎氏から聞いた“日中秘話”が、かつて北京特派員を経験した筆者にとって特別に興味を引くものだったからだ。
▽ ▽
こんな話である――。
北京一の繁華街王府井大通りの商店街の一角に、「和風」という日本料理を供する店があった。いまは数えきれないほどの和食店が存在する北京だが、1960年代初めに開店した「和風」は戦後北京の日本料理店第1号だったという。
この「和風」を会場に毎月一回、北京駐在の邦人記者を集めた「朝飯会」が開かれた。主宰は中国側の対日工作の実務責任者だった廖承志。中国側のほかに周恩来総理から「民間大使」と呼ばれた西園寺公一も必ず同席した。
日中国交の早期回復論者だった西園寺は1958年に一家をあげて北京に移住し、民間交流の橋渡し役を果たしていた。これまた細々と続く日中民間貿易に携わって北京に駐在していた南村氏は、やがて西園寺の秘書役をつとめるようになった、という間柄だ。
他方、廖承志は当時の中国切っての日本通であり、最後は党政治局員にのぼりつめた共産党の大物。対日工作のほかに華僑政策も担当したのは、父親が孫文の盟友で国民党幹部、廖仲愷だったからだろう。両親が日本滞在中に東京で生まれ、早稲田に学び、マグロのトロを愛する健啖家としても知られた。
まだ国交のない日中間で記者交換協定が結ばれ、第一陣の日本側9社9人、中国側7人が双方の首都に着任したのは東京五輪が開かれた1964年秋のこと。「朝飯会」はそれから間もなくスタートした。
現在のように政府機関の定例記者会見などなく、メディアも中国共産党機関紙『人民日報』ほか数紙、まだテレビ放送はなくラジオだけ、そして外出も制限付きという情報過疎状況にあって、この月例会は邦人記者にとっては実にありがたい機会で、他国特派員からは「特別扱いだ」と抗議が出たという。
ちなみに第一陣の菅榮一記者(産経新聞社)はこんな証言を残している。
「朝食会では日本人特派員の質問に答えて、江戸っ子の廖承志は上手な日本語で、巧みなヒユを交えながら次々に語った。日中関係はもとより、中ソ関係、ベトナム問題などが主で、中国の立場なり、考え方がつかめて、情勢を判断するうえで、貴重な手掛かりとなった」(『春華秋實―日中記者交換40周年の回想』日本僑報社、2005年)
▽ ▽
さて畳の話が別の方向にずれてしまったが、この「和風」の客室に敷かれた畳こそが、実は京都から貨物船で天津に運ばれものだった。なんで南村氏がそんな事情を知っているかというと、戦後初の日本料理店づくりでさんざん苦労した当事者だからである。
60年代初めのある日、西園寺から「北京で日本料理屋をやってくれんか」と唐突に依頼されたのが始まりだった。「廖承志さんがやはり和食が食べたいと。廖さんから何とかならんかと言ってきた話なんだ。実は場所も中国側が王府井に決めていて……」と、すでに断りにくい状況になっていた。
仕方なく下見に行くと王府井にある東安市場の一角の倉庫のような場所だった。改装計画を急いでまとめ、板前は戦前の大連の邦人家庭で調理師をしていた人材を中国側が見つけ、魚など食材も大連、青島からの供給ルートを確保。あとは“和”の雰囲気を醸し出すのに畳を探したが、中国国内では見つからない。
ならばと、客室の寸法を計り、それを京都に送り、特注品で作ってもらったという。ただし畳店の「名前は忘れた」とのことだった。
国交正常化前の日中関係について、本筋からはずれた話を長々書いてしまったが、この「和風」については本書の第2部「私が体験した日中民間交流」で語られている。1966年に始まる文化大革命の嵐の中で「朝飯会」は中断し、廖承志は失脚し、「和風」も閉鎖。「民間大使」西園寺もスパイ呼ばわりされる。こうしたことに象徴される起伏に富んだ中国現代史と、それに翻弄され続けた1972年の国交正常化以前の日中関係に関わる、歴史の“ひだ”に埋もれていた貴重な証言が本書にはふんだんに盛り込まれている。
父親の仕事の関係で中国に生まれ育った南村氏は、故国に引揚げた後は1956年に戦後の初訪中をし、以後長期間の北京暮らしを体験し、その後も日中間を頻繁に往復してきた。
そうした1950,60年代の日中関係を語ることの出来る数少なくなった証言者に注目し、長時間のインタビューを試みたのは筆者もよく知るベテラン・ジャーナリストである。2人は何度か南村氏の体験談を聞くうちに「一人の民間人が半世紀以上にわたり日中友好活動に通り組んできた真実と体験を大切に伝えたい」と、オーラルヒストリーで整理することを思いたったという。
その思いは筆者もよくわかるので、もう少し本書の内容を紹介したい。
▽ ▽
第2部第1章「日の丸にすがり抗議する老婆の衝撃」では南村氏と戦後中国の関係のぶれない「軸」が形づくられた体験が語られる。
学生運動に関わり、東京外国語大学を中退後、南村氏は鉄鋼業界紙の記者となり、後に日中経済交流で重要な役割を果たす八幡製鉄役員の稲山嘉寛(後に新日鉄会長、経団連会長を歴任)の知遇を得る。
稲山のすすめで1956年10月、北京の「日本商品展覧会」に随行記者として参加する。出発前に鉄鋼産業をどう復興させるかを考えていた稲山から特別のミッションが託される。
それは戦後日本の鉄鋼産業にもなくてはならないと稲山が考える開灤炭鉱(河北省唐山市)と海南島の田独鉄鉱山、それに北朝鮮の茂山鉄鉱山が生産を再開しているか、確認してきてくれというものだった。
なんとか報告できる情報をつかんだのだが、この時、南村氏個人にとってはより重要な体験をした。
1956年の「日本商品展覧会」は戦後初めての中国開催で、会場はソ連の援助でできた北京展覧館だった。その前の広場にあるポールには日の丸が掲げられ、毎日多くの来場者でにぎわった。ある日、広場に大勢の人が集まり、ちょっとした騒ぎになっていた。何だろうと前に出た南村氏の目に入ったのは、ポールにしがみついて泣き叫ぶ老女の姿だった。
肉親を日本軍に殺された老女が「私は、この旗を絶対にこういう所で揚げることを許さない」と叫んでいたのだ。警察官が説得するが、がんとして動かない。群衆は黙って見ているが、その雰囲気は「誰もがお婆さんを支持している」と南村氏にひしひしと感じさせたという。
目に焼き付けられた光景は「被害者の傷みということはこうなんだ」ということをいやというほど感じさせ、それを理解することが「中国と交流するときの『基本』であると教えてくれました」と南村氏は述懐する。
▽ ▽
第1部「日中首脳外交を仲介して」から、本書のサブタイトル「三木親書を託された日本人の回想録」に関わる政界秘話も紹介しておこう。
1972年7月のポスト佐藤を争う自民党総裁選直前の4月、三木武夫(当時、自民党顧問)は訪中し、念願の周恩来総理との会談が実現する。そしてポスト田中の74年末、首相に就任した三木は停滞する日中平和友好条約交渉を加速させようと決意し、その意志を伝えるべく周総理宛てに親書を書く。
このいずれも仲介役は南村氏だったのだ。中国側窓口は、かねて付き合いを深めて信頼関係を築いていた廖承志だった。
72年訪中の時点で中国側が注視していたのは“台湾派”佐藤栄作の後継首相は誰か、だった。同じ“台湾派”と見られた福田赳夫か、国交樹立に積極発言をする田中角栄なのか、あるいは―。
「三木先生、あなたはどう思いますか」と口を開いた周恩来に、三木は即座に「田中です」と答えた。その根拠は、決選投票では三木派と中曽根派は田中支持に回るからだ、と説明したという。
この三木発言を周恩来は高く評価したそうだが、次の平和友好条約交渉に関しては三木政権に対し、実にリアルな見方を持っていた。
周恩来宛ての三木親書は、南村氏が東京・南平台の私邸に深夜、番記者に気付かれないように裏口から尋ね、応接間で「周恩来総理閣下」と表書きされた封筒を手渡されたという。
次の日に北京に飛び、中日友好協会会長に就任していた廖承志に手渡す。一週間、中国側の返事を待ったが、なしのつぶて。催促して一応「返書」は手にしたが、廖が漏らした中国側の見解は、三木にとっては厳しいものだった。
当時の三木内閣では副総理が福田赳夫、党三役に灘尾弘吉、松野頼三と“台湾派”が固め、役員には石田博英、赤城宗徳ら“ソ連派”とされる大物議員がいて、「親台湾派と親ソ派に囲まれ、反対され、三木さんはいくら頑張っても無理だったのでしょう……中国はなるほど、そういう分析をしたのだなと後から分かりました」と南村氏が本書で明かしている。
ほかにも60年代初めに北京国際クラブの食堂で鄧小平と言葉を交わしたこととか、毛沢東暗殺とクーデターの企てに失敗したとされる林彪事件の発生(71年)を、世界のどのメディアよりも早く察知したことなど、秘話、エピソードにはことかかない。
▽ ▽
最後にいまはなき王府井の「和風」の話に戻って拙稿を締めくくりたい。
「朝飯会」でも黒衣役だった南村氏の記憶では、中国側参加者は主宰者の廖承志のほか、その後の国交正常化でも活躍し、中日友好協会でも幹部職を務めた張香山、孫平化、趙安博、肖向前らだった。この4人は中国の対日工作チームのいわゆる「四大金剛」と呼ばれた顔ぶれである。(張香山に代わりに71年春の「ピンポン外交」で活躍し、後に駐日大使館公使を務めた王暁雲を「四大金剛」に数える説もある)
「朝飯会」は廖の軽妙洒脱なブリーフィングが北京特派員にとっては貴重な情報源となっていたが、上記の顔ぶれからは、中国側には邦人記者たちとの何気ない会話から、最新の日本政治、社会情勢をつかむ機会として重視されていたことがうかがえる。
この廖が率いた対日工作チームは通称「日本組」と呼ばれ、国務院(政府)に1958年に設置された外事弁公室の一部局とされる。主任は周恩来が兼務していた外相職に就いたばかりの陳毅だったが、実務は副主任の廖承志が仕切り、周総理から直接の指示が下り、報告も直接上げる総理直属組織だったという。民間外交の橋渡し役をしていた西園寺や南村氏のカウンターパートは、「民間」という体裁をとりつつ、実際は「党」や「政府」そのものの「日本組」のメンバーだったのだ。
この点について筆者が南村氏から聞いた話だが、周恩来は50年代の早い時期にすでに「対日国交樹立」の目標を定めていた。その実務工作を信頼する廖承志に託し、廖の部下の「四大金剛」が役割を分担した。彼らは「民間」の肩書で訪日し、政府関係者とも接触した。さらに節目には周総理が直々に党、政府、軍などの関係幹部を招集し、「日本組」の上げた報告を基に政策の検討を行っていたという。
戦後27年目にして日中国交は実現したが、親台湾派だ、親大陸派だと対抗心をむき出しにしていた日本の政界に比べ、中国側は一貫して戦略的外交を「民間」を巻き込んで展開していたのである。
そうした50年代、60年代の複雑、微妙な日中関係を間近に目撃し、時には当事者として関わった南村氏の証言記録は実に貴重なものといえよう。
かとう・ちひろ
1947年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒業、朝日新聞社入社。広島支局、大阪社会部などを経て北京特派員、論説委員、アジア総局長(バンコク)、中国総局長(北京)、外報部長、編集委員などを歴任。一連の中国報道で1999年度ボーン上田記念国際記者賞受賞。また「報道ステーション」コメンテーターも務める。2010年同志社大学大学院教授。2018年より平安女学院大学客員教授。主な著書に、『中国大陸をゆく』(共著、岩波新書)、『北京&東京 報道をコラムで』(朝日新聞社)、『胡同の記憶―北京夢華録』(岩波現代文庫)、『加藤千洋の中国食紀行』(小学館)、『辣の道 トウガラシ2500キロの旅』(平凡社)など。訳書に『鄧小平 政治的伝記』(共訳、岩波現代文庫)、『勁雨煦風 唐家璇外交回顧録』(監訳 岩波書店 )など。
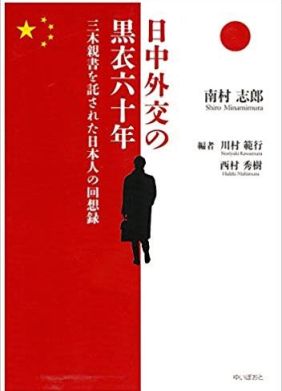
『日中外交の黒子六十年―三木親書を託された日本人の回想録』(南村志郎著、編者・川村範行、西村秀樹、ゆいぽおと刊、2018年10月、1400円+税)
目次
はじめに 聞き手・編者 川村範行
第一部 日中首脳外交を仲介して
第1章 三木武夫首相親書を極秘に周恩来総理へ
1 三木自民党顧問と周総理の会談をお膳立て(一九七二年四月)
2 国交正常化直後に廖承志訪日団受け入れ、三木副総理と会食
(一九七三年四月) 3 三木邸で親書託され、周総理に(一九七四年十二月)
第2章 江沢民主席訪日前に小渕首相の意向を極秘調査、訪日見合わせを進言
1 中国筋から極秘調査を依頼 2 後藤田官房長官から小渕首相の意向を確認
3 訪日見合わせを中国上層部へ進言 4 訪日に踏み切り、歴史問題に言及
第3章 中国人政治家との交わり
1 周恩来総理の質素・高潔さ 2 廖承志氏と家族ぐるみ昵懇
3 鄧小平氏の凄味 4 胡錦濤主席との出会い
第4章 日中間の政治家のパイプ衰退を嘆く
1 見直した古井喜実氏 2 後藤田正晴氏から野中広務氏へ
第二部 私が体験した日中民間交流
第1章 戦争の加害者・被害者意識―私と中国の原点―
1 中国で生まれ、戦後引き揚げ 2 稲山嘉寛氏との出会い
3 日の丸にすがり抗議する老婆の衝撃
第2章 一九五〇年代の新中国との貿易
1 稲山鉄鋼訪中団の成果 2 エビの尻尾切り 3 新中国との貿易契約第一号の秘話
第3章 廖承志さんと北京初の日本料理店
1 文革前に開店を担当 2 廖承志さんと駐在邦人記者との「朝飯会」 3 文革後、日本料理店再開
第4章 文革体験と林彪の死
1 文革〝マンツーマン講義〟受けさせられる 2 林彪の死〝トップシークレット〟知る 3 西園寺事務所を三十年
第三部 余生を日中の相互理解にかける
1 「民間」の弱体化 2 昔は訪中前に「学習会」をやった 3 天津で大学院講座と交流講座を開く
4 日中未来の会の代表として 5 若者を育てる
解説 日中平和友好条約締結に向けた三木武夫元首相の新事実が明るみに 川村範行
編集後記 聞き手・編者 西村秀樹
日中外交の黒衣六十年関連年表
特集・どこに向かうか2019
- ポスト安倍政権選択はグローバルな視点から日本女子大学名誉教授・本誌代表編集委員/住沢 博紀
- 外国人労働者政策の転換期を迎えて公益社団法人 自由人権協会理事/旗手 明
- まっとうな移民政策の確立こそ急務移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事/鳥井 一平
- 対等な労働契約関係には絶対になれないJAM参与・FWUBC顧問/小山 正樹
- 日本は移民国家になりえるのか青森公立大学経営経済学部教授/佐々木 てる
- 「トランプ再選」はあるのか国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎
- グローバルパワーシフトと一帯一路筑波大学大学院名誉教授/進藤 榮一
- 欧州は新しい地域主義の時代に突入したのか龍谷大学教授/松尾 秀哉
- 明仁天皇制・PKO・祭政一致国家筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹
- カルロス・ゴーンの虚飾と挫折労働経済アナリスト/早川 行雄
- 国交なき時代、細い糸で日本と中国を結んだ男たちがいたジャーナリスト・平安女学院大学客員教授/加藤 千洋
- かつて日本は移民送り出し国であった神奈川大学名誉教授・前本誌編集委員長/橘川 俊忠
