特集 ● 内外で問われる政治の質
「パクス・トクガワーナ」の虚妄(下)
柄谷行人流“カント平和論”を超えて
筑波大学名誉教授 進藤 榮一
「世界共和国という積極的理念の代わりに・・・戦争を防止し、持続しながら絶えず拡大する連盟という消極的な代替物のみが、法を嫌う好戦的な傾向性を阻止できるのである」
カント『永遠平和のために』宇都宮芳明訳、岩波書店、1985年(原著1795年)、45頁
1.「琉球独立」夢の跡
「琉球処分」へ / 「パクス・トクガワーナ」という虚構 / シャクシャインの戦い––アイヌ民族の
蜂起 / 非極の世界像から / 飢饉と貧困、そして百姓一揆へ / 頻発する民衆蜂起
2.構造的暴力、人間安全保障、そして「戦争のできる国」
積極的平和をつくる / 同盟の橋頭堡 / 「人間の安全保障」論へ––コロナ渦の中で(以上、34号に掲載)
3.「そろそろリベラルは、〈外交〉を語ろう」――二一世紀永遠平和論へ
「大転換期」の中で / 「アメリカの影」の下で / 「世界共和国」論をめぐって / フロイトの理論に
依拠して / 「世界共和国」論から「民主主義平和」論へ
4.国家間連携から市民的体制へ
二つの新世紀勃興期 / ユートピアとしての「世界共和国」 / 「カント読みのカント知らず」 /
国際連盟から地域経済共同体への展開 / コロナ渦での「新常態(ニューノーマル)」へ /
「ユーラシア統合」への道
5.「デモクラシー」論の陥穽
「デモクラシー」至上主義ではなく / 民主主義体制の陥穽 / 加憲論と国民投票正論の危うさ /
デモクラシーの罠 / 「日米同盟」の影、またはデモクラシーの罠(以上、37号に掲載)
ウイグル“ジェノサイド”非難の虚実 / アメリカ外交の二重基準 / 二元対立思考の過誤 / 二元対立思考を
超えて / 反植民地主義の視座
6.テリトリー・ゲームを超えて
平和実現のための六つの前提条件 / 日米安保の闇、あるいは「天皇メッセージ」 / 対米従属の
ブリッジヘッド(橋頭堡)として / 国民投票9条護憲論の虚妄 / 知の陥穽 / イージス・アショアを
買うということ / 再び、落日の軌跡
ウイグル“ジェノサイド”非難の虚実
アメリカをはじめ英国やカナダなど欧米諸国は、1948年国連で採択された「ジェノサイド(人種的抹殺)条約」を一つの根拠にして、中国における新彊ウイグル族の“人種的抹殺”もしくは“非人道的で人権無視の少数民族政策”を非難し、トランプ政権末期、ポンペイオ前国務長官以来、バイデン新政権下で、激しい反中非難攻撃を繰り返している。そしてそれを根拠に、2022年北京冬季オリンピックへの外交的ボイコット戦略に出ている。
しかし真実、習近平政権下の中国で、新疆ウイグル自治区において、少数民族“抹殺”政策が展開されているのだろうか。
国際アジア共同体学会は、2021年11月の国際年次大会で、5人の中国経済と中国少数民族問題専門家たちを招請して、現地実態調査を基に、報告を依頼した。
それらの報告によるかぎり、アメリカが主張するウイグル族“ジェノサイド”問題は、「新冷戦」下にあって覇権国家アメリカが展開する反中政策の一環であるといわざるをえない。
確かに、2008年3月のチベット・ラサ暴動や、2009年7月の新疆ウルムチ暴動発生以来、中国政府は、テロ再発防止に向けて、特にこの二つの少数民族の社会生活基盤の構築強化、特に職業訓練や言語文化問題に関して、過剰ともいえる政策対応をしてきたといえるかもしれない。
しかし、こと人口動態の変化に関する限り、ウイグル族の“民族浄化”政策は、”民族的抹殺“にしろ妊娠中絶強制化にしろ、現実とは程遠い、意図的で反中国的な論難と、結論せざるをえなかった。
実際、ウイグル族であれチベット族であれ、中国西北辺境部の少数民族の人口数は、ここ20年間で、減少ではなく、顕著な増大を見せているのである。
たとえば、1990年比で見た時――1990年人口を100とした場合—―2018年との比較で見るなら、ウイグル族の総人口数と人口増加率は、漢族の総人口と人口増加率よりも、はるかに大きい。すなわち、漢族総人口が785・7万人、人口増加率が136・7%であるのに対し、ウイグル族の総人口は1167・6万人、増加率は161・1%を記録し、漢族のそれよりもはるかに大きいのである
同様のことは、チベット族やモンゴル族に関してもいえる。
2000年代末の民族暴動発生以来、北京中央政府は、彼ら少数民族に関して、手厚い社会的保護政策を展開していることが、さまざまなデータからもうかがえるのである。
その一端が、漢族に強制している「一人っ子」政策を、ウイグル族など少数民族に関して採択していない事実、あるいは、水道電気などの社会インフラや、職業訓練や初等中等教育に関する手厚い保護政策に表れている。
アメリカ外交の二重基準
その時、改めて想起するのは、かつてアメリカが、2008年北京オリンピックの時にも、スーダン・ダルフール内戦の際に、国際人権団体の呼びかけに呼応して、北京オリンピック・ボイコットを国際的に展開していたことである。
実際、2020年時点でアメリカは、24の独裁国家を支援してきている。そして、民主主主義国家と専制主義国家を問わず、世界各国に大量の武器援助と兵器売り込みをしてきている。いったいわれわれは、そうしたアメリカ帝国の過去と現在とを、いかにとらえていくべきか。
2021年秋に放映された、ジョディ・フォスター主演のハリウッド映画『モーリタニアン—黒塗りの記録―』を見た。
9・11の、世界貿易センタービル倒壊の犯人の一人に仕立てられたアフガニスタンの少数民族国家モーリタニアの青年が、キューバ島グアンタナモ米軍基地内のアルグレイブ強制収容所で、20年近く拘留拷問を受け続けた悲劇を描いている。
いったいアメリカは、自らが犯している、それら反人道的政策の数々をどう位置付けているのか。
「デモクラシーと人権」を高揚する覇権国家の、外交理念と現実との自己矛盾を、私たちはいま直視すべき時が来ているといわねばなるまい。
二元対立思考の過誤
そこから私たちは再び、第二次世界大戦と冷戦とを経て――特にソ連共産主義体制の崩壊を経て――巷間、流布を強めた、(議会制民主主義にしろ大統領制民主主義にしろ)形だけの“民主主義体制(デモクラシー)”礼賛論の誤りを指摘できる。
その浅薄な現実を、2020年米国大統領選挙下で「分断と混乱」を極めたアメリカ民主主義の現実の中に見ることもできる。そしてそこから、デモクラシー至上主義論に立って、「民主体制」対「独裁体制」、「民主主義」対「専制主義(または「全体主義」)という、(日本を含む)西側“民主主義国”特有の二元対立思考の過誤と浅薄さを、指摘することもできる。
そしてそれを、冷戦終結後、特に9・11後に登場した「デモクラティック・ピース」論や「カラー革命」運動論に対する、根源的批判につなげることもできる。
一方で“共産党一党支配体制”下の中国を――特に2017年習近平主席の任期制限撤廃後の中国の政治体制を―-1930年代ドイツのナチ党支配体制やイタリア・ファシスト党体制、あるいは大政翼賛政党下の日本と同一線上に類型化し――「全体主義体制」、もしくは「専制主義体制」と規定する。
他方で、グローバル化で変容“解体”するアメリカ「民主主義」体制や、70年以上にわたる“自民党一党支配”体制下の日本を、ドイツや北欧等の社会民主主義的な諸国家と横並びにとらえていく。そして覇権主義国家アメリカの大統領制を、“デモス(民衆)のクラチア(権力)”を体現した「民主主義国家」と規定し、時に理想化し続ける。
あるいは、極貧下の被差別民(いわゆる「不可触民」)が全13億人口中、2億人を超える巨大格差社会インドを、選挙議会制民主主義を堅持している制度を根拠に、「世界最大の民主主義国家」と規定する、西側の過度に単純化された民主主義礼賛論がある。そしてその延長上に、“自由と民主主義”の価値を共有する(と称する)「自由で開かれたインド太平洋構想」の展開と限界がある。
二元対立思考を超えて
その上で私たちは再び、“グローバル資本主義体制”下の中国を、“専制主義”国家と規定し、北朝鮮や旧ソ連と同じ政治経済体制の鋳型にはめ込む危うさを、指摘できる。そして中国を、膨張主義的“共産主義”国家と短絡化して、米、欧、日など“民主主義的”な先進資本主義国家と、体制的に対峙させる危うさを指摘することもできる。
「民主体制対専制体制」あるいは「資本主義国家対共産主義国家」という、過度に単純化された――超歴史的な――二元対立的思考の陥穽である。
私たちに求められているのはだから、その二元対立思考を超えたところに、あるべき「統治のかたち」を求めることだ。
しかも承知のように、「遅れてやってきた途上国社会」は、長年の欧米植民地主義支配のために、多民族的で、時に多部族的な負荷を抱えながら、近代国家の道を歩まざるをえない。インドの場合、300年以上、中国の場合、180年以上、韓半島の場合、65年以上の、「分裂と分断」国家の歴史である。
加えて彼ら途上国社会は、多かれ少なかれ、近隣諸国家との間で錯雑な“国境線”問題を抱えている。アジアからロシア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ世界に共通するアポリアだ。それを、かつての帝国主義国家による「分断と支配」の残滓としての国境線問題といいかえてもよい。
二一世紀グローバル化の世界にあって私たちは、そうした途上国世界固有の歴史的地理的な現実と負荷を、何よりも直視すべきだ。その上で私たちは、政治体制のあるべき理念として、(デモクラシー・ファーストでなく)共和的で市民的体制の理念――いわば(シチズン・ファースト)――の現実化を、構築途上にある恒久平和のための体制上の条件としてとらえるべきだ。
求められているのはだから、多かれ少なかれ、それら歴史的現実を踏まえた上で、米国の「超格差社会」の登場と米国主導の“グローバル・ガバナンス”のあり方への批判的な視座だ。
そしてその米国主導の“グローバル・ガバナンス”の停滞と踵を同じくするかのように、いま一方で、好むと好まざるとにかかわらず、“世界最大の経済超大国”中国の主導下に、「アジア力の世紀」が登場し始めている。そして「パクス・アメリカーナ」の衰退の影で、いま「資本主義」中国が、経済と外交で圧倒的力を持ち始めたのである。
「アジア力の世紀」を軸とした「大転換期」――もしくは「大逆転する世界」――の到来である。
その時、私たちにとって求められる対抗軸は、米ソ冷戦期の<保守(右派もしくは資本主義)対左派(レフトもしくは社会主義)>ではない。途上国社会固有の「異形の他者」との、いわば「グローバル・サウス」との、共生の条件なのである。
それが、二世紀前のカントの「永遠平和論」が、二一世紀の今日、私たちに説く、第二の現代的意義である。そしてその時はじめて、「ポスト近代」の永遠平和の条件としての「アジア共生」の道が拓かれていく。
その上で、「日米同盟」機軸論の“絶対化”ではなく、いくつもの“同盟と戦略”のあり方を視座に入れた「同盟と戦略力の流儀」を見据えなくてはならない。
反植民地主義の視座
第三に指摘しなくてはならないことは、カントが、反植民地主義の視座を、永遠平和のための第三の確定条項としていたことである。その視座を、「世界市民法」の制定とあり方をめぐる提言の中で明らかにしていた。
すでに見たようにカントは、「世界共和国」の非現実性を説いた。そしてその非現実を説きなが、同時に「世界市民法」の存在とあり方を議論した。
そもそも人類の権利義務の法体系には、まず国内で適用される「国法」がある。次いで国家間で適用される「国際法」がある。その上で、国境を越えた市民の行動の権利義務を定める「世界市民法」がある。
しかしその国境を越えた第三の法体系としての世界市民法は、市民が他国を訪問できる範囲内にとどまる。カントのいう「訪問権」としての世界市民権である。
ここで私たちが注視しなくてはならないのは、世界市民法の内実が、あくまで「訪問権」にとどまっていることだ。それ以上に、他国の土地を所有したり、他国の人民の利益を収奪したりする権限を保障するものではないと、定義づけていたことである。
当時欧州列強は、すでに南北アメリカ大陸やアフリカ・アジア世界で、(カントの言葉を借りるなら)「水を飲むように」現地住民の利益を収奪し、欧州列強下の強権支配体制下においていた。いわゆる植民地主義の展開である。
カントはそれを、次のように語る。「ヨーロッパで再び戦争を行うために、(キリスト教という)敬虔について空騒ぎし、不正を水のように飲みながら、正統信仰で選ばれたものとみなされたがっている(欧州)列強諸国なのである。」(カント、50頁)
ここで「キリスト教」を、「デモクラシー」という言葉に置き換えてもよい。あるいは「世界共和国」という言葉に置き換えてもよい。
一方でカントは、「世界市民法」の考えに基づいて、世界の他の諸国を訪問して商取引を可能にする市民の権限を、世界共通の市民権として認めた。そして他方で、その「訪問権」を超えた権限を峻否すべきであるという立場こそが、永遠平和構築の第三の基本条件だとしていたのである。
カントは、「世界共和国」の構想を非現実主義的だと峻否した。そうしながらも同時に、「世界市民法」の現実性を語り、経済社会的で外交通商上の相互交流の推進を語りながら、反植民地主義の立場を鮮明にした。そしてそれを、「近代の新秩序勃興期」における国際平和の基本条件として提示した。
そこに私たちは、二世紀後のいま、「ポスト近代の新秩序勃興期」における、カント永遠平和論の第三の現代的意義を見ることができる。
「共生の条件」――もしくは「同盟と戦略力の流儀」――としてのカントの永遠平和論である。
6.テリトリー・ゲームを超えて
平和実現のための六つの前提条件
そして最後に、カントが以上の三つの確定条項に加えて、それら確定条項を現実のものとするための条件を、以下六つの前提条件としていたこと――つまりは「平和のための戦略」としていたこと――を、「予備条項」として提示したことを確認し強調しなくてはならない。
私たちはそこに、カントの平和論が持つ第四の現代的意義を見出すことができる。
すなわち、(1)将来の戦争の種を秘密裏に保留した平和条約の禁止、(2)領土の分割、領有、贈与の禁止、(3)常備軍の漸次的な廃絶、(4)軍備のための国債発行禁止、(5)他国の内政に対する不干渉、(6)他国との戦争で将来の平和回復時に相互信頼を不可能にする行為の忌避。
いったい二一世紀のいま、ポスト・コロナとポスト・ウクライナの世紀を生き抜くために、私たち日本人にとって、これら一連の「永遠平和のための予備条項」は、何を意味しているのか。
その解を、次のように要約できる。
第一に、第1条項と第2条項について。
1770年代当時、カントが生きていた時代に進行していたのは、プロシャ王国とロシア王国と革命フランス共和国の三国が、独立国家ポーランド王国を、三度にわたって分割していた、「ポーランド分割」の悲劇だった。
その悲劇をカントは義憤の対象にした。バーゼル講和条約締結数か月を待たずに執筆刊行し、王侯貴族、外交官や民衆に訴えた。「他国を分割し」たり、互いに取引して「割譲、交換、贈与」したりする「テリトリー(領土最大化)ゲーム」の愚かさを指弾したのである。
そうした講和条約は、けっして「講和」の名に値するものではない。条約の中に「次の戦争」への「種」が埋め込まれているからだ。
第二次大戦終結六年後に私たちの代表たちがサンフランシスコで締結した「対日講和条約」こそが、その二〇世紀版の典型であったろう。
そこでは、戦勝国代表アメリカが「日本国内のどこにでも、いつでも、いつまでも」軍事基地を設営し、基地を自由に使える全土基地方式が(秘密裏に、講和条約正文の陰で機密協定として)結ばれていた。
日米安保の闇、あるいは「天皇メッセージ」
しかも一方で、北緯30度線以南の琉球、沖縄群島は、米軍の軍事基地として――対ソ反共産主義攻撃の軍事拠点として――米軍が自由に使用できることが、取り決めていた。
その原点を、いわゆる47年9月と48年2月の二つの「天皇メッセージ」に見ることができる。
すなわち、47年9月19日、天皇の御用掛、外交官寺崎英成は、天皇ヒロヒトの御意思として、米国代表部代表シーボルトを訪問し、次のように伝えた。天皇の意見によれば、天皇は、日本は沖縄を米軍軍事基地として貸与(リース)し「25年から50年、あるいはそれ以上」使用できる。「沖縄永久基地貸与協定」を提案し、申し出ていたのである。
いわゆる「天皇メッセージ」のよる沖縄基地分割の歴史は、この時点で始まる。
しかもこの時、米国が沖縄を「自由に自国の意のままに」使用できるとする、もう一つの秘密協定が、上記の天皇メッセージによる秘密協定とワンセットとなり米日間で取り決められていた。
すなわち、「もし日本が南千島(国後、択捉、歯舞、色丹群島)のいわゆる北方四島を、日本領土として将来ソビエト・ロシアから返還してもらう取できた時には、日本は、アメリカが南方の沖縄群島に米軍基地を正規の軍事基地として永久に使用できる権利を取得できる」。
北方領土と沖縄群島の事実上の「分割割譲」を、講和条約交渉の裏の交渉で、極秘裏に米日双方の最高指導者たちが取り極めていたのである。
対米従属のブリッジヘッド(橋頭堡)として
戦後77年――日本もメディアや政党が沖縄の米軍基地撤去を要求し、真の意味での沖縄自立権を出張し始めている。あるいは、北方領土を「日本固有の領土」として対ソ交渉を数十回にわたり繰り返してきた。
だが前者についていえば、69年、日米安保条約改定交渉で、佐藤首相特別補佐官として若泉敬氏が、米国大統領特別補佐官キッシンジャーとの間で交わした秘密交渉と米日首脳間機密協定によって、沖縄基地の半永久的で自由使用権の容認が合意された。
後年、その現実を、若泉氏は、歴史的名著『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の中で、氏自身のみが知る得る超一級史料を直接引用して、明らかにしていた。そして氏は、上記の自著の完成を見た上で、かの沖縄の地で“自裁”していたのである。
かくて沖縄分割の悲劇は、51年サンフランシスコ講和条約と、その時取り極められた日米安全保障条約(いわゆる日米安保条約)と、その付属政府間協定、「日米行政協定」によって引き継がれた。
それがさらに、61年日米安保改定交渉で再確認され、同時に日米行政協定は、「日米地位協定」と名称を変えて改定され、米国の沖縄基地使用権は、「全土基地方式」として継受強化されていた。
『永遠平和のために』の中で、カントがバーゼル講和条約批判を軸に、「予備条項」の冒頭の第一項で「将来の戦争の種をひそかに保留した平和条約は結ぶべきでない」という警告を掲げた。そしてさらに第二項で「領土の分割、贈与」などの禁止を打ち出していた。
戦後日本外交に見る対米従属性と「自立性の欠落」の現実は、まさにカントの永遠平和論の機軸をなしていたのである。
国民投票9条護憲論の虚妄
柄谷“9条実践戦略”論は、下記二つの提案からなっている。
すなわち、憲法9条を国民投票にかけて、9条第3項に「自衛隊を海外に派遣できる」という新項目を加える、いわゆる「3項加権」論の是非を、国民に問う、という国民投票戦略である。
柄谷氏によれば、憲法9条は、「パクス・トクガワーナ」に歴史的淵源を持ち、その後「無意識の意識」として国民意識の中に定着しているのだから「必ず勝利する」。あえて、この国民投票の儀式を経ることによって、護憲論の正当性を確保すべきだ、というのである。
しかし、私たちは、国民投票論の持つ政治的危うさを繰り返し見てきている。国の命運を安易に国民投票に賭けた最近の「歴史の失敗」例を、2016年英国で実施された「EU離脱問題」で熟知している。
英国労働党を含めた全政党は、欧州と世界の命運を左右する歴史的な国際問題を、いとも安易に、国民投票の判断に託した。そして全投票数1%未満の僅差で、「英国EU離脱(ブレグジット)」に舵を切った。以後、2年余りの離脱交渉過程を進めながら、英国経済は、世界経済とともに、混乱と混沌の極みに達することになった。
憲法9条が国民投票にかけることになった場合、改憲側は巨額の資金と宣伝戦を展開するだろう。巨大企業の政治献金や電通など巨大広告会社による宣伝戦が、数億円単位の官邸機密費の投入も得て、テレビやメディアを通じ、9条改憲の道を容易に踏みしだいていくだろう。
住民投票前の「民意」が、住民投票宣伝期間の巨大企業献金とテレビ宣伝戦で、逆転敗北した最近例を私たちは、遺伝子組み換え食品表示に関するアメリカ各州での住民投票の結果に表れている。
例えば、2012年、全米最大の農業州カリフォルニア州の場合、住民投票前に、遺伝子組み換え表示を求める住民運動が圧倒的な勢いを持っていた。
しかし、州議会が定めた住民投票の実施段階になって、巨大化学産業大手のモンサントとデュポン・パイオニアが1600万ドル以上(日本円で1億7000万円以上)を投じて広告などで法案反対を訴えた結果、反対票が賛成票の2倍近くに達し、法案はつぶされた。
同じことは、コロラド、オレゴン、バーモント、ハワイなど、全米各州を生じている。
「これは、米国の民主主義が、カネで買えることのできる証明だ」と、Food Democracy Now! 創設者、マーフィー氏が語る所以だ。国民投票にひそむ巨大な危うさを、私たちは繰り返し想起しておいてよい。
知の陥穽
知と知識人は、これまで幾度も、この手の誤りを繰り返してきた。日清、日露戦争や、大東亜戦争開戦時もそうだった。
1993年当時の小選挙区制導入時もそうだ。オスプレイやF35などの超高額兵器購入時の軍事専門家の多数派やメディアの動向、あるいは郵政民営化や大店法改正などいわゆる新自由主義政策の導入展開に際してのエコノミストや経済専門家たちの知的動向も同じだ。
右も左も例外はない。
そして第二次安倍政権は、トランプ政権発足(2016年~)下、米国の要請に従って、超高額な兵器を“爆買い”し続けている。2019年5月トランプ大統領来日の際に、米国産ステレス戦闘機F35を105機購入約束した。既購入決定分を加えて147機。1機110億円、維持管理費含めて、総額約6兆2000億円にのぼる。
「F35を100機以上も買って、いったい何をするのか。目的が全く見えない」と、元航空自衛隊幹部が指摘する“無用の長物”である。
イージス・アショアを買うということ
加えて、米国が北朝鮮と対話を模索する中で、米国産ミサイル防衛システム「イージス・アショア」は、1基、1224億円。維持運営費を含めるなら、その倍額以上、1基、約3000億円かかる。それを、米側の要請に従って2基、購入するなら、総額約6000億円。
北朝鮮からのミサイル飛翔体を撃ち落とすため、地理的に最も近いとされる、山口と秋田に配備が予定されている。しかし、その後双方の配備予定に関する地形上の調査、周辺被害調査が、まったく杜撰で、十分な調査もしていないことが、明らかになった。
さらに米国製早期警戒機E-2D、9機を、約3480億円で。また無人偵察機グローバルホーク1機を、約173億円で。加えて、空中給油機4機、1000億円で、夫々アメリカから購入することを、政府は閣議決定によって決めている。
いずれも、北朝鮮から米国本土に向けて発射される最先端ミサイル兵器に対処して、それを打ち落とすための対抗ミサイル兵器群だという。
だが、それら対抗ミサイル兵器群は、いっさい機能することがない。というのも、北朝鮮から飛んでくるピストルの弾を、ピストルの弾で撃ち落とす類の対抗兵器でしかないからだ。しかも北朝鮮から飛んでくるピストルの弾は、秒速10メートル以上の速度で飛翔してくる。
それら対抗ミサイル兵器群を、なぜ日本は、米国の要請を受けて爆買いし続けるのか。素朴で深刻な疑問にとらわれざるをえない所以だ。そして極め付きは、オスプレイ、7機の爆買いだろう。オスプレイとは、水陸両用の海上から陸上へと侵攻作戦を展開するときの必須の軍事兵器群だ。
その陰で、経済成長率は低迷し続け、日本の国際競争力は低下し続けている。
私たちは、いったいいつまでこうした、市民生活軽視の政治外交をひきずり続けるのか。たとえばオスプレイ7機の購入をやめれば、日本の全国公立大学授業料一年度分を無料(!)にできるのである。
再び、落日の軌跡
二一世紀情報革命下にあって、科学技術力が国の興廃を決める決定的な役割を持っているにもかかわらず、である。
逆にいえば、先端的な科学技術力を持たず、それを生み出す研究・教育力に力を入れない限り、その国は、国際競争場で衰退し、落日の軌跡を辿らざるを得ない。
その軌跡を、いま日本は、「日米同盟機軸論」という戦略――つまりは非戦略――で手にし、それを強めている。まさにかつて森嶋博士が“日本没落”の条件として提起した“教育力”の衰退が、いまコロナ禍とウクライナ戦争下で進展している。
「永遠平和」を説くカントの平和論を、二一世紀の今日、“正しく読む”ことの枢要性を噛みしめ直すべきだ。その読み方を通じて、グローバル平和論の新しい理念と戦略力を手にすべきだ。
「戦略力の流儀」を幾重にも問い直す所以だ。(完)
しんどう・えいいち
北海道生まれ。京大法学部卒、同大学院博士課程修了、ジョンズホプキンズ大学留学を経て、筑波大学教授、同名誉教授。サイモンフレーザー大学、メキシコ大学院大学客員教授、プリンストン大学、ハーバード大学、オックスフォード大学、ウイルソン国際学術センター、延世大、各シニアフェロー歴任。専門はアメリカ外交、国際政治経済学、公共政策論。著書に『現代アメリカ外交序説』(吉田茂賞)『敗戦の逆説』『黄昏の帝国・アメリカ』『アジア力の世紀』『分割された領土』『戦後の原像』『アメリカ帝国の終焉』など著書多数。最近著に『日本の戦略力』(筑摩選書)。現在、国際アジア共同体学会会長、一帯一路日本研究センター代表、一社)アジア連合大学院機構理事長等。
「進藤榮一著作集―地殻変動する世界」全10巻刊行中
本誌で執筆頂いている進藤栄一さん(筑波大学名誉教授)の著作集全10巻の壮大な刊行がはじまった(花伝社より)。第一巻は昨年8月刊行、順次2年で10巻が刊行されるとのこと。以下紹介します。
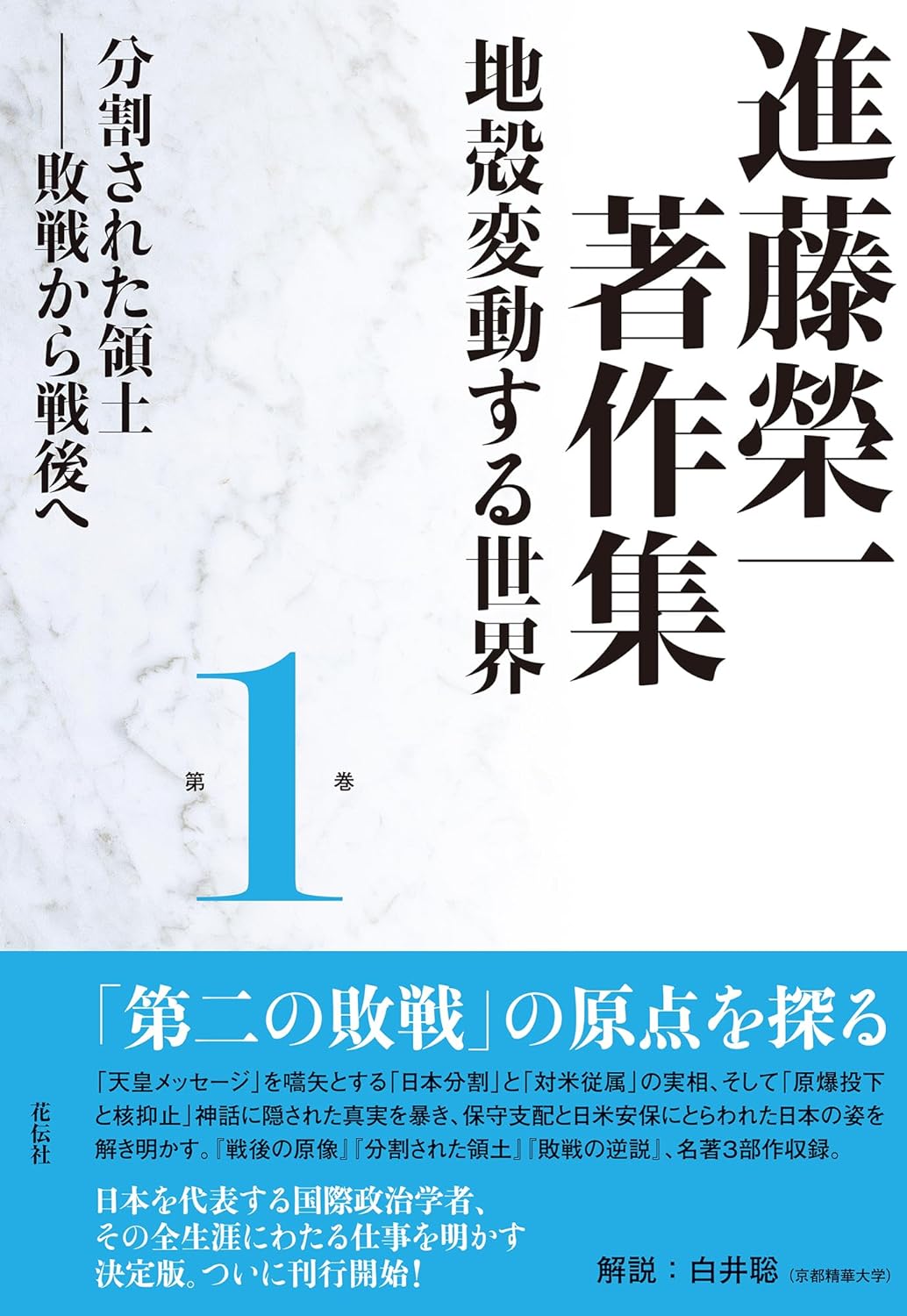 |
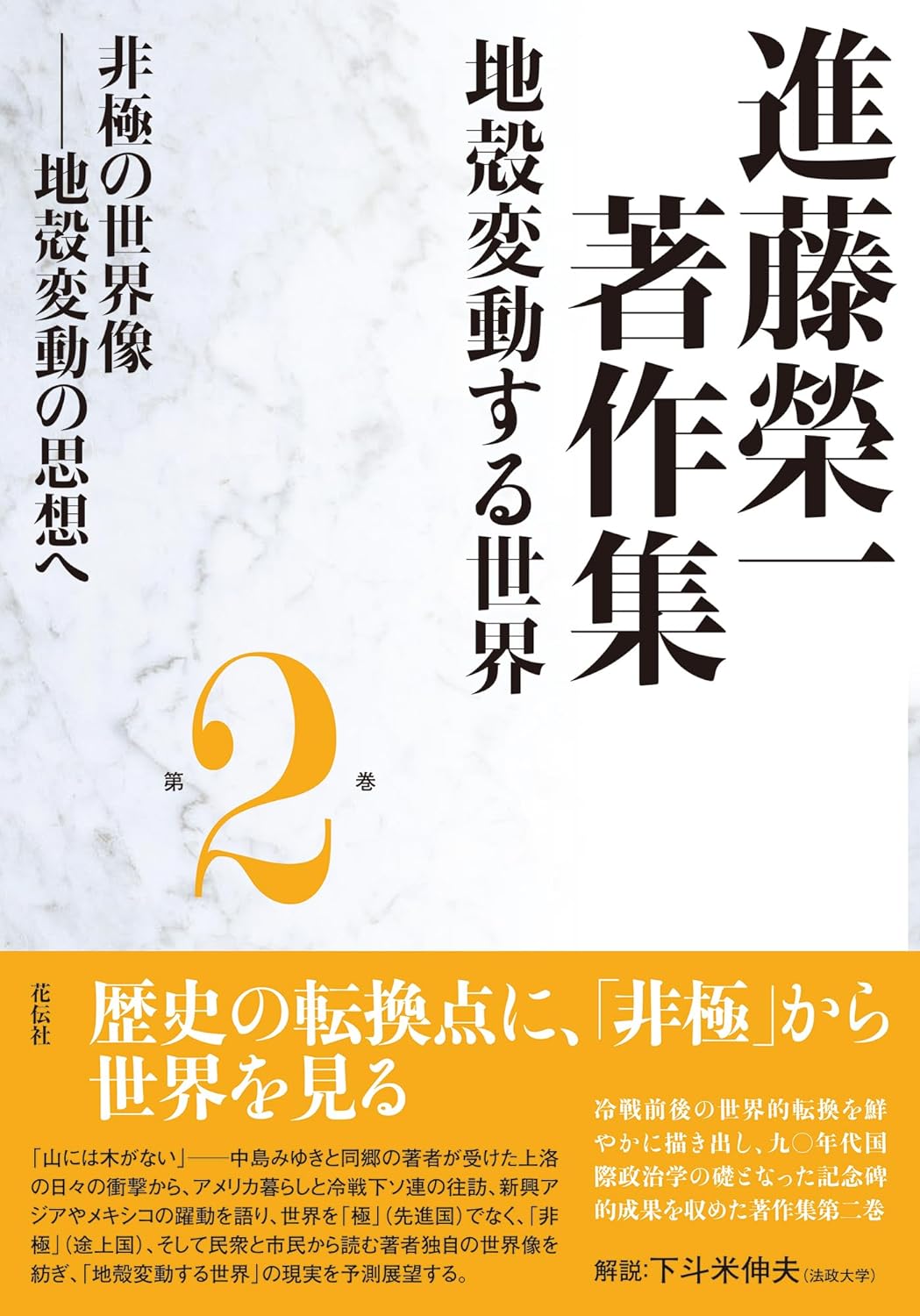 |
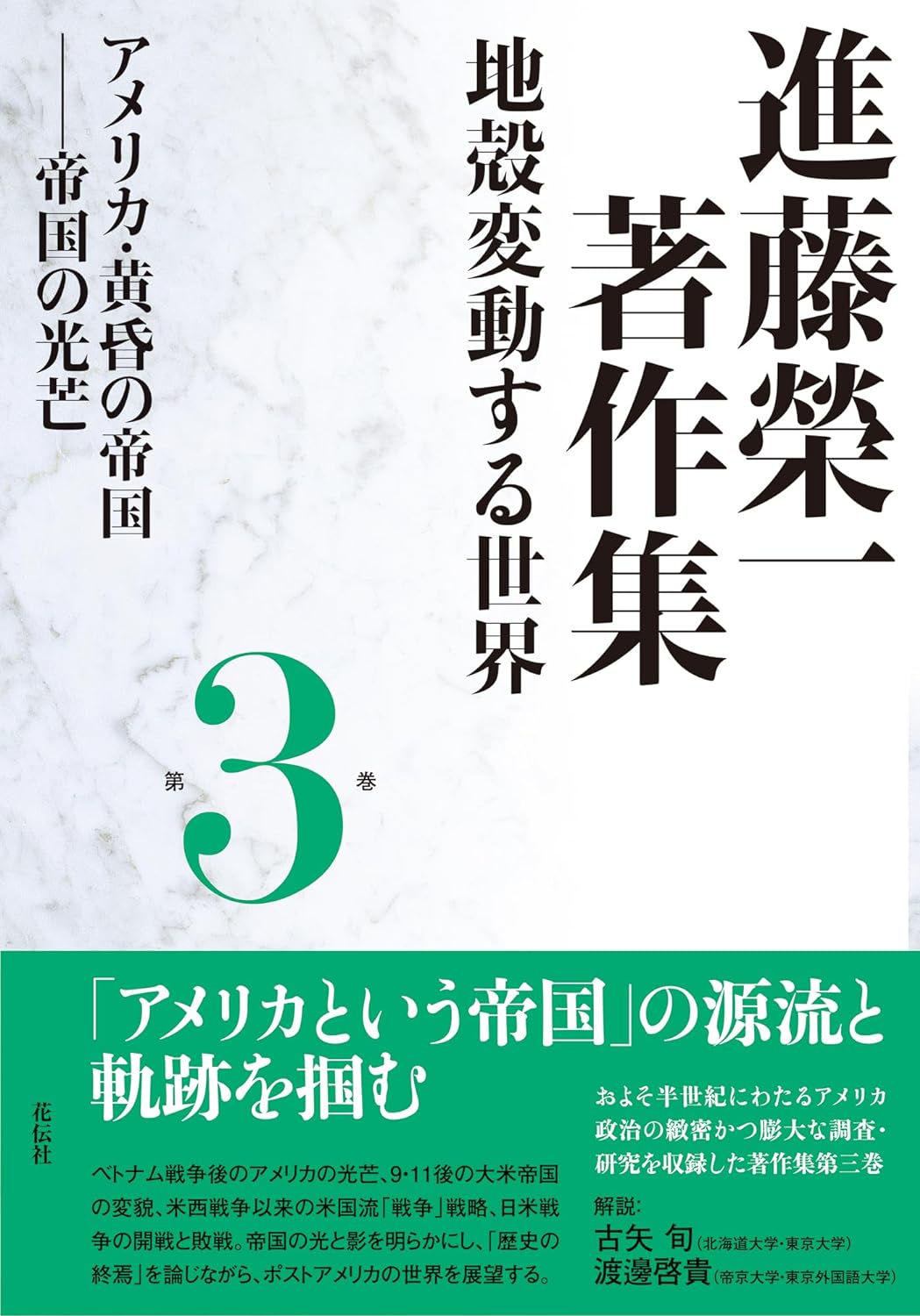 |
☆第1巻「分割された領土――敗戦から戦後へ」 (23年8月刊行)
『敗戦の逆説』(ちくま新書)、『分割された領土』(岩波現代文庫)、『戦後の原像』(岩波書店)など。解説・白井聰(京都精華大学)
ひとこと
今や歴史教科書にも掲載される(対米沖縄占領申し出の)「天皇メッセージ」を嚆矢とする「日本分割」と「対米従属」の実相を明らかにし、原爆投下と核抑止の神話を暴き、保守支配と日米安保がなぜ続くのか。隠されたクリオの顔を明らかにします。
☆第2巻「非極の世界像――地殻変動の思想へ」 (2024年1月刊行)
『非極の世界像』(ちくまライブラリー)、『地殻変動の世界像』(時事通信社)、『ポスト・ペレストロイカの世界像』(まライブラリー)、「「歴史の終焉」とは何か―フランシス・フクヤマとの対談」(月刊『アサヒ』所載)など。解説・下斗米伸夫(法政大学)
☆第3巻「アメリカ・黄昏の帝国――帝国の光芒」 (2024年4月刊行予定)
『アメリカ 黄昏の帝国』、『脱グローバリズムの世界像』、『アメリカ帝国の終焉』、「本多勝一との対談/白井聡『永続敗戦論』解説」など。解説・古矢 旬(北海道大学・東京大学)/渡邊啓貴(東京外国語大学)
☆第4巻「アジア力の世紀」
☆第5巻「現代紛争と軍拡構造」
☆第6巻『現代国際関係学』
☆第7巻『国際公共政策の道』
☆第8巻『現代アメリカ外交序説』
☆第9巻『最後のリベラリスト・芦田均』
☆第10巻『第二の戦後復興-同盟の呪縛を超えて』
現代の理論編集委員会
特集/内外で問われる政治の質
- 終末期を迎える自民党! 果たして野党による政治改革30年の新展開は可能か法政大学法学部教授・山口 二郎
- 排外主義的民族主義は混乱を糧として成長する神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠
- 追加発信行き着くところへ行き着いたイスラエル国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎
- ホロコーストから抜けられないドイツ在ベルリン・福澤 啓臣
- 万博開催1年切る 未だ迷走、課題は山積大阪市立大学元特任准教授・水野 博達
- 中小・下請け企業における賃金交渉の視点労働運動アナリスト・早川 行雄
- 「パクス・トクガワーナ」の虚妄(下)筑波大学名誉教授・進藤 榮一
- BUND(ドイツ環境・自然保護連盟)との対話本誌代表編集委員・日本女子大学名誉教授・住沢 博紀
- 昭和のプリズム-西村真琴と手塚治虫とその時代ジャーナリスト・池田 知隆
- 日本の「幼稚園と保育所」──その二元体制の根本問題を問うこども教育宝仙大学元学長・池田 祥子
- 20年を経た「平成の大合併」の評価と教訓松山大学教授・市川 虎彦
- 緊急寄稿日本共産党からの批判に反論する中央大学法学部教授・中北 浩爾
